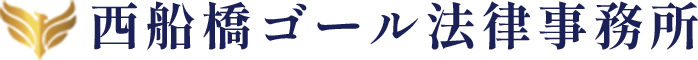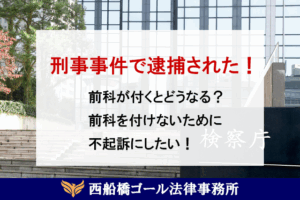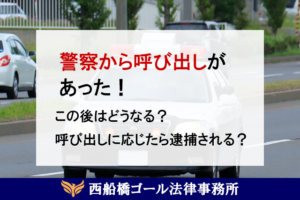勾留を阻止したい!家族は何ができる?弁護士に勾留阻止の活動を行ってもらうメリット
未分類
ご家族が逮捕されてしまった場合、一刻も早くその身柄を解放してあげたいと思うものです。
また、勾留を阻止することは、早期の職場復帰に繋がることもあります。
この記事では、勾留とは何か、勾留される要件、勾留阻止のためにできることを解説します。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業 平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 学習院大学法科大学院修了 平成27年9月 司法試験合格 アトム市川船橋法律事務所 令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業 所属:千葉県弁護士会
西船橋ゴール法律事務所では、逮捕後の接見・被疑者の早期釈放を目指す刑事弁護活動を行っています。
家族や親戚、知人等が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。
初回30分無料の法律相談や、正式な契約前でも利用できる初回接見サービスもございます。まずはご連絡ください。
(TEL)047-404-2258 西船橋ゴール法律事務所
メールでのお問い合わせを希望の方はこちらまで。
まずは勾留について知ろう
勾留とは何?逮捕と勾留の違いは?
勾留とは、逮捕された被疑者を留置施設などに10日間身体拘束することをいいます。
逮捕されると警察署に身柄を拘束されることから、逮捕=勾留と考えてしまう方もいるかもしれませんが、逮捕と勾留は別の概念です。
【逮捕】主に警察官が行う。最大72時間で、拘束場所は警察署の留置場
【勾留】検察官が裁判所に請求し、裁判所が決定の判断をする。原則10日間で拘束場所は警察署の留置施設や拘置所など
逮捕された人はまず警察署の留置場に入れられた後、取調べのために48時間以内に検察官へ送致されます。
そして、送致された先の検察庁にて検察官が裁判所に対し勾留請求するかを決めます。
裁判所が勾留決定を出せば被疑者の勾留が始まります。
つまり、時系列的には、逮捕の後に勾留が来ることになります。
逮捕された後の詳しい流れについてはこちら↓
【西船橋ゴール法律事務所】逮捕されたらどうなる?勾留された後はどうなるの?弁護士に早めに相談するメリット
勾留が決定されるまでの流れ
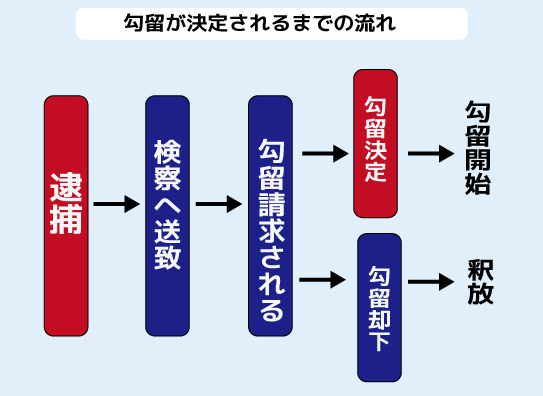
検察官へ送致された人は、ほとんどの事案で、24時間程度で勾留請求がされます。
勾留請求とは、身体拘束を10日間続けさせてほしいという検察官から裁判所に対する要望のことです。
勾留請求されなかった場合は、勾留されず釈放されます。
裁判所は、検察官からの勾留請求がくると、検察官から送られてきた一件記録(刑事事件の証拠や供述をまとめたもの)を確認します。
その後被疑者に対する勾留質問を行い、検察官の勾留請求に対する判断を下します。
千葉県では、逮捕翌日に検察庁へ連れていかれ、その日のうちに裁判所に行くケースが多いです。東京都では、逮捕翌日か、翌々日に検察庁へ連れていかれ、さらにその翌日に裁判所へ行くこともあります。
●勾留請求に対する裁判所の判断は2種類
検察官からの勾留請求に対する裁判所の判断としては、
・勾留決定(勾留される)
・勾留却下決定(勾留されない)
のいずれかになります。
勾留決定とは、検察官の勾留請求に対して裁判所が勾留を決定することを意味します。
勾留請求が却下されれば被疑者は釈放されますが、勾留決定が出されてしまうと、被疑者は勾留請求のあった日を含め10日間の身体拘束が決まってしまいます。
勾留が長引くケース
●勾留延長された場合
10日間の勾留の満期を迎えた際に検察側で十分な捜査を終えていない場合、検察官は裁判所に対して勾留延長請求をします。
勾留延長請求とは、被疑者の勾留をさらに10日間延長することの要望を出すことです。
勾留延長請求が認められると、被疑者はさらに10日間身体拘束をされることになり、逮捕から最大で23日間警察署に身体拘束されることになります。
●起訴された後にも勾留が続く場合
起訴された後も勾留されることがあります。
起訴前の被疑者が勾留されることを被疑者勾留(起訴前勾留)、起訴後の被告人が勾留されることを被告人勾留(起訴後勾留)と呼んだりします。
被疑者は被疑者勾留をされたまま起訴されると、通常裁判が終わるまで被告人勾留が続きます。
勾留するかを裁判所が判断するポイントは?
その前提として、まず裁判所がどのような要件のもとに勾留決定、勾留却下決定の判断を下しているのかを確認していきたいと思います。
勾留は、刑事訴訟法上一定の要件が認められる際に許されており、具体的には①勾留の理由②勾留の必要性の両方がある場合に認められています。
1.勾留の理由(刑事訴訟法第60条1項)
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
一 定まった住居を有しないとき(住所不定)
二 犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(罪証隠滅のおそれ)
三 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(逃亡のおそれ)
上記3つのいずれか1つに該当する場合には、裁判所は勾留することができると規定されています。(刑事訴訟法第60条1項より)
ですが、被疑者にこれら3つのいずれの事情もないと判断されれば、被疑者は勾留されず釈放されます
●「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」とは?
ここでいう「相当な理由」は、裁判例上では犯罪の嫌疑が一応認められる程度の理由であることを要するとされています。
ですが、被疑者が逮捕されている多くの事案では犯罪の嫌疑が何らかの証拠により一応認められてしまっているため、この要件は多くの事案で認められてしまっています。
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」であると判断されてしまった場合でも、罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなく、勾留の必要性もないとき等は、勾留却下決定が出され被疑者の身体拘束は解かれることになります。
(1)住所不定
刑事訴訟法第60条1項1号
「定まった住居を有しないとき」とは、住所や居住場所がないことを意味します。
(例)・住民票などがなく屋外で野宿しながら生活している場合
・ホテルやインターネットカフェなどを短期間のうちに転々としている場合など
なお、住所や居住場所がある方であっても、捜査機関や勾留質問で自身の住所や居住場所を黙秘し、他の資料を確認しても住所や居住場所が明らかとならなければ、「定まった住所を有しないとき」と認定されてしまう場合もあります。
(2)罪証隠滅のおそれがないこと
刑事訴訟法60条1項2号
「犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」とは、証拠に対して不正な働きかけをすることで、検察官の起訴、不起訴の判断を誤らせたり捜査や公判を混乱させたりするおそれがあることを意味します。
勾留決定が出される多くのケースでは、この罪証隠滅のおそれがあると認定されてしまうのです。
捕まった人にとっては、「自分は証拠隠滅なんてするわけない」と思いますし、皆さんはそれを検察や裁判官に必死に訴えますが、聞き入れてもらえない場合がほとんどです。
ルールを理解した弁護士が専門的な観点から主張を行うことが重要です。
1⃣罪証隠滅の対象はどのような事実か
2⃣どのような態様(働きかけ)で隠滅することが予想されるか
3⃣罪証隠滅の余地(客観的可能性及び実効性)があるか
4⃣具体的な罪証隠滅行為に及ぶ意図を有するか
5⃣罪証隠滅のおそれの程度
1⃣罪証隠滅の対象はどのような事実か(罪証隠滅の対象)
まず、罪証隠滅の対象となり得る事実を検討することになります。
ここでいう「事実」には犯罪事実だけでなく、実務上「重要な情状事実」(犯罪事実以外の事実)も罪証隠滅の対象事実とされています。
例えば、被疑者が犯罪事実を全て認めていたとしても、被害者に対して不正な働きかけを行い、本心でないにも拘らず被害者の方に「被疑者を許した」と言わせた場合など。
この被害者の供述は、被疑者にとって重要な情状事実といえるため、被疑者の被害者に対する働きかけは罪証隠滅行為となってしまいます。
2⃣どのような態様(働きかけ)で隠滅することが予想されるか(罪証隠滅の態様)
(例)
・押収されていないパソコンやスマートフォンその他電子機器等を破壊すること
・目撃者その他事件の証人となり得る者に接触し、不正な働きかけにより供述を捻じ曲げること(嘘を言わせる等)
3⃣罪証隠滅の余地(客観的可能性及び実効性)があるか
仮に罪証隠滅行為の態様(働きかけ)を予想できたとしても、罪証隠滅行為の実効性がなければ(実際にはできないようなこと)、そもそも罪証隠滅行為が行われることはありません。
この場合は罪証隠滅のおそれはないということになります。
(例)被疑者が犯人であることを証明する証拠として防犯カメラの映像があるも、その防犯カメラが既に捜査機関に押収されている場合

弁護士
このような場合、被疑者が捜査機関から防犯カメラを奪取することなど客観的に不可能ですし、実効性はないでしょう。
その場合、被疑者が犯人であることを証明する防犯カメラに対する罪証隠滅のおそれはないことになります。
4⃣具体的な罪証隠滅行為に及ぶ意図を有するか(罪証隠滅の主観的可能性)
こういった場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまう可能性があります。
罪証隠滅に及ぶ意図があると思われる場合
・供述内容がころころ変わる場合
・供述内容が矛盾している場合
・客観証拠に反する供述をしている場合
・反省の態度が見られないような場合
ですが、被疑者が取調べにおいて、当初から一貫して犯罪事実を認め自白しており、反省している態度を示している場合、被疑者に罪証隠滅行為に及ぶ意図が否定されれば、罪証隠滅のおそれはないものと判断されます。

弁護士
逮捕後は、誰もがパニックになるので、どう見ても不合理な供述をしてしまうことがあります。
弁護士が付いている場合は、客観的に信用される供述ができているのか・場合によっては正面から罪を認めることが必要なのかを検討しアドバイスができます。
5⃣罪証隠滅のおそれの程度
「罪証隠滅のおそれ」の程度に関し、最高裁は、その可能性が現実的といえるほどに高いものであることを要すると判断しています。
(3)逃亡のおそれがないこと
刑事訴訟法60条1項3号
「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」とは、被疑者が起訴されることや有罪判決の執行を免れる目的で裁判所に対して所在不明になることを意味します。
・生活状態が不安定の状況の者
(例)年齢が若く、人口の多い大都市で同居人もおらず単身で居住し、職業も日雇いの仕事を転々としている
・犯した罪が重く、非常に重い刑を科されることが予想される者
・前科前歴から実刑判決を受ける可能性が高い者など
逆に、相当な年齢であり、持ち家を所有し配偶者や子どもなど同居している家族がおり、さらに定職に就いてから長期間が経過している者は、逃亡のおそれを否定される傾向にあります。
2.勾留の必要性があるか
前述の「勾留の理由」に合致する事情がある場合であっても、勾留の必要性がなければ勾留することは許されません。(刑事訴訟法87条1項)
ここでは、以下の二点を比較することになります。
・公的な必要性(被疑者を身体拘束しなければ捜査の目的を達成することができないなど)
・被疑者の不利益(被疑者が身体拘束されること)
→被疑者を身体拘束することによる公的な必要性がほとんどなかったり、被疑者の受ける不利益が非常に大きい場合には、勾留の必要性はないということになります。
例えば、家出少女の被疑者であっても、親の身元引受により出頭が確実といえる場合や、被疑者の健康状態が悪く身体拘束が行われると生命や身体に危険が生じる場合などには勾留の必要性はないという判断になることもあります。
長期間の勾留を阻止するために主張すべき点/家族ができること
このような長期の身体拘束を避けるためには、早期の段階から身体拘束を解くための活動をしていく必要があります。
●最初に行うべき身柄解放の活動は、勾留阻止の活動
まずは、逮捕された被疑者がそのまま勾留に繋がらないようにする活動が必要となります。
勾留阻止のためには勾留される要件や勾留阻止のための手続きについて熟知している刑事弁護士に相談しましょう。
●勾留を阻止するためのポイント
勾留が認められる場合は、①罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由、②逃亡すると疑うに足りる相当な理由、③勾留の必要性が認定される場合です。
そのため、被疑者の勾留を阻止するためには、①罪証隠滅のおそれがないこと、②逃亡のおそれがないこと、③勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に訴えていく必要があります。

弁護士
効果的な弁護活動を行うためには、被疑者の方の家族や恋人、職場関係者の方など被疑者に身近な方々の協力が不可欠となります。
1.罪証隠滅のおそれがないこと
罪証隠滅のおそれがないことについては以下のような事情などを主張していくことになります。
✅被害者やその親族、目撃者やその他事件関係者の連絡先や住所などを知らない(罪証隠滅の余地がない又は可能性が低い)
→被疑者と被害者の供述により一定程度裏付けられるので、裏付けとなる資料を提出することはあまり多くありません。
✅捜索・差押えなどが既に行われていて、物的証拠が既に押収されている(罪証隠滅の余地がない)
→捜索・差押えが勾留請求前に行われた場合、その結果に関する資料が一見記録(刑事事件の証拠や供述をまとめたもの)にまとめられているので、裏付けとなる資料を提出することはあまり多くありません。
✅被害者との間で示談が成立している、又は被害者に被害弁償金を支払っている(罪証隠滅の意図がない)
→こちらは早急に被疑者側から提出する必要があります。
逮捕、勾留請求前に示談が成立している場合や被害弁償金が支払われている場合には、勾留請求がされない、もしくは勾留決定が却下される可能性が高いため、早急に示談書や被害弁償金を送金した振込明細書、金銭受領書などの提出が必要となります。

弁護士
こちらから被害者との示談の結果を検察官に知らせると、検察官は被害者の方に示談の有無をすぐに電話で確認してくれます。
✅詳細な自白調書があり反省している態度を示している(罪証隠滅の意図がない)
2.逃亡のおそれがないこと
逃亡のおそれがないことについては以下のような事情などを主張していくことになります。
✅持ち家を有していること
→自宅の売買契約書、残ローンの返済予定表、登記簿の写しなどを提出すると良いでしょう。
✅定職に就いていること
→会社のホームページや名刺などがあれば明らかとなります。
✅同居家族がいること
→警察があらかじめ被疑者の戸籍謄本を取得しているケースが多いため、こちらから何か資料を出すことは多くはないかと思います。なお、現行犯逮捕の場合などは、送致前に警察が戸籍を取得できているかは微妙なところですので、こちらから何らかの資料を出すと有効かと思います。
✅身元引受人がいること
→弁護士が作成する身元引受書などの書式を利用して、ご家族、親戚、友人、恋人、会社の同僚・上司その他被疑者と近しい関係の方から1~数通取れるとよいかと思います。
✅事案が軽微であり罰金処分になる可能性のある事案や執行猶予の可能性が高い事案であること
→客観的な事実さえ明らかであれば、軽微な事案か否か罰金処分の可能性がある事案か否か、執行猶予の可能性が高い事案か否かは検察官、裁判官であればそれなりに評価できることなので、被疑者側で何か準備すべき資料というものはありません。被疑者側としましては、事案が軽微で実刑になるようなものではない若しくは罰金刑以下になると強調しておけばよいでしょう。
3.勾留の必要性がないこと
勾留の必要性がないことについては以下のような事情を主張していくことになります。
✅定職に就いており、勾留が長引けば失職するおそれがあること
→会社の就業規則、被疑者本人の供述などを提出します。(弁護士が被疑者と接見し事情聴取結果報告書や供述録取書などを作成します)
・代替性のない仕事をしている方は、自分がいないと自分だけでなく会社にも大きな不利益をもたらすことを強く主張するのが重要です。
・代替性があっても、繁忙期などの人手が必要な時期の身体拘束は会社にも不利益が大きいので、強く主張すべきです。
弁護士が付いている場合はその点に注意して書面を作成します。
✅会社から解雇され失職した場合家族が路頭に迷う可能性があること
→家族の方による上申書などを提出します。
✅病気を患っており、勾留にたえられる身体的・精神的状況ではないこと
→医師の診断書や薬の処方箋、お薬手帳などを提出します。
勾留阻止のためには弁護士のサポートが必要不可欠
1.検察官に対する活動
検察官から裁判所に対して勾留請求がなければ、勾留はありません。
そのため、まずは検察官に対し、勾留の理由(罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことなど)と勾留の必要性がないことを主張し勾留請求をしないよう説得していく必要があります。
この主張は、最低限書面を提出して行うことになりますが、事前に担当検事に連絡し、電話や対面で検察官に勾留の理由及び勾留の必要性がないことを主張することもできます。
千葉県ですと、逮捕された日の翌日の午前中に検察官へ送致され、午後の早い時間には裁判所に勾留請求されてしまいます。
逮捕されたら、可能な限りその日のうちに弁護士に依頼し、次の日の午前中に検察官に対して勾留請求を阻止するための働きかけをしてもらいましょう。
2.裁判官に対する活動
●勾留請求却下のための意見書提出
検察官が勾留請求をした場合は、裁判所に対して勾留請求を却下すべきとの意見書を弁護士から裁判所に提出することになります。
千葉県では逮捕翌日の午前中に検察官送致→午後に裁判所での勾留質問があるので、弁護士が当日午前中に依頼を受けた場合、検察官への働きかけをとばして、裁判官に対して勾留請求却下を求める活動から行うことになるのが多いです。
裁判官に対する勾留請求却下を求める活動においても、裁判官に勾留の理由及び必要性がない旨を記載した意見書をFAXで送付することになりますが、時間があれば電話や対面で裁判官面談を行うことも可能です。
●勾留決定への不服申し立て
裁判所が検察官の勾留請求を却下すれば被疑者は当日中に釈放されますが、裁判官が検察官の勾留請求を認めてしまった場合、被疑者は10日の勾留が決定してしまいます。
その場合には、弁護士に依頼し、準抗告(裁判官の勾留決定を取り消すよう請求する勾留決定に対する不服申し立て)を行うことになります。
この不服申し立てが認められると、被疑者は釈放されることになります。
⚠️裁判所が検察官の勾留請求を却下した場合でも、検察官が不服申し立てをすれば、被疑者は釈放さません。ですが、検察官の不服申し立てが認められないことが決まれば被疑者は釈放され、検察官の不服申し立てが認められてしまった場合には勾留が決まってしまいます。
●刑事事件は時間勝負
西船橋ゴール法律事務所では、午前11時に依頼者様から相談・依頼を受け、午後2時に意見書提出→裁判官面談を経て、勾留請求を却下したということがありました。
このような短い時間の制約の中で結果を出せたのは、数多くの経験を通じて何をどのように主張すれば効果的かがわかっていたからだといえます。
勾留阻止を目指す活動は、非常にタイトな時間の制約の中で行われることになります。
大切な方の身柄解放をしたいのであれば、勾留阻止のための活動を多数経験している弁護士にできるだけ早い段階で依頼をするのが良いでしょう。
千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所では、逮捕後の接見・被疑者の早期釈放を目指す刑事弁護活動を行っています。
家族や親戚、知人等が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。
初回30分無料の法律相談や、正式な契約前でも利用できる初回接見サービスもございます。まずはご連絡ください。
(TEL)047-404-2258 西船橋ゴール法律事務所
メールでのお問い合わせを希望の方はこちらまで。