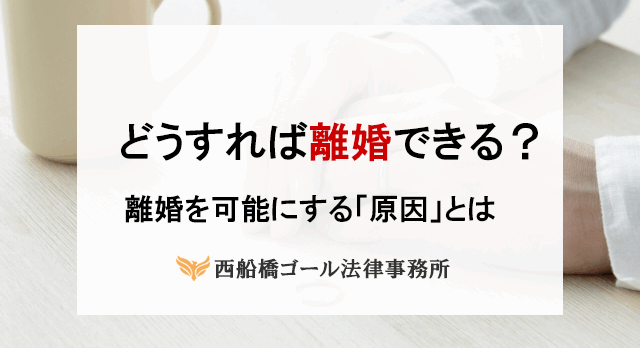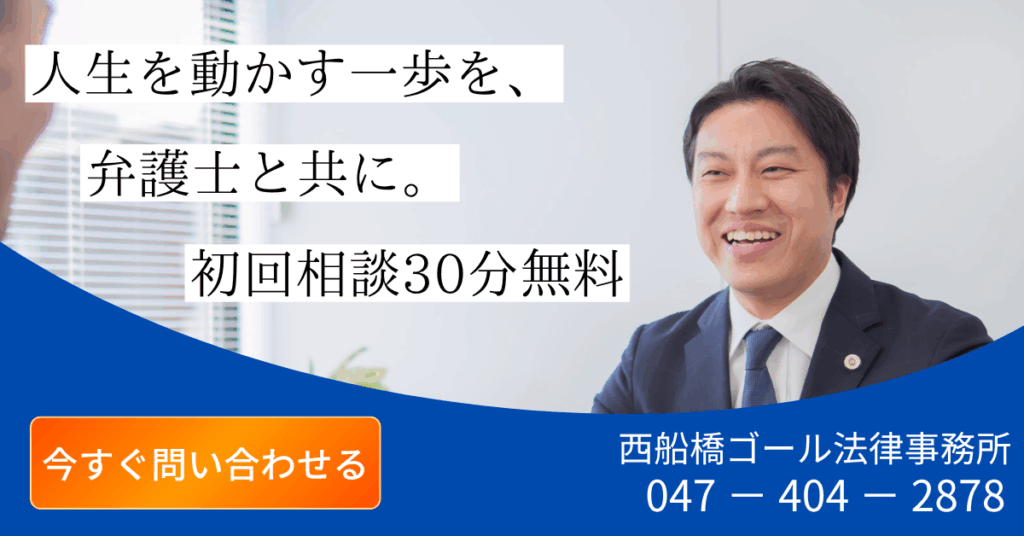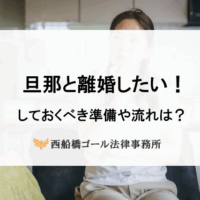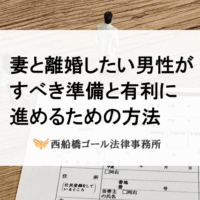平成28年3月 八千代松陰高等学校 卒業
令和2年3月 早稲田大学法学部 卒業
令和4年3月 早稲田大学大学院法務研究科 卒業
目次
離婚はどうしたらできる?
離婚するには法的な要件を充たすことが必要
お互いが離婚したいと思っているのなら、離婚届にお互いがそれぞれ署名し、提出することで、離婚することができるはずです。
しかし、夫婦の一方が、離婚することを拒絶している場合はどうでしょうか?
夫婦の一方が離婚を拒否している場合に離婚が認められるには、裁判所で離婚判決をもらう必要があります。
この離婚判決をもらうには、離婚原因があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
離婚を可能にする「離婚原因」とは?
離婚を可能にする離婚原因
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(モラハラ・DVなど)
1.配偶者に不貞な行為があったとき

この不貞行為というのは、旦那さんや奥さん以外の人と、性交渉を行うことなどをいいます。
ここで、不貞行為とは、どのくらいのものから、離婚原因として、認められるのだろうかと疑問をお持ちになった方もいるのではないでしょうか。
まず、不貞行為の定義とは、夫婦の一方が、夫または妻以外の者と、自由な意思のもとに、性的関係をむすぶことです。
まず、自由な意思で、性的関係をむすぶことが要件としてあげられます。
すなわち、不同意性交や不同意わいせつなど、性犯罪の場合には、当然、不貞行為ではありません。
【どこから不貞行為となるのか】
まず、不貞行為とは、性的関係をもつこと、すなわち、性行為をしていることを指すものです。
そのため、性行為(男性器を女性器に挿入すること)や性的類似行為(オーラルセックス)などをした場合には、不貞行為として認定されます。
逆に言えば、性行為をしていない場合、単なるデートや、相手に好意を伝えるメッセージのやり取り、二人だけで出かける、手をつないでいる、キスをするなどの行為については、不貞行為とは認定されないことになります。
そのため、不貞行為があったことを認定するためには、相手と同棲していることや、一緒にラブホテルを出入りしていること、宿泊を伴う旅行など、性的行為をしたと推認させるような証拠が必要ということになります。
それでは、次に、性的行為があった場合でも、不貞行為にあたるかどうかがわかりづらいものについて、解説していきます。
【風俗にいった場合】
まずは、風俗についてです。
みなさんの中には、風俗の利用は不貞にはならないと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、結論から申し上げますと、風俗の利用は、不貞行為にあたる可能性があります。
なぜなら、性的行為や性的類似行為を行っている可能性があるからです。
あくまで、性的行為があったかどうかが、不貞であるといえるかどうかの重要な判断基準であるということです。
【過去の不貞行為】
10年前の不貞行為などはどうでしょうか。
かつての不貞行為を理由としての離婚請求はできるのでしょうか。
これについては、事案ごとに異なるといえます。
すなわち、宥恕があったかどうかによって結論が異なってきます。
宥恕とは、他方の配偶者が相手方の不貞行為を知ったうえで、これを許したような場合をいいます。
宥恕があった場合には、離婚原因としての不貞行為にはならないと考えられています。
もっとも、宥恕があったといえるかどうかについは、慎重に考える必要があります。
また、性的関係を強要する、無理やり行うといった性犯罪の加害者となった場合にも、不貞行為はあったと認められることになります。
2.「悪意の遺棄」があったとき

【悪意の遺棄とは】
悪意の遺棄の「悪意」とは、「社会的・倫理的に非難されるべき心理状態、すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを容認する意思をいう」とされています。
次に、「遺棄」とは、「正当な理由のない同居拒否一般、ないしは同居・協力・扶助義務または婚姻費用分担義務の不履行一般を含む」とされています。
簡単に具体例をあげると、夫が妻を家から追い出したうえ、生活費を渡さない場合や、家事や育児を一切しない場合、病気や障害があるのに全く助けようとしない場合などが、悪意の遺棄に当たる可能性があるといえます。
とはいえ、ただ単に、相手方を追い出し、生活費を与えないというだけでは、悪意の遺棄に当たるとはいえません。
悪意の遺棄というためには、夫婦関係を破綻させる意思があったかどうかが問題となってきます。
また、同居を拒否するだけでは、悪の遺棄とはいえません。
悪意の遺棄というためには、同居を拒否する正当な理由がないことが必要となります。
当然ですが、夫婦間で離れて暮らすことが、夫婦の合意によるものであった場合にも、悪意の遺棄は認められません。
【悪意の遺棄が認められた例】
①夫が別居3か月前から生活費を一切渡さなかったほか、ガスや水道の元栓を鍵で閉鎖して使用不能にし、電気コードを切断するなどして、妻に別居を余儀なくさせた行為が、短期間であるとしても、悪意の遺棄として認定された事例(東京地裁平成17年11月29日)
②金銭的援助をするなど支えてくれた妻と生後間もない子を置いて家を出た夫に対し、夫婦関係の修復を図ることなく離婚調停を申し立て、養育費の支払いを滞らせて妻のもとに戻らなかったことが、悪意の遺棄として認定された事例(東京地裁平成21年4月27日)
などがあります。
一方で、悪意の遺棄が認められない例としては、正当な理由があればよいことから、DVやモラハラなどを避けるために 別居した場合や、実家の親の介護のために、やむを得ず別居した場合には、悪意の遺棄にはあたりません。
そのほか、専業主婦・主夫である一方が生活費を負担しない場合は、通常、専業主婦・主夫には、収入がないことから、扶助義務違反とはいえず、悪意の遺棄ということはできません。
また、正当な理由とは、性格の不一致があり、同棲することが困難であるために、別居するといったようなときにも認められます。
すなわち、悪意の遺棄として認定されるためのハードルは、とても高いといえるでしょう。
3.「3年以上の生死不明」について

3年以上の生死不明という離婚原因は、言葉のとおりです。
単純に、3年以上相手が行方不明であり、生きているか死んでいるかがわからない場合には、離婚することができます。
この場合の疑問としては、どうやって離婚すればよいのかということを思うのではないでしょうか
そこで、ここでは、どのように離婚すればよいのかを中心に解説していきます。
まず、通常、離婚をする際に、裁判を起こしたいと思うときには、その前に、「調停」という当事者同士で話し合う制度を使わなければいけません。
これを、調停前置主義というのですが、こういった仕組みについては、また別の機会に解説しようと思います。
ところが、3年以上の生死不明の場合、当然、相手方と話し合うことはできません。
そのため、生死不明の場合には、いきなり、離婚裁判をすることができます。
それでは、相手方の行方がわからないのに、どうやって、裁判の訴えをするのでしょうか。ここでは、公示送達という制度を使うことになります。
公示送達とは、裁判所の掲示板に必要事項を掲示することによって、相手方に、裁判をすることを伝えたことにするという仕組みのことです。
その際には、事前にいくつかの資料を準備する必要があります。
また、裁判においても、相手が本当に生死不明であることの証拠をいくつか提示する必要があります。
以上が、生死不明の場合の離婚裁判の大まかな流れになります。
生死不明の期間が7年以上の場合には、失踪宣告の申し立てをすることで、婚姻関係を解消するという方法もあります。
これは、相手を死亡したとみなすため、実質的に婚姻関係を解消することができます。
相手方がひょっこり現れた場合には、婚姻関係も復活してしまうことになるので、離婚したいと考えている場合には、通常、離婚裁判をすることになるでしょう。
4.その他婚姻を継続し難い重大な事由(DVやモラハラなど)

具体例としては、DVやモラハラ、性格の不一致、夫婦以外の親族関係、性的問題など多岐にわたる事情が挙げられます。
そこで、一例として、どのようなときに、この4号での離婚が認められるのかについて、具体例を示していきたいと思います。
(1)DVの場合
DVが離婚原因として認められるためには、DVの内容、具体的には、暴力や精神的虐待の内容についてはもちろん、そうしたDVに至った経緯についても詳しく主張する必要があります。
また、配偶者の暴力を受けて、どのような行動をとったかについても、詳しく主張することも必要になります。
その際には、DVを証明するための証拠として、診断書や暴言の録音、相手方からのメッセージなどが考えられます。
■DVにより婚姻が破綻していると認められた例
①夫が妻や長女に対して暴力を振るい、妻が長女を連れて別居したが、夫がそこから長女を連れ去り、夫と夫の両親が長女と面会することを禁じたうえで、夫は妻が長女と会いたがるのを利用して、妻の意思を無視して性的行為を強要したり、暴言を吐いたりしたという事案について、夫の妻に対する暴力及び精神的虐待を原因として婚姻関係は完全に破綻していると認めた事例(名古屋高裁金沢支部平成14年2月27日)
②妻は、夫が身勝手な行動をしており、家事や育児をしないことにストレスをためていった一方で、夫も妻が家事や育児を十分にしておらず、その態度が改まらないと感じ、ストレスをためており、両者は頻繁に喧嘩していた。そして、ある日、妻と夫が口論となったとき、夫がテーブルを持ち上げて妻の頭にめがけて振り下ろし、その際、頭をかばった妻の手にテーブルが当たり、これにより妻は、右中指・環指中節骨骨折の傷害を負ったという事案について、お互いが喧嘩を繰り返す中、夫が暴力行為により妻を骨折させたことは明らかに行き過ぎとして、婚姻関係の破綻が認められた事例。(東京高裁平成24年8月29日)
などがあります。
ここで、2個目の事例について、もう少し詳しく述べると、暴力を受けた場合であっても、夫婦げんかで双方が殴ったり蹴ったりしていた場合のように、夫婦のいずれにも原因があるということもあります。
このような場合には、暴力があったからといって直ちに離婚請求が認められるわけではなく、喧嘩に至る経緯、暴力の内容・程度、被害の程度などが重要な指針となります。
そのことを前提にすると、この2個目の事例は、テーブルを相手の頭に振り下ろすという、非常に危険な行為であり、社会常識的に考えても、明らかに行き過ぎた暴力であるといえます。
そのため、その暴力行為を行った側の当事者に、より重い婚姻関係破綻の責任を負わせているものといえます。
(2)暴言・モラハラ
暴言・モラハラが離婚原因として認められるには、相手方の言動が夫婦の日常生活や通常の夫婦喧嘩において受任すべき限度を超えているかが一つのポイントとなります。
例えば、夫が妻を知人に対して紹介する際に「風俗嬢だった時に店で知り合った」と虚偽を言いふらしたり、度重なる浪費をしていた事案については、受任すべき限度を超えていると認定した。
(3)性格の不一致
夫婦の性格の不一致による離婚が認められるためには、夫婦の性格の不一致が重大なものである必要があるといえます。
とはいえ、性格の不一致により婚姻関係が破綻していると認められる必要があるため、別居が数年続いているなどの、客観的に見ても懇意関係が破綻しているということが明らかであることが必要であるといえます。
すなわち、ただ単に「性格が合わない、よし、離婚だ!」という風に簡単に離婚請求ができるわけではありません。
有責配偶者(悪いことをした方)から離婚できる?
有責配偶者、つまり、悪いことをしたほうからの離婚請求が認められるのかについて、述べたいと思います。
例えば、不貞行為を行った側からの離婚請求が認められるかという問題です。
これについては、原則としては認められません。
しかし、例外として、①相当長期の別居期間があり②未成熟子(経済的に独立していない子)が存在せず③離婚した際に、相手方を過酷な状態に置くことがないと認められる場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあります。
もちろん、この3要件はあくまで目安であり、事案によって、認められる・認められないは変わっていくことになりますが、おおよその基準として、この3要件が認められるかによって、離婚請求が認められるかが判断されます。
離婚の問題でお悩みの方は西船橋ゴール法律事務所へ【初回30分相談無料】

千葉県船橋市の離婚弁護士 西船橋ゴール法律事務所はこれまで100件を超える多くの夫婦問題・離婚問題を解決に導いて参りました。
ご相談者様のお話をじっくり聞き、ご相談者様が最善の選択をできるようアドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。