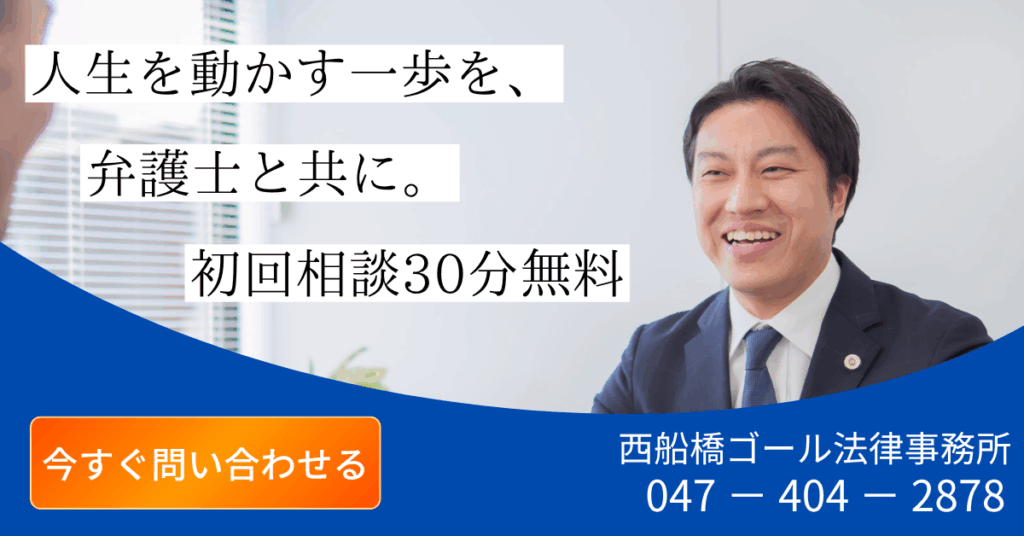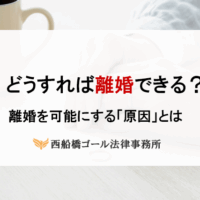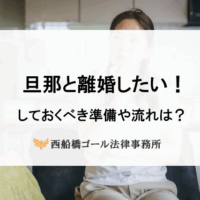みなさんは、離婚する際に財産分与や離婚慰謝料について考えると思いますが、離婚慰謝料を支払ってくれない、財産分与をしてくれないという場合には、どうしたらよいでしょうか?
今回は、離婚慰謝料や財産分与を確実に行ってもらうために、その準備として行うこと、保全処分について解説していきたいと思います。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業
平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業
平成26年3月 学習院大学法科大学院修了
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
目次
保全処分とは
保全処分とは、裁判所が暫定的に相手の財産を差し押さえたりする措置のことをいいます。
なぜこのような制度が必要かというと、調停や裁判の成立に、時間がかかってしまうことが背景にあります。
しかし、このような時間をかけている間に、こちらの生活ができなくなる・相手が財産を隠してしまう、使ってしまうなどといったことが起こる可能性があります。
そうした場合、財産を得ることができない、金銭が必要なときに得ることができないといった問題が生じることになります。

弁護士
このような事態を防ぐために、保全という手段を用いて、相手方の財産を事前に差し押さえることがあります。
離婚訴訟における保全処分とは
離婚訴訟における保全処分については、通常の民事保全処分と審判前の保全処分にわけられます。
民事保全処分となるケースは、一般調停事件と特殊調停事件の場合です。
審判前の保全処分となるケースは、別表第一事件(主に身分について争う事件)と別表第二事件(離婚や親子関係を前提にお金や扶養などを争う事件)の場合です。
離婚に関連して紛らわしいものとして、離婚の訴え(調停・訴訟)をすると同時に財産分与・離婚慰謝料請求をする場合には、通常の民事保全処分となります。
別表第二の事件のなかには、財産分与についての記載があるにもかかわらず、民事保全処分となるからです。

この際には、離婚調停の申立てが、本案の申立てとして扱われることになります。
保全に必要な条件
保全は、①保全する権利と②保全の必要性が要件となります。
そのうえで、この保全する権利が、ある程度確実に認められるものであることが必要となります。
婚姻費用の保全処分決定までの流れ
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が別居した場合に、一方が他方に対して支払う生活費のことです。
この婚姻費用は、収入の高い方から収入が低い方・ない方へと支払われるものとなります。
もちろん子供の有無も関係してきますが、通常子供は妻とともに別居あるいは、夫が妻と子供を置いて別居するという例が多いといえます。
(例)専業主婦である妻と子供を置いて、夫が家を出ていった場合
妻は専業主婦ですから、当然収入はなく、夫からの生活費が早急に必要となります。
しかし、夫の住所がわからない場合、どうやって請求すればよいでしょうか。
まずは、家庭裁判所に、婚姻費用の分担の審判を申し立てることになります。
調停の場合だと、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てる必要がありますが、審判であれば、夫婦のどちらかの住所地を管轄する裁判所に対して申し立てることができます。
この例だと、夫の住所地がわからないため、審判を申し立てることになります。
次に、保全の申し立てをします。
早急に婚姻費用を確保する必要性があるため、婚姻費用分担の審判の申立てと同時またはその後に、婚姻費用分担の審判を本案として、婚姻費用の仮払いの仮処分を申し立てます。
婚姻費用の保全処分申立ての要件
審判前の保全の申立てについては、家事事件手続法106条1項に「審判前の保全処分(前条第一項の審判及び同条第二項の審判に代わる裁判をいう。以下同じ。)の申立ては、その趣旨及び保全処分を求める事由を明らかにしなければならない。」と規定されており、さらに同法106条2項は、「審判前の保全処分の申立人は、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。」と規定されています。
保全処分を求める事由には、本案認容の蓋然性と保全の必要性を記載する必要があります。

弁護士
疎明とは、証明には至らなくても、裁判官に一応確からしいという心証を抱かせることをいいます。
審判前の保全処分の申立ての要件は以下のとおりです。
①本案が係属していること
婚姻費用分担の審判または調停を家庭裁判所に申し立てていることという意味です。同法157条1項が根拠規定です。
②本案認容の蓋然性
つまり、婚姻費用分担の請求が裁判所に認められるだろうといえることが必要となってきます。今回の場合だと、夫と妻の収入額・夫が妻に婚姻費用を払っていないこと・妻が子供と生活していることなどを主張し、それを疎明する資料を提出することになります。
③保全の必要性
保全が認められるためには、「強制執行を保全し、子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは~」(同法157条1項)と規定されているとおり、保全の必要性が求められています。
今回の場合だと、夫が婚姻費用を支払っていないため、妻と子の生活が困窮しているといえます。そこで、その困窮、つまるところ保全の必要性を疎明するために、妻の資産を示すために預金通帳を示したり、妻が働けない状態であることを示すために診断書や、育児記録等を提出する必要があります。
④ 申し立ての趣旨
保全処分の内容を示すことを意味しますが、この内容は、相当程度具体的に明示する必要があります。例えば「相手方は、申立人に対し、婚姻費用の分担として、令和〇年〇月から本案審判が効力を生ずるまでの間、毎月〇月限り、月額〇円を仮に支払え」などと記載する必要があります。
これらが、保全処分の申し立てに必要なことです。
婚姻費用の仮払いの仮処分の場合には、原則、相手方の言い分を聞く必要がある
婚姻費用の仮払いの仮処分の場合には、原則、相手方の言い分を聞く必要があります。(家事事件手続法107条)
聞き取りの方法は、裁判所の適正な裁量に委ねられていますが、実務上多くの場合、調停や審判の期日と同時あるいはその前に、裁判官と面接する期日を入れ、当事者双方から主張書面や疎明資料の提出を受けて審理が行われます。
保全処分は、審判で裁判所の判断が下されるまえに、相手から金銭を取り立てるものであるため、保全処分を乱用される場合、相手方の保護が十分にできないことが考えられます。
そこで、違法な保全処分によって相手方が被る可能性のある損害を担保するために、担保を立てさせることができます。(同法115条と民事保全法14条1項)
担保を立てさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられることになりますが、仮払いを受けないと生活を維持することができないことが保全の必要性で求められている以上、そもそも担保を立てるだけの資力がないといえます。
そうであるなら、担保を立てさせることは相当といえず、実務上も立てさせないようにするのが通常です。
婚姻費用の保全処分の効力
それでは、婚姻費用の仮払いの仮処分は、いつ効力を発揮するのでしょうか。
婚姻費用の仮払いの仮処分は、その緊急性及び暫定性から、審判を受けるものに告知することによって効力が生じ、審判が確定することで失効します。
※これは、審判が確定すれば、婚姻費用は審判の効力によって、支払われることになるからです。
この例のように夫の住所地が不明である場合には、保全処分については、就業先に送達することができます。
財産分与における保全処分決定までの流れ
財産分与と同時にする保全処分とは
財産分与と同時にする保全処分とは、離婚と同時に財産分与を請求する際に、相手が財産を隠したりすることを防ぐために行う保全処分のことです。
この手続きの場合だと、離婚調停の申立てと同時に財産分与を請求していることになります。
つまり、本案は離婚調停であり、財産分与の請求はそれに付随しているものにすぎません。
そのため、家事事件手続法別表第2の財産分与を請求する調停・審判ではなく、一般調停である離婚調停に付随して財産分与を請求しているにすぎないので、これまで述べてきたような審判前の保全処分ではなく、人事訴訟法上の保全処分を利用することになります(人事訴訟法30条)。
財産分与における保全処分申立ての流れと要件
まず、管轄は、離婚訴訟を提起する場合の管轄裁判所(夫もしくは妻の住所地を管轄する家庭裁判所)または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所となります。
簡単に言うと、夫婦どっちかの住所か、預貯金を差し押さえたいという場合には、その口座のある銀行の所在地を管轄する裁判所の申し立てるということになります。
次に、保全処分には、婚姻費用のところでも述べたように、申し立てをするうえでの要件がありますが、先ほどとは違うところもあるので、見ていきましょう。
① 本案係属の要否
これについては、本案である離婚訴訟が係属している必要はなく、離婚調停中であっても、離婚調停の申立て前であっても、いつでも申し立てをすることが可能です。
② 本案認容の蓋然性
離婚調停と同時に財産分与を行っている場合、本案である離婚が認容されるだろうといえることと財産分与を請求することができるだろうということが必要です。
そのため、離婚請求が認容されることについての疎明資料として、婚姻の経緯・離婚原因の存在についての資料、財産分与請求が認容されることについての疎明資料として、同居中に夫婦によって形成された財産の内容・財産形成についての寄与度(特別な寄与がある場合)についての資料を添付したうえで、申し立てる必要があります。
③ 保全の必要性
これも同様に必要です。具体的には、相手方が財産を処分しようとしていることや隠そうとしているなど、保全処分をしなければ、将来財産分与が認容されたときにこれを確保することができなくなるおそれがあるということを主張することになります。
✅ 仮差押えの目的物については、仮差押命令が暫定的かつ仮定的な命令であることから、なるべく相手方の被る損害が小さくなるようにする必要があります。例えば、預貯金と不動産が財産分与の対象となる場合に、預貯金を差し押さえる必要があるのかについては、慎重に判断されることになります。
✅ 申し立てをした後に、申立人に対する裁判官の面接により、申し立ての内容や疎明資料に不明な点がある場合には、補正が求められます。
✅ 保全命令を出す前には、担保をたてることを要求され、申立人が担保を立てたときに、保全命令が発せられることになります。
→この担保の金額は、財産分与については、離婚請求が認められた場合には、通常何らかの財産分与も認められることが多いため、一般の民事保全よりも低額になることが多く、申し立て債権額の1割程度の金額の担保でも認められているケースもあります。
なお、離婚後に財産分与を請求する場合の保全の手続きは、審判前の保全処分の申立てをすることになります。
なぜなら、この場合には、家事事件手続法別表第二の事件扱いとなり、本案が財産分与請求審判、あるいは財産分与調停になるからです。
そのため、要件としては、婚姻費用の際に書いたものと同様のものが求められますが、婚姻費用のように仮払いを求めるわけではないため、相手方を呼んでの面接などは必要ありません。
以上が、財産分与の際の仮差押えの保全の申し立てをする際の例となります。
保全処分についての対応を弁護士に依頼するメリット

保全処分の手続きを任せることができる
保全処分は、これまで述べてきたとおり、その要件が多く、じっさいにどのようなことを記載すればよいのか、また、どのような証拠を添付する必要があるのかなど、法律についての知識や経験がなければ利用するのが難しい手続きです。
そのため、専門家に依頼することで、保全の手続きを任せることが安心でしょう。
保全処分をすべきかについて相談できる
保全処分については、審判が確定する前に行うものであるという性質上、わざわざする必要はないのではないかと思う人もいるかもしれません。
しかし、保全手続きは自己の権利を守るために、必要性があれば可能な限り行うべきであると考えます。
そのため、保全手続きを行うか迷っている場合は、一度弁護士に相談し、メリットとデメリットを確認してみると良いでしょう。
まとめ
色々と細かな部分まで説明してしまいましたが、覚えておいていただきたいのは、相手に確実に財産分与をしてもらうため・または相手から緊急で生活費を支給してもらう必要があるときに取れる手段として、保全というものがあるということです。
とはいえ、保全については、それぞれの請求によって、例えば親権者指定についての請求や慰謝料請求についてなどによっても、必要となってくる資料であったり、申し立てるべき保全処分の種類が異なってきます。
離婚をする際に、相手方の行動について、何か不安に思うことがあるなどの事情があり、事前に何かできないのかと考えた場合には、離婚事件の知識が豊富な西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。
弁護士と話すことで、解決策が見つかるかもしれません。
離婚の問題でお悩みの方は西船橋ゴール法律事務所へ【初回30分相談無料】

千葉県船橋市の離婚弁護士 西船橋ゴール法律事務所はこれまで100件を超える多くの夫婦問題・離婚問題を解決に導いて参りました。
ご相談者様のお話をじっくり聞き、ご相談者様が最善の選択をできるようアドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。