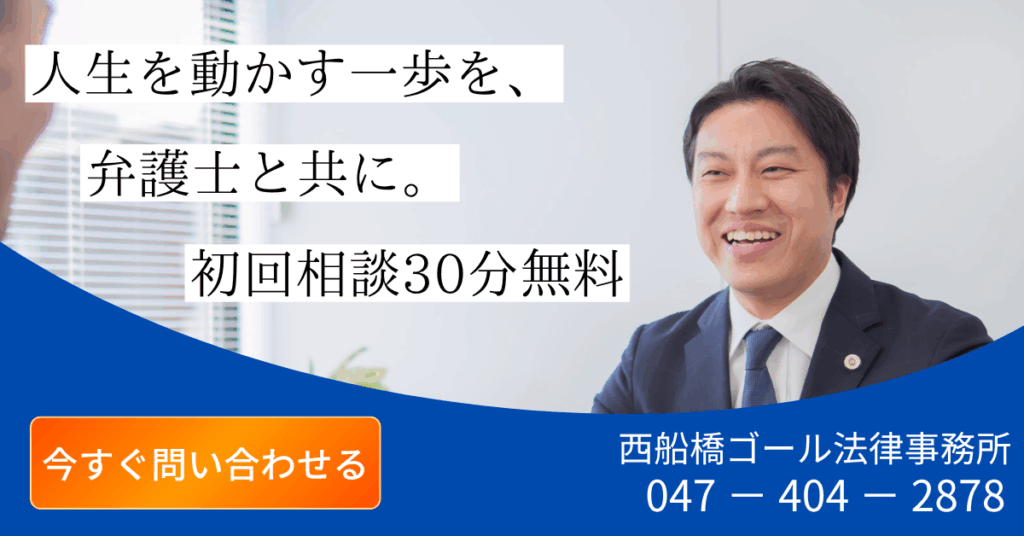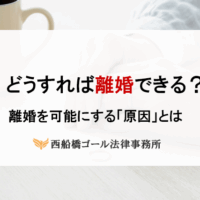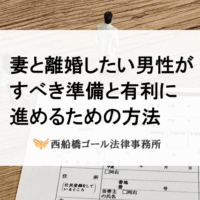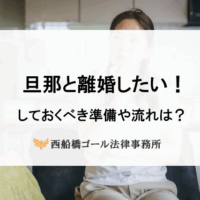平成28年3月 八千代松陰高等学校 卒業
令和2年3月 早稲田大学法学部 卒業
令和4年3月 早稲田大学大学院法務研究科 卒業
目次
公正証書とは何か
公正証書とは、行政機関によって作られるものであり、公文書です。
離婚における公正証書とは、お金や子どもなど離婚に関わる様々な条件について合意した内容を公文書にすることを言います。
公正証書については、法的拘束力が備わります。具体的に言うと、確定判決つまり裁判で出した判決と同じ効力を持つことになるので、相手が条件どおりの支払いをしないというときには、この公正証書を用いることで、相手に対して強制執行などをすることができるようになります。
公正証書の作り方・費用
公証役場というところに、夫婦二人で出向いて、公証人と面談を行ったうえで、作成することになります。
費用としては、おおむね3万円~5万円程度の費用がかかることになります。
ここで、注意が必要なのは、公証役場で公正証書を作る際に、具体的な文面や内容は自分たちで考えなくてはならないという点です。
つまり、夫婦で公証役場に行って、「自分たちのいう条件をもとに公正証書を作成してくれ」というかたちで作成するというわけではないことに、注意が必要です。

川口晴久
具体的にいうと、公正証書を作成するということは、自分たちで作った文書を公正証書化をするということなのです。
自分たちで条件などについて定めた文書を作成し、それを公証役場に持っていくことで、自分たちの作った文書を、公正証書にしてもらうということです。そのため、もともとの文章については、自分で作成しなければなりません。
公正証書の必要性
離婚をする際には、色々な条件を夫婦間で定めておかなければ、後々の紛争の種になってしまうことがあります。
そこで、紛争の蒸し返しを防ぐためには、離婚をする際に、夫婦で定めた条件について、書面に残しておく必要があります。
しかし、ただ書面に残すだけでは、法的拘束力がない、つまり、相手にいうことを聞かせられない書面になってしまいます。
そこで、相手が条件を守らない場合に、強制的に条件を守らせるために、公正証書を作成しておくことが必要になります。
公正証書ではどのような条件を定めるのか
文章の一例を示す前に、そもそも、どういった条件について、文章を作成すればよいのか、何についての条件を定めればよいのかということについて、疑問を持つ方もいるかもしれません。
公正証書と離婚協議書は、その内容において違いはほとんどありません。
離婚時に定めておくべき条件として、以下のようなものが挙げられます。
①親権者をどちらにするか
②財産分与をどうするか
③慰謝料をどうするか
④年金分割をどうするか
⑤養育費をどうするか
⑥面会交流をどうするか
それぞれ解説していきます。
親権者の指定
親権者の指定は、必ず行う必要があります。
離婚届には、親権者をどちらにするのか記載する箇所があり、その記載がなければ、離婚届は受理されないからです。
そのため、協議離婚をする際には、どちらが子供の親権者となるのかを決めておく必要があります。
親権者については、調停や裁判で決める場合には、これまで子供を世話していた監護権者、一般的には、母親の方に親権がいく傾向にありますが、協議離婚においては、お互いの合意によって親権者をどちらにするのか定めることができます。
財産分与
離婚をする際に、財産分与の条件を定めておくことは、非常に重要です。
なぜなら、民法768条1項には、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定しており、どちらにせよ、財産分与をすることが決まっているからです。通常、調停・審判、裁判離婚の場合には、2分の1ルールという、財産分与の際には夫婦それぞれで半分ずつ分けるというルールのもと、折半されることになります。
しかし、協議離婚では、そのようなルールはありません。そのため、夫婦間で合意がなされるのであれば、どのような割合による分割も認められることになります。これは、協議離婚のメリットとも言えます。
慰謝料
慰謝料についても、協議離婚をする際には、考えるべき重要なことの一つです。
なぜなら、通常、離婚するときには、何らかの原因があります。
その原因が性格の不一致などであれば、夫婦双方に原因があったといえ、慰謝料は請求できないといえますが、相手方の不貞やDV、モラハラなどがある場合のように、相手方に離婚原因があったといえる時には、離婚慰謝料を請求することができます。
この離婚慰謝料については、例えば不貞の場合ですと、おおよそ裁判所で認定される慰謝料は50万円~300万円の間になりますが、協議離婚では、そのような相場と関係なく夫婦が合意した場合には、自由に慰謝料額も認定することができます。
そのため、協議離婚において離婚慰謝料を減額または増額したい場合には、夫婦でそれぞれ妥協できる点・できない点についてすり合わせを行いながら、両者が納得のいく結論を目指すことができます。
年金分割
年金分割についても、夫婦で合意をしておくことは必要ですが、他のものとくらべると、その優先度は低いです。
なぜなら、年金分割とは、夫婦の合意によって、請求すべき按分割合を定めるものですが、基本的に按分割合は0.5となります。
これは、調停・審判や裁判で離婚をする場合も同様です。また、仮に合意をしていなくても、3号分割といって、会社員の夫・妻をもつ専業主婦・主夫である場合には、単独で年金分割の申請をすることができ、その場合にも按分割合は、0.5となるからです。
つまり、年金分割については、その按分割合について話し合うことはないと言えます。
ただ一つ注意すべき点は、年金分割は、離婚をした日の翌日から2年以内に申請しなければ、その請求権を失うことになりますので、その点にだけは注意すべきです。
もしも、年金分割について、より詳しく知りたいことがあれば、年金分割についてのコラムがあるため、そちらを見ていただくとよいと思います。
養育費について
離婚する際に、子供がいるときには、親権者の指定とともに、養育費についても定めておく必要があります。
養育費とは、親権者となり、子供の面倒を見ていく相手方に対してい払う必要の費用のことです。
これについて、調停・審判、裁判で判断を求める際には、原則として、算定表に従って、額を算出することになり、ある程度金額が定められています。もっとも、協議離婚の場合には、お互いの合意によって、相場より多額のあるいは低額の養育費にすることもできます。
面会交流について
協議によって、親権者と認定されなかった場合でも、面会交流といって、子供と会うことを求めることはできます。
この面会交流については、調停や裁判でも申し立て求めることはできますが、後々の争いをなるべく防ぐためにも、できる限り協議の段階で定めておくことがよいでしょう。
その際には、頻度や面会交流の方法など、条件について、詳しく定める必要があります。
公正証書の文章例
1 離婚の合意
条件ではないですが、大前提として、離婚することについて、お互い決めている場合には、この離婚の合意について、文章として残しておくのがよいでしょう。
例 甲と乙は、甲と乙の婚姻の解消に関する件について、次のとおり合意する。
甲及び乙は、本日、協議離婚することを合意する。
といった内容になります。この甲と乙の部分に、夫婦それぞれの名前をいれていくことになります。
2 親権者の指定
例 甲及び乙は、当事者間の未成年の子丙(令和〇年〇月〇日生)の親権者を乙と定める。
といった内容になります。
3 財産分与
例 甲は、乙に対し、財産分与として〇〇万円を、令和〇年〇月末日限り、乙名義の〇銀行〇支店の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
といった内容になります。
4 慰謝料
例 甲は、乙に対し、離婚に伴う慰謝料として、金〇〇万円の支払義務があることを認め、これを〇年〇月末日限り、乙名義の〇〇銀行〇〇支店普通預金口座(番号〇〇)に振り込む方法により支払う。なお、振り込み手数料は乙の負担とする。
5 年金分割
例 甲と乙は、甲乙間の婚姻解消について、本日、以下のとおり合意した。
甲と乙は、本日、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険法第78条の2第1項第1号に基づき、対象機関に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。
といった内容となります。
6 養育費
例 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満20歳に達する日の属する月までの間、月額〇万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日限り、乙の指定する下記記載の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
といった内容になります。
7 面会交流
例 乙は、甲に対し、甲が未成年者と面会交流することを認め、その具体的な時間、場所、方法等については、子の利益を最優先に考慮し、当事者間で協議して定める。
といった内容になります。
以上が、各条件についての、一番基本的な書き方になります。意外と難しいと感じた方もいるのではないでしょうか。とはいえ、これはあくまで、基本的な例であり、もっといろいろな条件を付け加えることになると、その内容もより複雑になっていきます。
公正証書作成のメリットとデメリット
メリット
公正証書を作成することのメリットは、離婚協議書と違って、法的拘束力を持つことができるようになるということです。
つまり、相手方が条件を守らない場合には、この公正証書をもとに、裁判所による強制執行を行うことができるようになります。
確定判決と同様の効力をもつので、その法的拘束力は、相当強いものといえるでしょう。
デメリット
公正証書を作成することのデメリットは、数万円程度の費用がかかってしまうことと、一度作ってしまったら、その内容が法的拘束力を持ってしまうことです。
これはつまり、不利な条件での公正証書を作成した場合には、それに従わざるを得なくなってしまうということです。
弁護士が公正証書を作成するメリット

弁護士が公正証書を作成するメリットは、弁護士が条件をチェックしたうえで、最大限ご依頼者様に対して有利になるような条件で作成することができるという点です。
不利になりそうな点があれば指摘し、訂正を行います。
また、相手方が提示する条件が、本当に良い条件なのかという点についても精査することができます。
もしも、離婚をする際に、公正証書を作成しようと思っているが、その内容について迷っている、そもそもどうやって作成したらよいかわからないという方がいれば、西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。
離婚の問題でお悩みの方は西船橋ゴール法律事務所へ【初回30分相談無料】

千葉県船橋市の離婚弁護士 西船橋ゴール法律事務所はこれまで100件を超える多くの夫婦問題・離婚問題を解決に導いて参りました。
ご相談者様のお話をじっくり聞き、ご相談者様が最善の選択をできるようアドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。