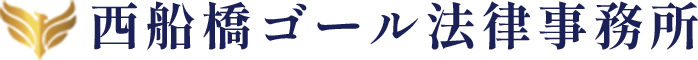警察署で書いた上申書は撤回できる?思わず余罪を認めてしまった場合は?

目次
取調べで最初に作成する「上申書」とは
逮捕直後や最初の取調べの際に、警察官が、被疑者に対し、罪を認める内容の書面を書かせることがあります。これを「上申書」と呼びます。タイトルは、「上申書」に限らず「私がやったこと」や、「今日の出来事」など様々です。
この「上申書」は、供述調書と異なり、被疑者がペンを持たされ、自分の手で書くことが多いです。
書く内容は、ほとんどのケースで、警察官が記載内容を口頭で指示し、被疑者がそれに従って記入しています。
しかし、はじめて受けた取調べで混乱してしまい、認める必要のないことまで認めてしまったり、時には余罪もたくさんあるかのように書かされてしまった・・・ということがよくあります。あるいは、罪を否定していたはずなのに、いつの間にか、認める内容の作文になってしまっていた・・・ということまであります。

赤井耕多
認めないとより不利益になってしまうではないか、家に帰してくれなくなるのでは?・・・と思い混乱して、ついつい不利な内容を書いてしまうケースが少なくありません。
この上申書も、証拠書類の一つです。後の手続に影響してしまうことがあります。
上申書の効力
警察・検察がその後の取調べで利用
・その後の取り調べで、罪を否定したときに「あのとき(上申書で)認めたよね?」「いまはなぜ否定しているのか?」と、変遷を指摘する材料になる。
・余罪を追及する材料になる
裁判の証拠として
・自ら作成した供述書として、裁判の証拠になり得る(刑事訴訟法322条1項)。
しかし、逮捕後や、突然の取調べ後に、いわば混乱した状態で、最初に作成したものという位置づけです。
まだ警察に十分な詳細を話す(その後の2回目,3回目の取調べよりも)前に作成していることが多いということです。
そのため、内容の具体性を欠くケースが散見され、プロの目から見れば、内容の正確性の根拠に乏しいことも多々あります。
そのため、上記の効力をもってしても、捜査機関にとって万能な書面ではありません。

川口晴久
実は、裁判でも、決定打に使うには、上申書はやや弱いという側面があります。間違った内容を認めて作成してしまっても、まだ諦める必要はありません。
弁護士がついていれば、やり直しが可能です。
次回の取調べできちんと訂正することが重要です。
間違った内容を後で訂正・撤回させてもらえる?(起訴前)
では、次の取調べのときに、警察官に対し「この前の書面、間違っていたので、間違っていた部分を消してください」「書き直しをさせてください」などと言ったら、応じてもらえるでしょうか?
これについては、ほとんどの場合、警察官は応じません。一度作成した書面について、日をまたいでから、その書面に書き加えをすることは、ほとんどないのです。したがって、あくまで、最初に作成した上申書は、そのまま警察署で保管されます。
では、どうすればいいでしょうか。
以下の方法で、間違った上申書の効力を打ち消し、あるいは減少させることが考えられます。
正しい内容で弁護士に書面作成してもらう方法
間違った上申書を作成されてしまった後でも、弁護士が、正しい事実関係を聴取し、書面化することができます。
弁護士は、この書面を、公証役場等で、確定日付(その日に存在していたことが公証される)入りで保管します。こうすることで、間違いが直ちに弁護士へ報告されたことを日付入りで証拠化できます。間違った上申書の直後に、正しい書面が別で存在していれば、すぐにいい直したという証拠を残すことができます。
そして、タイミングを見ながら、警察や検察官に、その内容を示すか、存在を示し、こちらに有利な証拠があることを知らせることができます。また、弁護士から警察へ、改めて、正しい内容の取り調べをしてほしいと申し入れることもできます。
新たに正しい調書を作成してもらう 方法
第2に、次回の取調べで、きちんと事件内容の説明をし、新たに、詳細な供述調書を作成してもらうことが考えられます。
はじめての取調べでは、一方的に、「お前がやったのだろう」と強い言葉をいわれ、記憶をきちんと整理できないまま慌てて作成してしまうというケースもあるので、記憶をきちんと整理してから、落ち着いて言い直すことが重要です。
警察官は、検察官に事件を送致するまでの間に、同一の事件について、何通か調書を作成することがあります。なので、上申書1枚のみで調書作成が終わることはあまりなく、むしろ、2回目以降の取調べで、詳細な供述調書を作成することが多いです。 つまり、まだチャンスはあるということです。
もっとも、新たに真実を述べて作成してもらった調書に、サイン(被疑者の署名押印)をしてよいかは、今後の処分見込みを踏まえ慎重に検討する必要があるので、専門家である弁護士に相談することが望ましいです。

赤井耕多
最初の供述よりも、新たな供述の方が正しい理由を、警察(や検事・裁判官)に信じてもらうには、どんな事情を伝えればよいか、弁護士に相談できます。また、異なる供述をしたことでかえって疑われてしまうことのないように、その話をすべきか否かを相談できます。
実務上よく見られるケースは、被疑者の方から見れば、自分の言ったことを適切に書いてもらったと思える書面でも、弁護士の目から見ると、重要部分が記憶に基づかず捜査機関の思い込みに基づく表現となっていたり、不利な内容にになっていたりするケースです。
実は、供述調書にサインをするか否かは、被疑者が自由に選択できます。
参照:刑事訴訟法 第198条5項 「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」
この条文から、2つのことが言えます。
①調書にサインをした場合は、調書内容につき間違いないと認めたことになる。
②被疑者は、調書にサインをする義務はなく、拒否することができる。
このように、供述調書にサインをすべきかは、重要な選択です。サインをすべきか弁護士が相談された場合、今後の見通しを踏まえて、アドバイスします。具体的には、現在の捜査状況、証拠状況、示談の進行具合も見ながら、経験に基づいた最適な選択を案内します。一般の方には初めての経験であることが多く、判断が難しいことなので、刑事事件を取り扱う弁護士に相談するのが良いでしょう。
上申書や調書にサインをしないと、取調べが終わらない?
よく寄せられる疑問として、警察官の作った調書どおりにサインしないと、家に帰れず延々と取調べが続くのでは?というご相談があります。
確かに、すんなりサインをするケースと比べ、サインをしない方が、サインしない理由を尋ねられ、場合によってはサインするよう説得されるなど、応答に時間を要します。その分取調べ時間が長引きますが、終わりがないわけではありません。警察官は、サインをするまでいつまでも取調べを行うかのような姿勢を見せます。
しかし、現実的に、警察官は、他にも何件もの対応すべき事案に追われています。また、取調べは、都度、「取調べ状況報告書」という用紙で、取調べ時間を記録しています。そのため、休憩を設けず不当に長時間の取調べを行った場合、それが取調べ状況報告書により形に残ってしまいます。休憩がない、深夜まで行われたなどの過酷な環境下で 行われた自白については、証拠とできないことが法律上定められています。
参照:刑事訴訟法 第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
そのため、取調べ方法のルールが定められています。
原則として、①1日8時間までとすること ②午前5時から午後10時までの時間に行うこと(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/keiki/keiki20080403.pdf)がルールとなっています
(ただし、深夜に事件が起きて逮捕したケースなどは例外です)。
このように、取調べには必ず終わりがあるので、持久戦にも限界があります。
余罪について
余罪についても、「過去に何件かやりました」と言ってしまったら?
はじめての刑事事件で、慌てているとき、混乱しているときに、余罪がたくさんあるかのような供述をしてしまったというお声をよく耳にします。警察官の態度がこわかったので、これもやった、あれも自分がやったと、認めることで迎合する方が、その場をおさめるうえで有効だとの心理状態に陥ってしまうことがあるのです。
本件以外で、過去の余罪についても「自分がやりました」と認める調書が作成されたとします。あるいは、携帯電話などの電子機器類の中に、余罪に関するデータがあったとします。
プロ以外の方からすれば、その状況では余罪も含めて罰せられてしまうとお思いになるかもしれません。
しかし、余罪の日時場所、被害のお相手がだれであるかなど、詳細
時には記憶違いで誤った余罪を話していたり、証拠が十分にそろわないことがあります。
自分から進んで余罪を話すことは、反省のうえでは重要なものの、本当にその記憶は正確か?という問題があります。

川口晴久
警察介入よりも何週間、何か月か前の出来事(余罪)について、供述をすべきかは、専門的判断が必要です。自分が正しいと思っていても、実は誤った記憶であることがよくあるからです。弁護士とともに記憶を整理してから供述をすることをお勧めしています。そうすることで、誤った起訴や、誤った重罪化を防止できます。
余罪の発言についても撤回・修正できる?
余罪については、間違った供述がされることがままあります。
そのため、「先日お話した余罪部分は、○○の部分が記憶違いでした」とお伝えすることも可能なケースがあります。きちんと理由も付して供述することが必要です。

赤井耕多
被害者から違約金を付けるよう提案された場合、加害者の方で、受け入れる方と受け入れない方が半々くらいという印象を受けます。
例えば、第5条として、「乙(加害者)は、甲(被害者)に対して、直接・間接を問わず、一切接触しないことを確約する」などといった記載をします。また、違約金条項を付する場合には、「乙(加害者)は、前項の規定に違反した場合、甲(被害者)に対して、違約金として、金●●万円を支払うこととする。」などといった規定が考えられます。
口件及び本件和解内容・経緯について、一切口外しないことを誓約する」などといった条項が考えられます。
裁判で使用されてしまうの? (起訴後)
「時間がないから早くサインをしてくれ」といわれ、内容をきちんと確認できないまま調書にサインをしてしまったというケースもよくあります。
その調書が、裁判で証拠として提出されることがあります。
参照:刑事訴訟法 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

赤井耕多
この条文を根拠に、自白調書は、原則として裁判上の証拠となるのです。
しかし、裁判においても、言い直しは可能です。
調書ではそのように書いたが、記憶を整理し直すと、正確には○○であったと裁判で言い直した場合、その○○の方が具体的で裏付けのあるものならば、言い直しの内容の方が信用されることがあります。
裁判上の発言を信用してもらうには、きちんと打合せを行う必要があります。
最後に
以上が、上申書や調書の効果、修正方法です。
誤りのない調書が作成されるよう、訂正を求めたり、あるいはサインを拒否するなど、誤った調書の作成を予防できることが一番です。そのために、弊所では、取調べ前のアドバイスや、場合によっては弁護士が取調べ日に同行することもしています。刑事事件で警察からの呼び出しを受けた方は、必ず検討すべきでしょう。
そして、もし、記憶と異なる調書が作成されてしまっても、諦めることなく、直ちに弁護士に相談してください。

川口晴久
どうなってしまうか不安な日々を過ごすよりも、まずはお気軽に相談してください。

法政大学法学部卒業
学習院大学法科大学院修了
アトム法律事務所
アトム市川船橋法律事務所
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
所属:千葉県弁護士会