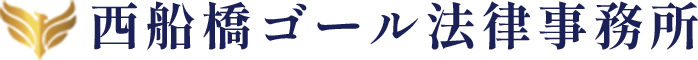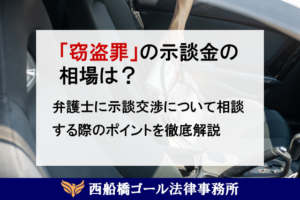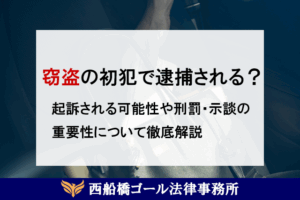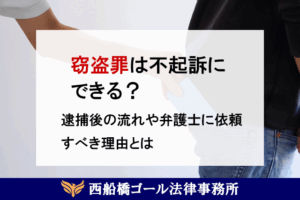万引きしたらどうなるの? 被害届や逮捕される?処分はどうなる?
万引き・窃盗
万引きをした後、どうなるのか不安になる方は多いと思います。
このコラムでは、万引きがばれてしまった方やそのご家族に向けて、万引きに関する知識を解説していきます。

平成28年3月 八千代松陰高等学校 卒業
令和2年3月 早稲田大学法学部 卒業
令和4年3月 早稲田大学大学院法務研究科 卒業
この記事でわかること
✅ 万引きをしたら被害届が出されるのか
✅ 万引きで逮捕されることはあるのか
✅ どのような刑事処分が下されるのか
目次
万引きをしたらどうなる?被害届が出されるのか
そもそも、万引きをした場合には、どのように警察は認知するのでしょうか。
通常、万引きの事実が発覚した場合には、被害届が出されます。
そして、警察官は、その被害届を受理し、捜査をしていくことになります。
つまり、被害届が店から出されると、基本的には捜査され、場合によっては、逮捕されることもあるといえます。
しかし、一方で、そもそも被害届が出されない場合もあります。
皆さんも、お店側との話し合いや被害を弁償することで、警察への連絡をやめてもらう、あるいは、お店の責任者が許しているような場面を見たことがあるのではないでしょうか。
具体的な例として、以下のような場合には、そもそも被害届が出されないことが多いです。
被害額が少ない場合
例えば、駄菓子など数十円~数百円程度の金額のものを万引きした場合など、被害額が少額のときには、被害届が出されない場合があります。
とはいえ、店ごとに対応は異なるため、一概に少額だからといって、被害届がだされないということではありません。
加害者が若年や高齢の場合
加害者が未成年であること、あるいは、非常に高齢である場合には、店の判断によっては、被害届が出されない場合があります。
これは、警察への連絡より、更生を促すために保護者へ連絡するとか、あるいは、支援団体等に連絡すべきだと判断されたときです。
初犯であり、弁償・謝罪した場合
単純に、初めて万引きし、捕まった後、すぐに弁償したうえで、謝罪することで、店側が厳重注意で済ませることもあります。
このような場合のほか、ほかにもいくつかの理由で、そもそも被害届が出ない場合はあります。

弁護士
被害届がない場合には、基本的に、警察はわざわざ捜査をしませんので、逮捕されることはまずないでしょう。
現行犯の場合は?
また、現行犯の場合はどうでしょうか。
つまり、お店の店員が万引き犯を発見し、警察に通報などした場合です。
この場合でも、先ほど述べたように、被害額が少額などの事情があれば、警察としても、厳重注意程度ですませるよう店に述べたり、あるいは、店側から、被害届までは出さないといったような方針を取ることが考えられます。
結論を申しますと、被害届をだすかどうかは、店の判断基準によって異なります。
場合によっては、出されないこともあるといえます。
そして、被害届が出されない場合には、そもそも、注意を受けるくらいで終わることがほとんどですが、被害届を出された場合には、逮捕されるおそれがでてくるといえます。
万引きで被害届を出されたら逮捕される?
それでは、被害届が出された場合、万引きで逮捕されるのでしょうか。
万引きは、刑法上、窃盗罪として扱わるため、逮捕される可能性も当然あります。
そこで、逮捕の可能性がどれくらいあるのか、また、逮捕の可能性を上げる要因としては、なにが考えられるのかについて、解説していきます
万引きで逮捕の可能性に影響する要素
万引きで逮捕される可能性に影響するポイントとして、重要な要素としては4つあります。
万引きでの逮捕に影響する要素
- ・万引きの回数
- ・被害金額
- ・犯行態様
- ・反省や被害弁償をしているか
一つ目は、回数です。
単純に、初犯の場合には、逮捕される可能性は低いですが、2回、3回と繰り返していく、前科があると、逮捕される可能性は上がっていきます。
二つ目は、被害の金額です。
これも単純に、被害額が数百円程度であれば、逮捕される可能性は低いですが、数万円程度になると、被害額が高額とみなされ、逮捕される可能性が上がります。
三つ目は、犯行態様です。
例えば、現行犯で捕まった際に、逃げたりせず、反抗をしなければ、逃亡のおそれがないとして、逮捕される可能性は低くなるでしょう。
反対に、万引きがばれた際に、捕まらないように、逃げた場合には、逃亡のおそれがあるとして、逮捕される可能性が高くなると考えられます。
四つ目は、反省しているか、被害弁償をしているかなどの、情状です。
万引きをした後に、謝罪の言葉を述べたり、弁償することができた場合には、逮捕される可能性は低くなるでしょう。反対に、反省の態度がうかがえず、弁償もしていない場合には、逮捕される可能性が高くなるといえます。
逮捕はどのような時にされる?
ここで、そもそも、逮捕とは、どういうときにされるのか、みなさまご存じでしょうか。
現行犯での逮捕をのぞき、①住居不定②罪証隠滅のおそれがあること③逃亡のおそれがあることのどれかが認められなければ、逮捕はされないのです。
つまり、逮捕されたくなければ、万引きの場合には、②、③の危険性がないことを示すことができればよいといえます。
そのことを考えると、上記の行動によって、逮捕の可能性が上がったり、下がったりする理由もなんとなくわかっていただけるのではないでしょうか。
万引きが事件化したら、刑事処分はどうなるの?

弁護士
逮捕されたとしても、また、逮捕されなかったとしても、それで終わりというわけではありません。
通常、処分としては、起訴前の段階だと、微罪処分、不起訴処分が考えられます。
そして、起訴された場合には、略式判決、有罪、執行猶予、無罪の処分が考えられます。
それでは、どういった場合に、どの処分になるのかについて、のべていきます。
微罪処分になる場合
まず、無罪判決を除いた、最も軽い処分として、微罪処分があげられます。
微罪処分とは、警察に逮捕され、警察署には連れていかれるが、そこで、厳重注意を受けただけで、釈放される処分のことをいいます。
この微罪処分は、警察官の裁量によって決まり、明確な判断基準はありませんが、犯罪捜査規範の198条には「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。」とされています。
つまり、「送致しないことができる」という文言から、大前提として、かならず微罪処分になるというわけではありません。
また、微罪処分となるのは、「犯罪事実が極めて軽微」である必要があります。
【微罪処分となるには初犯である必要がある】
以上をふまえて、万引きの事案で、微罪処分となるのは、どのような場合かというと、まず、初犯である必要があります。
この初犯というのは、前科・前歴がないという意味です。この前歴には、不起訴処分となった場合や微罪処分があった場合も含まれます。
微罪処分は、何度も受けられる処分ではないということに注意しましょう。
被害額が小さいというのも、必要な要素です。
おおよその目安としては、数百円程度のものが限界だと考えられます。千円を超えると、微罪処分とすることは難しいでしょう。
また、犯行態様が悪質であったり、反省の色がうかがえないといったことも、微罪処分を得るうえでは、問題となります。
謝罪がされているうえで、弁償もされている場合に、微罪処分となるといえます。
不起訴処分になる場合
次に軽いのが、不起訴処分です。
これは、犯罪をしたという証拠が十分でないため、起訴できないという【嫌疑不十分】と、犯罪をしたことは認められるが、色々な事情を総合して、起訴する必要はないとする【起訴猶予】の二つがあります。
もっぱら、ここでの不起訴処分は、この、起訴猶予のことだと考えてください。
不起訴処分の場合には、前科がつくことはなく、裁判所に行くなどをする必要はなくなります。
それでは、不起訴処分となる場合は、どのような場合でしょうか。
これも、これまでと同様に考えてください。
例えば、すでに微罪処分を受けている場合に、もう一度、同じような万引きをしてしまった場合などには、不起訴処分となることが考えられます。
また、初犯であっても、被害額が大きいなどの理由で、微罪処分にはならない程度の万引きでも、被害弁償をしっかり行い、示談をしたうえで、反省している場合などには、不起訴処分となることもあるでしょう。
このように、通常、このようなことをすれば、反省しているな、被害は回復したなと思われるような行動をすることが重要です。
略式判決が出る場合
次に、起訴された場合について、述べていきます。
起訴された場合に、罰金のみであれば、略式起訴というかたちで、起訴されることになります。
略式起訴とは、罰金刑の場合になされるもので、書面審査だけで判決が下されます。
そのため、逮捕された本人が、直接裁判所に出向く必要などはありません。
とはいえ、前科はつくことになります。
もっとも、罰金を払うだけですみ、懲役刑となることはないため、比較的軽い処分であるといえるでしょう。
およそ、3回目の万引きの場合には、この略式起訴となるケースが多いといえます。
つまり、万引きの場合には、段階を踏んでいくことになります。
まずは、微罪処分、次に、不起訴処分、その次には、略式判決、つまり罰金といった具合でしょうか。

弁護士
万引きの被害額によっては、初回から、略式起訴となるケースもあります。
有罪判決(執行猶予)となる場合
起訴されたうえで、懲役刑となる場合には、裁判所で、公判が開かれます。
そして、裁判官から、判決を受けることになります。
これが、万引きの有罪判決で、最も重い処分といえるでしょう。
万引きにおいて、有罪判決となるのは、複数回万引きを繰り返した常習犯の場合や、被害額が大きな場合だといえます。
とはいえ、まずは、執行猶予が付く場合が多いといえます。
とはいえ、常習犯の場合には、執行猶予中にも、再度万引きをしてしまうことがあります。
その時には、再度の執行猶予が認められるかというのが問題となるのですが、それについては、後述させていただきます。
無罪判決となる場合
これは、本人が万引きしていないにもかかわらず、万引き犯とされた場合、または、本人が万引きしていないと最初から犯行事実を認めず、それを立証するだけの十分な証拠がなかった場合に行われる処分です。
字面どおり、無罪であるのだから、そもそも犯罪をしていないことが認められることになります。
そのため、処分といえるかはなんともいえませんが、最も軽い処分といえるでしょう。
✅ 無罪判決を得た場合には、逮捕・勾留されていた時には、その期間について、補償金を求めることができます。
以上が、万引きをした場合に考えられる処分です。
万引きの常習犯の場合はどうなるの?
それでは、万引きの常習犯の場合には、どのような処分になるでしょうか。
通常、万引きというのは、常習性が認められ、場合によっては、執行猶予判決をもらっても、その執行猶予期間中に再度、万引きしてしまうことがあります。
このような場合、再度の執行猶予が認められるのかという問題があります。
【再度の執行猶予とは】
再度の執行猶予とは、執行猶予中に犯罪をしてしまったときに、もう一度、執行猶予付きの判決を得ることをいいます。
具体的には、刑法25条の2項に「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定されています。
ここで、重要なのは、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という文言です。
【クレプトマニアである場合】
この万引きの常習性のことを、クレプトマニアといいます。
そして、クレプトマニア、つまり、窃盗症を直す手助けをしている榎本クリニックという医療法人が存在します。
例えば、このような、医療法人の助けを借りて、症状を改善しようとして、通院などを行っていること、または、その成果を何らかの形、診断書等で示すことなどが、情状に特に酌量すべきものとしてあげられるでしょう。
単純にいってしまえば、刑務所に入れるより、社会生活の中のほうが、更生を目指せますよという事情が必要だということです。
こういった事情に加え、反省、被害弁償等がされていれば、再度の執行猶予の判決になることも十分に考えられます。
万引きで、有罪判決を受けた場合、量刑はどうなるの?
それでは、最後に、万引きで有罪判決を受けた場合の量刑について、おおよその相場を解説していきます。
懲役刑になる場合
まず、万引きで、懲役刑になるケースの場合は、何より回数が重視されているといえます。
例えば、被害額が数百円でも、前科がある場合には、執行猶予付きの懲役刑の判決が出ることがあります。
また、複数回の前科がある場合には、被害額が数百円でも、執行猶予のつかない懲役刑の判決も出ることがあります。
逆にいえば、初犯で、懲役刑の判決が出る場合は、限られており、被害額が数万円から数十万円の場合には、初犯でも懲役刑の判決が出ることもありますが、その場合でも、執行猶予付きの判決となることがほとんどです。
つまり、これまで述べたように、回数と被害額が重視されます。
求刑の相場としては、まちまちなことから、これだという断定はできませんが、おおよそ、10か月から1年6か月が基本的な量刑となっており、それに執行猶予期間が3年つくというのが多いといえます。
罰金刑になる場合
通常、窃盗罪で罰金刑のみの場合でも、最低20万円は支払うことになり、おおよそ、20万円~30万円となります。
ここで、ポイントなのが、被害額の大小はあまり関係なく、罰金刑の場合は、一律に最低20万円となっていることです。
つまり、数百円のものを万引きしたというだけでも、20万円の罰金を支払わなければならない場合もあるということです。
このような罰金について、払えない場合には、未決勾留期間を満つるまで参算入というかたちで、罰金を支払うこともあります。
これは、刑事施設に、判決が出るまでの間、逮捕・勾留されていた場合には、その日数を1日5000円換算で計算し、罰金を減らすという仕組みです。つまり、20万円だと、40日間勾留されていた場合には、罰金がゼロ円になります。
万引きがバレてしまったら弁護士に相談しよう
万引きは、数百円のものを盗んだとしても、多くの金銭を最終的には支払うことになりかねない犯罪です。
たかが万引きだと思っている人がいる場合には、その認識をあらため、万引きはれっきとした犯罪であるということを再認識したほうがよいでしょう。
一方で、万引きをしてしまった場合には、弁護士がつくことで、不起訴処分や微罪処分等の有利な処分を得ることのできる可能性が高くなります。
そのため、万引きをしてしまった場合には、窃盗事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
万引き事件を起こしてしまってお困りの方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所までご相談ください。
【参考ページ】