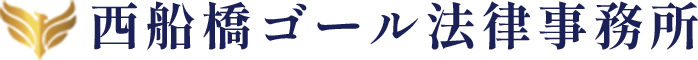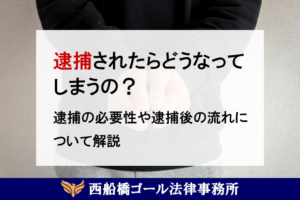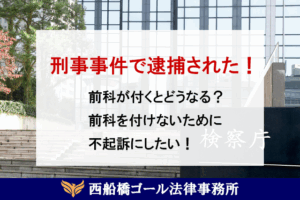職場のストーカーとは?社内でストーカーが発生したときの対応
未分類
職場でのストーカー行為は、被害者だけでなく職場全体に深刻な影響を与える問題です。
業務上の接点をきっかけに発展するケースも多く、放置すれば被害が拡大し、離職や社内トラブルにもつながります。
この記事では、ストーカー規制法における定義や職場における具体的な事例を紹介しつつ、職場で被害に遭った場合の対処法と、企業として職場のストーカーに対してとるべき対応をわかりやすく解説します。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業 平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 学習院大学法科大学院修了 平成27年9月 司法試験合格 アトム市川船橋法律事務所 令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業 所属:千葉県弁護士会
目次
職場でのストーカー行為とは?
職場でのストーカー行為は、業務での関わりをきっかけに始まることが多く、当事者だけでなく、職場全体の人間関係にも深刻な影響を与えます。
日常的に顔を合わせる職場だからこそ、被害者と加害者が日常的に接することになるため、加害者の行動がエスカレートしてしまうケースもあります。
まず、ストーカー規制法の定義を確認しながら、どのような行為がストーカーに該当するのかを見ていきましょう。
法律上の「ストーカー行為」とは
ストーカー行為は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」によって定められています。
警視庁のホームページでは、以下の行為を「ストーカー」として紹介しています。
| 分類 | 具体的な行為 |
| つきまとい等・位置情報無承諾取得等 | つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき |
| 監視していると告げる行為 | |
| 面会や交際の要求 | |
| 乱暴な言動 | |
| 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書 | |
| 汚物等の送付 | |
| 名誉を傷つける行為 | |
| 性的しゅう恥心の侵害 | |
| GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為 | |
| GPS機器等を取り付ける行為等 | |
| ストーカー行為 | 同一の者に対し、「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うこと |
参考:警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html
こうした行為を繰り返し同一人物に対して行うことが「ストーカー行為」と定義されています。

川口晴久
ストーカー行為は単なる迷惑行為や民法上の不法行為ではなく、刑事罰の対象になる可能性があるものです。
そして、職場で起きるストーカーも、これらの定義に該当する場合は刑事事件として取り扱われる可能性があります。
職場のストーカーの具体例
職場でのストーカー行為の具体例としては、同僚や上司、部下といった同じ職場で働く人からの「つきまとい」や「過剰な接近」「プライバシーの侵害」があげられます。
たとえば、業務とは関係ないメールを頻繁に送ってくる、帰宅時間や出勤経路、休日の行動を把握しようとする、無断でPCやスマートフォンを見ようとする、デスクやロッカーを勝手に見るといったもので、被害者が不快に感じる行為が繰り返されます。
ストーカー行為はプライベートタイムに行われることもある
職場でのストーカー行為は、業務時間内にとどまりません。仕事後や休日にもメールや電話、ときに待ち伏せといった手段で加害者がストーカー行為を繰り返すケースもあります。
プライベートの時間を侵害されることで、被害者は精神的に追い詰められ、日常生活に大きな支障をきたすことになります。職場以外の出来事だから関係ないと軽視せず、私的な時間に行われている行為についても一体のものであると認識して対応する必要があります。
最近ではネットストーカーというケースもある
ストーカー行為は物理的な接触だけでなく、ネット上でも行われるケースがあります。
こうした「ネットストーカー」は、周囲から見えにくいため、気づかないうちに被害者が深刻な精神的ダメージを受けるケースも少なくありません。
ネットストーカーとは
ネットストーカーとは、SNS、メール、オンラインゲーム、チャットアプリなどを利用して、執拗な接触や、監視、嫌がらせをする行為です。
たとえば、投稿をくまなくチェックして、行動パターンを分析して待ち伏せをしたり、プライベートなメッセージを送るケースがあります。
悪質な場合は、誹謗中傷や、個人情報を漏洩させるといった手段が使われることもあります。

川口晴久
誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害は犯罪となり得る行為です。
そして、ネットでのストーカー行為が職場での関係に由来している場合は、プライベートタイムに行われていたとしても職場でのストーカー行為と一体であると解釈できます。
場合によっては、職場環境づくりや管理体制が問われることもあるため、企業としても対策を講じる必要があります。
会社でストーカーの被害に遭った場合
職場でストーカーの被害に遭った場合、どのように行動すべきなのでしょうか。
職場でのストーカーには、社内の人間関係や仕事上の関係が絡むため、我慢や放置してしまうケースもありますが、我慢をするとより相手の行動がエスカレートすることもあります。ここでは、被害者になってしまった場合にとるべき対処法を紹介します。
①上司に相談する

川口晴久
職場で関わりがある人からストーカー行為を受けた場合は、できるだけ早く、直属の上司や信頼できる人物に相談しましょう。
被害の内容や頻度、加害者の行動を具体的に伝えて、証拠がある場合は、停止できるように準備しておくといいかもしれません。
ストーカーの証拠の例
・メール
・ラインやチャットの履歴
・録音 など
②警察に相談する
ストーカー行為がエスカレートして、身の危険を感じることがあれば「会社に迷惑をかけるかもしれない」などと躊躇せず、すぐに警察に相談するべきです。
それが職場で起こったことであっても、警察は「ストーカー規制法」や「迷惑防止条例」といった法律を根拠に対応してくれます。
③弁護士に相談する
ストーカーの加害者に対して、慰謝料請求、接近禁止命令といった法的措置を検討している場合は、弁護士に相談するという方法があります。
特に加害者が職場の人間である場合、職場の人間関係や雇用契約上の問題があるため、法律的判断が必要になります。
早い段階で専門家に相談してアドバイスを受けることで、ストーカー被害がエスカレートする前に手を打つことができる場合があります。
会社でストーカー被害が発生した場合(会社対応)
ストーカー被害が社内で発生した場合、当事者間の私的なトラブルだとするのではなく、組織として適切に対処しなければなりません。

川口晴久
対応を誤ると、被害がさらに大きくなるだけでなく職場環境の悪化といった悪影響が出てしまいます。
ここでは、企業側が取るべき基本的な対応を解説します。
放置せずに迅速に対応する
職場でのストーカーの被害の相談があった場合や、ストーカー行為を発見した場合は、速やかな対応が大切です。
初動で、事実確認を怠ったり、被害の訴えを軽視するような対応をしたりすると、被害が深刻化し、場合によっては会社の責任が問われる可能性もあります。
被害が分かった段階で早急に会社として問題に関与し被害者の保護などに務める必要があります。
被害者から詳しい状況を聞く
職場でのストーカーの対応で重要なのが、丁寧で慎重なヒアリングです。
社内の人間からストーカー行為が行われている場合、被害者が萎縮して本当のことを言いづらいということもあります。

川口晴久
被害の内容・頻度・手段などについて、証拠や時系列を含めて具体的に確認し、被害者の意に反しない形で記録しましょう。
被害者を保護する
ヒアリングや調査の結果、ストーカー行為があったと判断した場合は、まず被害者の保護が最優先です。
そして、加害者への指導・処分、部署異動など、会社として必要な措置を講じなければなりません。
被害者が不利益を被ることなく業務を続けられるよう、配置転換や在宅勤務の提案もできるかもしれません。
加害者への対応についても、感情的になって処分するのではなく、就業規則や雇用契約の制約を考慮して行いましょう。
再発を防止する
しかるべき対応をしたあとは、再発防止のための措置を行います。
社内でのハラスメント研修の実施や、ストーカー行為に関する法律に関するルールの再確認、社内で相談しやすい体制を整えることも必要です。
警察に相談する
加害者のストーカー行為に違法があると判断された場合や、暴力的な手段があり被害者の身に危険が及ぶ恐れがある場合は警察に相談することも検討しましょう。

川口晴久
警察と連携することで、さらなるストーカー行為の抑止にもなりますし、必要であれば警察が対応するというケースもあるでしょう。
職場のストーカーの対処をするメリット
職場でのストーカー行為に対して会社として対応することは、被害者を守るだけでなく、職場全体の安全性や信頼性を維持する上でも大きな意味を持ちます。
ここでは、企業がストーカー対策を講じることによって得られるメリットを整理します。
被害を最小限にとどめることができる
ストーカーの被害があった場合には、早期な対応がさらなる行動のエスカレートを防ぐことになります。
初期段階で加害者に警告を行ったり、物理的に社内での接触を制限をすることにより、被害の拡大を避けられます。
被害者の心身へのダメージを軽減することは、結果的に職場環境の悪化や業務への支障も抑えることにつながります。
離職の防止
ストーカー被害が長期化すると、被害者が精神的な苦痛を受け続けて、職場に居続けることが難しくなるケースもあります。
特に加害者が同じ部署に在籍している場合、日常的な接触や視線がストレスの原因となり、最終的には退職や転職を余儀なくされることがあります。
また、周囲の社員にとっても良い影響はありません。
こうした社員の心のほころびで退職者が出ると、貴重な人材が去ることになります。

川口晴久
ストーカーが問題になったときに、迅速かつ適切な対応を行うことで、安心感を高め、離職を防ぐことができます。
職場のストーカー対策として会社ができること
職場でのストーカー行為は、仕事とプライベートの両方を侵害するものです。
被害者は大きな精神的苦痛を受けることになり、会社としても信用失墜や社内の人間関係の悪化といったデメリットがあります。
ストーカー対策として会社ができることをまとめて解説します。
就業規則の徹底周知
会社の就業規則に明確にストーカー行為を禁止する条項を入れておくこと、そして、その就業規則を社員に周知徹底することでストーカーを未然に防止できます。
もちろん、就業規則があれば全員が必ず守るという保証はありませんが、会社として「禁止している」こと、そして、「被害があった場合にはしかるべき対応をする」という姿勢を見せることには一定の効果を期待できます。
被害があった場合に相談しやすい環境をつくる
万が一、被害が発生した場合はできるだけ早めに状況を把握することが大切です。
ストーカー行為は、被害者が声をあげない限り、第三者が被害に気づくのが難しい犯罪です。
職場でのストーカー行為は、被害者が声をあげにくいと感じるケースも多いため相談しやすい環境を整えることが重要です。
✅ 相談窓口を設置する
✅ カウンセラーをおく

川口晴久
上記のような対応を行い、被害が発生した場合にすぐに相談できる環境をつくりましょう。
顧問弁護士をつける
ストーカー行為は犯罪行為であり、違法行為となる可能性が非常に高いため、顧問弁護士を置いて法律的なアドバイスを受けると安心です。
会社にとっては、加害者に対する処分は労働基準法などとの兼ね合いもあるため慎重に対応しなければなりません。
顧問弁護士にいつでも相談できるようにしておけば、法律的に適切な対応ができます。
まとめ
職場でのストーカー行為は、被害者のみならず職場全体に深刻な影響を与える重大な問題です。
業務上の接点をきっかけにストーカー行為に発展するケースでは被害者が声をあげづらいということもあります。
ストーカーを「個人の問題」だとして被害を放置すれば被害が拡大し、離職や社内トラブルにもつながる可能性があります。
被害にあった場合はすぐに相談すること、そして、会社としては、初期対応を怠らず、就業規則の整備や相談体制の構築や顧問弁護士が重要です。職場でのストーカー行為は組織全体で防ぐべきリスクであることを忘れてはなりません。
職場でのストーカー対応にお悩みの方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。