過失運転致死では執行猶予がつく?交通死亡事故で不起訴を目指す方法も解説
過失運転致傷・ひき逃げ・当て逃げ
過失運転致死事件では、早期の適切な対応で執行猶予を獲得できる可能性があります。
この記事では、過失運転致死事件で実刑を回避するための条件や方法を解説します。
過失運転致死で執行猶予を目指すために今何をすべきかがわかります。
交通死亡事故を起こしてしまった後の刑事罰について、どのような処分が下されるのかわからず悩んでいる方も多いでしょう。特に過失運転致死は、人の命を奪ってしまった重い罪です。
この記事でわかること
① 過失運転致死で執行猶予がつく可能性
② 執行猶予獲得のための具体的な方法
複雑な刑事手続きの中で、どのような弁護活動が有効であるかが理解できるでしょう。
✅過失運転致死で執行猶予を目指すためには、専門知識を持つ弁護士の対応が必要です。

平成28年3月 八千代松陰高等学校 卒業
令和2年3月 早稲田大学法学部 卒業
令和4年3月 早稲田大学大学院法務研究科 卒業
目次
交通死亡事故(過失運転致死)に執行猶予はつくか
交通死亡事故を起こしてしまった場合でも、執行猶予がつく可能性はあります。

赤井耕多
しかし、条件は簡単ではありません。なぜなら、人の命を奪ったという事実の重さから、刑罰が重くなる傾向にあるためです。
被害者との示談が成立しているか、事故の過失の程度がどのくらいかなど、さまざまな事情が考慮されます。以下で詳しく見ていきましょう。
①執行猶予とは
執行猶予は、有罪判決の言い渡しがあっても、直ちに刑務所に収監されずに済む制度です。
判決で定められた一定期間、再び罪を犯さなければ、言い渡された刑の効力は消滅します。
執行猶予では、刑務所に入らず、社会生活を送りながら更生を目指せるのです。
執行猶予制度がある理由は、初犯の場合や反省の態度がみられる場合、収監するより社会で更生の機会を与える方が適切なためです。
実刑判決となり刑務所に収監されると、会社を解雇されたり、再出発が難しくなったりと、社会生活への影響は計り知れません。
過失運転致死の事件では、事故の状況や被害者との示談の有無など、さまざまな要素が執行猶予の判断に影響します。

川口晴久
交通死亡事故において執行猶予がつくかどうかは、被疑者にとって重要な問題です。
②交通死亡事故で執行猶予がつく可能性
交通死亡事故における執行猶予の可能性は、いくつかの条件によって決まります。以下を全て満たすことが前提条件です。
- 3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金の言い渡しを受けている
- 以前に禁固以上の刑に処せられたことがない
- 仮に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、執行を終えてから、または執行の免除を受けてから5年以内に禁固以上の刑に処せられていない
上記を満たした上で、裁判官が「情状」を認めれば、執行猶予がつく可能性があります。
情状とは、刑の重さを判断する際のさまざまな事情のことです。事故の原因や過失の程度、被害者との示談の有無、遺族の処罰感情、加害者の反省の度合いなどが考慮されます。
過失運転致死は、人の命を奪うという重大な結果を招く犯罪です。
執行猶予を獲得するには、上記の条件を満たすだけでなく、情状酌量を強く主張する必要があります。
具体的には、被害者やご遺族への真摯な謝罪と賠償、再発防止への具体的な取り組みなどを示すことが重要です。
交通死亡事故を起こしたときの罰則
交通死亡事故を起こしたときの罰則は、代表的なものとして次の2つが挙げられます。
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
以下で詳しく紹介します。
①過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、自動車の運転において必要な注意を怠り、人を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
道路交通法では、運転者に対し、他人に危害を及ぼさないよう細心の注意を払う義務が課せられています。
過失運転致死傷罪は、事故が起き人を負傷させたり死亡させたりした場合に適用されます。
過失運転致死傷罪の適用事例
✅ わき見運転
✅ 一時停止の見落とし
✅ 標識の無視による注意義務違反など
例えば、不注意による一時停止違反で事故を起こし、相手を負傷させてしまった場合、過失運転致死傷罪が適用されます。しかし、被害者が死亡した場合は、過失運転致死罪です。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金です。もし被害者が死亡した場合は過失運転致死罪となり、より重い刑罰が科される可能性が高まります。しかし、死亡事故であっても、情状によっては執行猶予がつくこともあります。
事故の状況や加害者の反省の度合い、示談の成立などが考慮されるためです。
②危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、危険な運転行為と認識しながら運転し、結果として人を死傷させた場合に成立する重い犯罪です。
単なる不注意による過失運転致死傷罪とは異なり、より悪質性が高いと見なされます。
どのような行為が「危険運転」に該当するかは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に定められています。該当例は、飲酒運転や薬物の影響下での運転、制御困難な高速運転、未熟な運転などです。
危険運転致死傷罪の刑事罰は非常に重いです。人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と規定されています。人の生命や身体に対する危険性の認識があったにもかかわらず、その行為を敢行したことに対する厳しい処罰です。
酒に酔った状態で車を運転し、衝突事故を起こして相手を死亡させてしまった場合、危険運転致死罪が適用されます。執行猶予がつく可能性は極めて低くなります。
危険運転致死傷罪が、単なる不注意を超えた悪質な行為であると判断されるためです。
過失運転致死で執行猶予を目指す方法
過失運転致死の状況で執行猶予を獲得するには、複数のアプローチがあります。
中でも重要なのは、検察官の判断に影響を与える活動です。
具体的には、不起訴処分を目指すことや、より軽い罪での起訴を求めること、そして裁判で有利な情状を主張することが挙げられます。
示談を成立し不起訴を目指す
過失運転致死で刑務所に服役するのは、起訴され実刑判決を受けた場合です。
しかし、不起訴処分となれば、刑事裁判は開かれませんし、当然実刑判決も出ません。
起訴・不起訴の決定は検察官が行いますが、被害者側にも一定の過失があったり、加害者側の落ち度が軽減される事情がある場合などには、捜査段階での弁護活動によって、不起訴の可能性を高めることは可能です。

赤井耕多
その中でも特に重要なのが、被害者との示談を成立させることです。
示談とは、加害者が被害者に直接謝罪し、損害を賠償することで和解することを指します。
示談が成立すれば、被害者の損害が償われ、さらに被害者からの許しが得られている状態になります。示談の成立は、加害者の反省の態度が具体的な行動として示されていると評価されるのです。
検察官は、示談が成立している場合、事故態様も考慮のうえ、「裁判を開始してまで刑罰を科す必要はない」と判断し、不起訴処分を下すことがあります。
ただし、あまりにも悪質な事案は示談が成立していても起訴され、刑罰が科されることもあるでしょう。
弁護士に依頼することで、被害者側との冷静な交渉を進め、適正な示談額の提示や、円滑な合意形成をサポートしてもらえます。
過失運転致死傷罪での起訴を目指す
起訴されることになった場合は、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死罪で起訴されることを目指すのが重要です。
違いは、執行猶予の可能性に大きく影響します。
過失運転致死罪の場合、比較的執行猶予がつきやすい傾向にあるからです。一方で、危険運転致死傷罪では、ほとんどのケースで実刑判決が下されます。
法務省の「犯罪白書」によると、2022年の過失運転致死罪の執行猶予率は、懲役・禁固の言い渡しを受けた者のうち約90.4%でした。
一方で、危険運転致死傷罪では、ほぼ全てのケースで実刑判決となっています。
適用される罪名が刑事処分に与える影響の大きさがわかるでしょう。

川口晴久
弁護活動では、事故の状況が危険運転に該当しないことを示し、注意義務違反による「過失」を主張する必要があります。
事故当時の状況を詳細に分析し、客観的な証拠を集めることが不可欠です。例えば、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、車の損傷状況などを基に、危険運転の意図がなかったことを立証します。
過失運転致死罪で起訴されるよう、検察官に働きかける弁護活動が、執行猶予獲得への重要な一歩となるでしょう。
示談を成立させ運転免許を再取得しないと誓約し執行猶予つきの判決を目指す
死亡事故の裁判は、執行猶予つきの判決を目指す必要があります。
裁判官が刑の重さを判断する際の「情状」を、できるだけ有利に形成することが重要です。検察官が容疑者を起訴するかを決定し、起訴された後にどのような刑罰を科すかは、裁判官が総合的に考慮して判断します。
示談が成立した事実は、加害者にとって非常に有利な材料です。
示談は、被害者への誠実な謝罪と損害賠償が行われたことを示し、加害者の反省の態度を具体的に示すものとなります。示談の成立により、裁判官は加害者が十分に反省し、償いを果たそうとしていると評価するでしょう。
さらに、服役を回避し執行猶予を得るためには、再犯の可能性がないと判断されることがポイントです。
裁判官は、被告人が再び罪を犯すリスクが低いと評価すれば、社会内での更生を促す執行猶予を検討しやすくなります。
交通事故による死亡事件の場合、「車を運転しなければ事故を起こすことがなくなる」という事実があります。運転免許を再取得しないと誓約することは、再犯防止への強い意思表示です。
過失運転致死と執行猶予に関するよくある質問
以下では、過失運転致死と執行猶予に関するよくある質問に答えていきます。
過失運転致死で執行猶予になる確率は?
過失運転致死罪において、執行猶予がつく可能性は比較的高いといえます。
法務省の「犯罪白書」によると、2022年に過失運転致死罪で懲役・禁固の言い渡しを受けた者のうち、約90.4%が執行猶予となっています。実刑判決となるのは約9.6%程度にとどまっているのが現状です。
高い執行猶予率は、過失運転致死罪が、故意犯とは異なり、不注意によって結果が生じてしまったという特性を持つためです。もちろん、個々の事件の状況や、被害者やご家族との示談の有無、加害者の反省の度合いなどによって、結果は大きく変わります。
過失運転致死で懲役何年になりますか?
過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と定められています。「拘禁刑」は、2025年6月1日施行の改正刑法により「懲役」と「禁錮」が統合された新しい刑の種類です。
人を死亡させてしまった場合は過失運転致死罪が適用され、この範囲内で刑罰が決定されます。しかし、被害が軽微な「傷害が軽い場合」には、裁判官の情状により刑が免除される可能性もあります。
具体的な事故の状況、加害者の過失の程度、被害者やご遺族への示談状況、反省の態度など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されるためです。
人身事故で相手を死亡させると免許はどうなりますか?
人身事故で相手を死亡させてしまった場合、運転者は運転免許の取り消し処分を受けます。

赤井耕多
取り消し処分は行政処分であり、刑事処分とは別に課されるものです。
免許取り消し処分を受けると、一定期間は運転免許を再取得できなくなります。
この期間は欠格期間と呼ばれ、過去の違反歴や事故の状況によって異なります。
さらに、刑事罰として、過失運転致死罪や危険運転致死罪に問われる可能性があるでしょう。
これらの罪で有罪判決を受けた場合、懲役刑や罰金刑が科せられます。特に、危険運転致死罪は刑が重く、執行猶予がつくことは少ないです。
まとめ│過失運転致死で執行猶予を得るには示談に強い西船橋ゴール法律事務所へ相談を
過失運転致死事件で執行猶予を得るには、弁護士によるサポートが必要です。
特に、判決の行方を大きく左右するのが、被害者やご遺族との示談交渉といえるでしょう。
執行猶予が認められるには、真摯な反省と謝罪の気持ちが具体的な形で示される必要があるからです。しかし、加害者側が直接交渉すると感情的な対立を招きやすく、事態を悪化させるリスクがあります。
弁護士が介入すれば、法的な観点から冷静に話し合いを進めることが可能です。適切な賠償額を提示し、円滑な示談成立を目指すことで、執行猶予の可能性を高めることができます。
過失運転致死という深刻な事態だからこそ、1人で悩まずに専門家へご相談ください。
千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所は示談交渉と刑事事件に自信があります。
ぜひお気軽にご連絡ください。
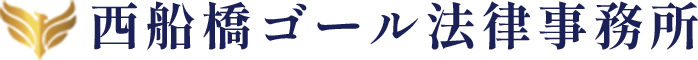
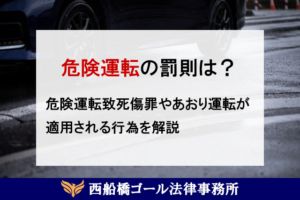
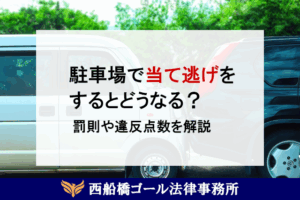
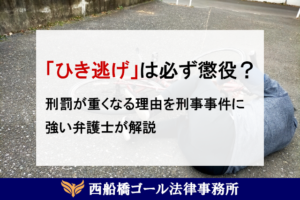
をしたら逮捕される?刑罰の重さは?-300x200.png)