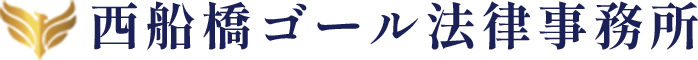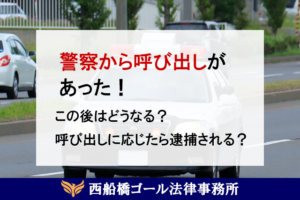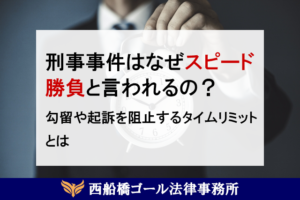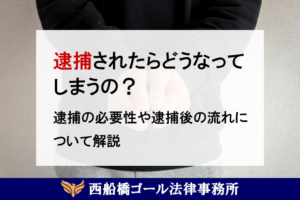起訴後の刑事裁判の流れは?裁判の期間はどのくらい?
未分類
この記事でわかること
✅刑事裁判の流れ
✅裁判が終わるまでの期間

平成28年3月 八千代松陰高等学校 卒業
令和2年3月 早稲田大学法学部 卒業
令和4年3月 早稲田大学大学院法務研究科 卒業
目次
手続きの流れ
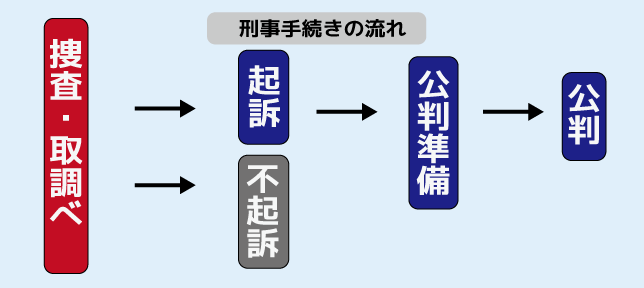
刑事裁判は、基本的に、起訴→公判準備→公判という流れで進んでいきます。
※起訴するかどうかは、検察官が、警察の集めた証拠や被疑者の供述、示談の成立の有無などを総合的に考慮したうえで、決めます。
この記事では起訴されて以降の流れを説明していきます。
起訴
まず、前提として、起訴されなければ、裁判は行われません。
起訴するかは、検察官が判断します。
起訴するかを決める要素
・犯罪をしたことを認定するだけの証拠が十分にあるか
・示談の成立の有無など情状関係
・犯罪が重大であるか 等
起訴されたら
場合には、それまで、被疑者という立場だったものが、被告人という立場になります。
また、起訴前の勾留期間は、最大でも20日間ですが、起訴後であれば、起訴前から勾留されている場合には、判決が出るまでの間、勾留が続くことが一般的です。
在宅事件の場合
起訴前から勾留などの身柄拘束を受けていない場合には、自宅に起訴状が送られてきます。

川口晴久
この場合には、裁判所に行く必要がある日までは、普段と変わらない生活を送ることができます。
公判準備
起訴された場合には、公判に向けての準備が行われます。
ここで、公判前整理手続が行われるかどうかが非常に重要になってきます。
公判前整理手続きとは
公判前整理手続きとは、刑事裁判を円滑に進めるために裁判官、検察官、弁護士の三者がお互いに、どのような証拠を請求し、どのように裁判で争っていくのかのおおよその枠組みについて共有し合う場です。
公判前整理手続きの目的は、刑訴法316条の2第1項に規定されているように、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に実現するために審理計画を立てることとされています。
公判前整理手続きはすべての事件で開かれるわけではありません。
一般的には、争点が複雑なうえ、証拠も多く、整理の必要が大きいものや、裁判員裁判の場合には、公判前整理手続に付されることになります。

赤井耕多
この公判前整理手続きには、被告人にも出席する権利があります。
公判前整理手続きの流れ
以下、公判前整理手続の流れを簡単に見ていくことにします。
1. 検察官による証明予定事実記載書の提出
この証明予定事実記載書は、検察官が、これから裁判で何を証明するつもりなのかが書かれた書面になります。
それを見て、弁護士も、これから検察官が何をしようとしているのかを把握することになります。
2. 検察官による証拠調べ請求及び、請求証拠の開示
検察官が証拠調べ請求及び、請求証拠の開示し、弁護士は、検察官がどのような証拠を請求しているかを確認します。
また、弁護士は、検察官に対して、証拠一覧表の提出を要求します。

川口晴久
これをすることで、検察官がどのような証拠を持っているかの確認をすることができます。
とはいえ、証拠一覧表には、警察から検察官に送致された証拠しか記載されません。そのため、先ほども述べた、類型証拠開示請求というものを行い、被告人にとって有利となるような証拠を探していきます。
※この類型証拠開示請求というものは、法律上規定されている類型の証拠を請求できるというものです。
3. 弁護士、検察官それぞれの請求証拠について、同意・不同意といった意見を提出する
弁護士側も、証拠開示が進んだ段階で、予定主張記載書面を提出します。この予定主張記載書面については、弁護士が主張する予定の事実を記載します。
■主張関連証拠開示請求
公判前整理手続きでは、類型証拠開示請求以外にも、主張関連証拠開示請求というものを行うことができます。
これは、弁護士の主張に関連すると考えられる証拠について、検察官に開示を請求するものです。この主張関連証拠開示請求では、類型に当たる証拠かどうかを考える必要はなく、また、検察官の手元になくても、検察官が容易に取得できるものであれば、取得させることができるという制度です。
公判前整理手続きは、弁護士としては、検察官の証拠について、できるだけ多くの開示を請求できるものであり、被告人にとって有利な判決を得るために、非常に重要な制度であるといえます。

赤井耕多
公判前整理手続きをした場合には、原則として、これ以降の証拠の提出はできなくなるということには、注意が必要です。
公判前手続きをしない場合
まず、弁護人としては、検察官が、公判で、どのような証拠によって、被告人が犯罪を行ったことを証明するかを確認する必要があります。
そこで、検察官に連絡をしたうえで、事件の記録をいつ開示するのかを問い合わせます。
この事件記録がいつまでに開示されるかは、各検察庁によって運用が異なるのですが、例えば、東京地方検察庁では、第1回公判の2週間前までに開示される運用になっています。
そのうえで、記録を閲覧し、謄写(コピー)していきます。そして、記録を確認したら、被告人と打ち合わせをして、どのような弁護をするべきかの方針を立てていきます。
被告人に事実関係の確認をしたうえで、証拠と矛盾がないのかを確認します。
被告人との打ち合わせ以外にも、検察官とも、第1回公判までに、事件の争点を明らかにするために、打ち合わせを行います。
また、検察官の請求している証拠について、同意・不同意といった意見を知らせます。ここで、検察官は、警察の捜査によって集められた証拠から、犯罪事実を立証するための証拠を請求しています。つまり、検察官は、犯罪の事実の立証に必要ない証拠については、請求しません。
しかし、そのような証拠のなかには、被告人にとって有利となる証拠が存在している場合があります。そのため、弁護士は、類型証拠開示の申し立てというものを行い、被告人にとって有利な証拠がないかを確認していきます。証拠については、弁護士自身も、請求することができます。そのため、弁護士として、被告人のために請求する予定のある証拠については、事前に検察官へ伝えておきます。
公判(裁判)
公判準備が終わると、いよいよ裁判になります。この裁判については、裁判員裁判の場合と通常の裁判の場合で、その流れや、かかる時間についても、異なっていきます。
また、認め事件か否認事件でも変わっていきます。
ここで、認め事件とは、被告人が、犯罪行為をしたことを認めている場合のことをいい、争点としては、量刑がどの程度になるかを争います。一方で、否認事件とは、犯罪行為をしたことを認めず、無罪を主張することをいいます。
そこで、まずは、通常の裁判の流れについて、解説していきます。
裁判官裁判の流れ
まず、裁判官裁判の場合の流れは、
人定質問→起訴状朗読→黙秘権の告知→罪状認否という最初の手続きがあり
そのあと証拠調べに入ります。
証拠調べ手続きでは、検察官の冒頭陳述→検察官の証拠の取り調べ請求→弁護士の証拠に対する意見→裁判官による証拠採用の決定→弁護士の証拠の取り調べ請求→検察官の証拠に対する意見→裁判官による証拠採用の決定という流れをとります。
その後、証人尋問が予定されている場合には、証人尋問が行われ、最後に被告人質問が行われます。
そして、証拠調べ手続きの後には、論告→弁論→被告人の最終陳述→判決の言い渡しとなります。
以上がおおよその流れです。次に、それぞれについて説明していきます。
最初の手続き
人定質問とは、被告人が本当に被告人本人かを確認するためのものです。例えば、被告人の名前や職業、住所などを聞きます。
起訴状朗読とは、検察官が起訴状を読み上げ、被告人がどのような罪を犯したかを述べることです。
黙秘権の告知は、その名のとおり、被告人に対して、黙秘権という権利があることを説明することです。
罪状認否は、起訴状に書かれた通りの犯行をしたかどうかを確認するものです。
ここで、被告人は、量刑のみを争うなら、間違いないなど認める旨の発言をし、無罪を主張するなら、私は犯行をしていないなどの発言をします。
以上が、最初の手続きについてのおおまかな説明です。
証拠調べ手続き
検察官の冒頭陳述とは、検察官が事件の概要、証拠により証明しようとする事実を話し、今後の立証方針を明らかにするためのものです。
冒頭陳述が終わると、検察官は、証拠調べ請求を行います。その証拠調べ請求に対して、弁護士は、意見を述べていきます。
おおよそ、証人の供述調書や、被告人の供述調書については、不同意としたうえで、証人尋問をすることになる場合が多いです。
そして、裁判官が、弁護士の意見を聞いたうえで、証拠の採用・不採用を決めます。この後、弁護士も、自身が用意してきた証拠がある場合には、証拠調べ請求を行います。その後の流れは、先ほど述べた、検察官の証拠調べ請求のときと同様です。
その後、証人尋問がある場合には、その証人に対して、尋問を行います。通常、自身が証拠調べ請求、つまり、証人尋問を請求した側が、主尋問を行い、それに対して、相手側が反対尋問を行っていきます。主尋問というのは、その証人の証言によって、証明したい事実を話してもらうもので、反対尋問は、その事実の証明力を減退させるような事実を獲得するために行うものです。
そして、被告人質問も、証人尋問と同様のかたちで行われます。この場合は、弁護士が主尋問を行い、検察官が反対尋問を行います。
以上が、証拠調べ手続きの概要です。
判決まで
証拠調べ手続きが終わると、論告が行われます。論告とは、検察官の、これまでの裁判における活動の集大成といえるものです。簡単に言うと、まとめのようなものです。
この論告では、被告人がなぜ有罪なのか、どのくらいの量刑が妥当であるかについての意見を、これまでの裁判での活動をもとに、述べていきます。
そのあと、弁護士の弁論が行われます。これは、検察官の論告の弁護士バージョンといったものです。弁護士は、逆に、被告人が反省していることや、有罪にはなりえないことをについての意見を、これまでの裁判での活動をもとに、述べていきます。
この両者の意見を裁判官が聞いたうえで、判決が述べられます。
以上が、判決までの流れです。
裁判員裁判の場合
裁判員裁判の場合では、まず、冒頭陳述を検察官だけでなく、弁護士も必ずしなければなりません。
これは、裁判員裁判の場合には、裁判官だけでなく、一般の方々も裁判員として裁判を傍聴したうえで、判決を考える必要があるため、裁判員の方々の理解の手助けをするためだといえます。
また、裁判員裁判の対象となる事件は、複雑な事件の場合が多いため、検察官と弁護士の双方に、これからどのような主張をしていくのかを述べさせることで、内容を分かりやすくするという目的もあるといえます。
また、裁判員裁判の場合は、検察官と弁護士の論告、弁論が終わった後に、裁判官と裁判員による評議が行われます。この評議とは、これまでの裁判を踏まえて、どのような判決を出すべきかを、裁判官と裁判員で話し合って、決めるというものです。
裁判員裁判では、通常の裁判と異なる点がまだあります。それは、パワーポイントを使ったりするなど、とにかくわかりやすくしていくことです。これは、裁判員の方々にも、どのようなところを判断してほしいか、なにを重点的に見てほしいかということを、なるべくわかってもらうために行われるものです。
また、裁判員裁判は、公判が開始されると、連続して期日をいれたうえで、評議も連続して行われるため、通常の裁判に比べると、公判が始まってしまえば、すぐに終わるといえます。
認めと否認事件の違い

赤井耕多
認めと否認事件の場合の違いは、端的にいうと、判決が出るまでの長さに違いが生じます。
つまり、被告人が犯罪の事実を認めている場合には、争いとなるのは、量刑になるといえます。そのため、判断することが少なく、早期に判決が出ます。場合によっては、即日判決といって、その日のうちに、判決まで宣告されることもあります。
一方で、否認事件の場合は、犯罪事実の有無が争点となるので、その認定には相応の時間がかかります。つまり、判決までの時間も長くなります。
判決までにかかる期間
【起訴~裁判】
まず、裁判官裁判の場合、起訴から裁判に至るまでにかかる時間は、おおよそ1か月半から2か月ほどかかります。
一方、裁判員裁判の場合には、公判前整理手続きを行いますから、必然的に裁判が始まるまでは、長くなるといえます。起訴から裁判に至るまでには、おおよそ4か月~半年、場合によっては、1年以上かかることもあります。もちろん、否認事件の場合のほうが、より時間がかかるでしょう。
【裁判~判決】
そして、裁判が始まってから、判決に至るまでにかかる時間としては、認め事件の場合は、最短で1日から、最長でも、1か月というところです。平均すると、2週間程度でしょう。
一方で、否認事件の場合は、複数回の期日を行ったうえで、判決を出すため、数か月かかります。
裁判員裁判の場合は、上述したように、いざ、公判が始まれば、そのあとは、集中して期日が入れられたのち、判決となるため、最長でも2~3週間程度で判決に至ります。認め事件の場合には、1週間程度でしょう。
✅ 総合すると、裁判官裁判で、認め事件の場合は、起訴から判決までは、おおよそ2~3か月程度、否認事件の場合は、半年から1年ほどかかります。
✅ 裁判員裁判の場合は、認めか否認かの場合で起訴から裁判に至るまでの期間に大きな違いはありますが、半年から長くて数年程度かかるものもあるといえます。
まとめ
刑事裁判は、起訴されてから、裁判が始まるまでに、準備を十分にしたうえで、場合によっては、長期間の裁判をしていく必要があります。
刑事裁判の準備には、専門的な知識と適格な判断が求められ、ご本人やご家族だけで対応するのは大きな負担となります。

川口晴久
不安な点があれば、早めに弁護士にご相談ください。
千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所は、刑事事件の豊富な経験を活かし、状況に応じた的確なアドバイスと、今後の見通しをご案内いたします。
お気軽にご相談ください。

平成28年3月 八千代松陰高等学校 卒業
令和2年3月 早稲田大学法学部 卒業
令和4年3月 早稲田大学大学院法務研究科 卒業