盗撮で後日逮捕されたらどうする?刑事処分を軽くするためのポイントを弁護士が解説
盗撮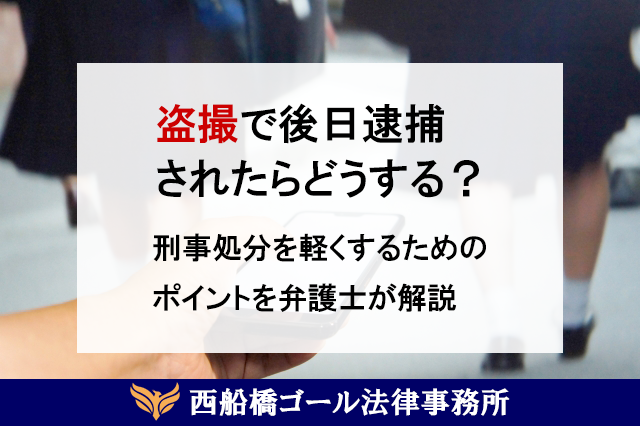
目次
盗撮で後日逮捕されたらどうする?
盗撮の加害者となった方へ、「現行犯逮捕との違い」「どんなときに後日逮捕されるか」「後日逮捕後、勾留・釈放されるまでの流れ」「後日逮捕された場合に起訴を回避する方法」などを盗撮事件に詳しい弁護士が解説します。
この記事でわかること
✓ 後日逮捕と現行犯逮捕の違い
✓ 後日逮捕から勾留・釈放されるまでの流れ
✓ 後日逮捕に至る3つのきっかけ
✓ 起訴を回避するための4つの方法
✓ 弁護士選定や費用負担について家族や友人ができるサポート

法政大学法学部卒業
学習院大学法科大学院修了
アトム法律事務所
アトム市川船橋法律事務所
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
所属:千葉県弁護士会
盗撮事件には現行犯逮捕と後日逮捕の二種類がある
盗撮行為で逮捕されるケースには、現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。
後日逮捕の場合、事件の捜査開始直後はまだ身柄拘束されていませんが、いつ警察が自宅や職場に来るかわかりません。
「家族や同僚の目の前で逮捕されたらどうしよう……」
そんな不安を抱えている方は一度弁護士にご相談ください。
盗撮事件では後日逮捕される可能性がある
盗撮事件と聞いて、多くの方がイメージするのは、現場で被害者や周囲の人に取り押さえられる「現行犯逮捕」かもしれません。
しかし、実際には、盗撮行為から時間が経過した後に、警察の捜査を経て逮捕される「後日逮捕」のケースもあります。
後日逮捕とは、犯罪が行われた後、捜査機関(警察や検察)が必要な証拠を収集し、「被疑者であると疑うに足りる相当な理由」があり、かつ「逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれ)」が認められる場合に、裁判官が発行する逮捕状に基づいて行われる逮捕のことです。(刑事訴訟法第199条第1項)
盗撮事件では、犯行現場から一旦逃げたとしても、様々な証拠から犯人と特定され、後日逮捕される可能性があります。
近年は防犯カメラ映像の解析やデジタルデータの復元などが容易になったため、後日逮捕の可能性は以前よりも高まっています。
現行犯逮捕と後日逮捕の違い
盗撮事件では現行犯逮捕されるケースも少なくありません。
では、現行犯逮捕と後日逮捕はどのように違うのでしょうか。
逮捕できる要件や手続きの違いを解説します。
現行犯逮捕とは?
犯行中または犯行直後で、逃走や証拠隠滅のおそれが高い場合に認められるのが現行犯逮捕です。
現行犯人にあたるかは、刑事訴訟法が定める以下の要件を満たすかどうかで決まります。
現行犯人にあたる要件
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者(刑事訴訟法212条1項)
満員電車で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しているように、誰が見ても「たった今、盗撮した」と言える場合、その者は現行犯人となります。
また、「たった今、盗撮した」とまでは言えないとしても、それが強く疑われるような以下の4つのケースも、同様に現行犯人とみなされます。(刑事訴訟法212条2項)
✔ 犯人として追呼されているとき(1号)
✔ 贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(2号)
✔ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(3号)
✔ 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(4号)

川口晴久
たとえば、「盗撮犯です!」などと追及された男があわてて電車から降りて逃げようとしている場合(1号)や、犯人が盗撮用の小型カメラをカバンの中に隠したのを見つけたような場合(2号)です。
以上の要件に該当する者は盗撮の現行犯である可能性が高いと言えるでしょう。
現行犯人であることが明らかな者に対しては、警察官等ではない一般人であっても、犯人の体を押さえ込むなどの実力行使をして逮捕することが許されます。(私人逮捕。刑事訴訟法213条)
後日逮捕とは?
後日逮捕とは、逮捕状にしたがって行われる通常逮捕のことです(刑事訴訟法199条1項)。
現行犯逮捕が犯行から間もない時・場所で行われるのに対して、通常逮捕は犯行直後ではなく「被疑者であると疑うに足りる相当な理由がある」と認められる時にのみ、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われます。
このように、通常逮捕は犯行から一定の時間が経過してから行われるため「後日逮捕」と呼ばれるわけです。

赤井耕多
盗撮をしたと疑われる者(被疑者)を後日逮捕する際は、その者の目の前で逮捕状を示さなければなりません。
※刑事訴訟法201条1項より
盗撮事件で後日逮捕後、勾留・釈放されるまでの流れ
ここでは、盗撮事件の犯人が後日逮捕されてから勾留・釈放されるまでの流れを詳しく説明します。
身柄拘束に関する刑事手続のポイントも合わせて紹介しますので参考にしてください。
被害届受理・事件の認知
「盗撮された被害者が警察署に被害届を提出する」「盗撮を目撃した第三者が通報する」などにより警察が事件を認知すると、捜査が始まります。
捜査(事情聴取・証拠収集・被疑者の特定)
最初に行うのは被害者や目撃者からの聞き取りです。
盗撮された日時と場所、犯人の特徴(外見、服装など)、使用された機器などの情報が記録されます。
被害者からの聞き取り等の結果、事件の重大性が高いと判断した場合、現場周辺での聞き込みや防犯カメラの確認など、本格的な捜査を行います。
盗撮事件における主な捜査活動は以下のとおりです。
主な捜査活動(盗撮)
- 目撃者の事情聴取
- 犯行現場の検証
- 防犯カメラ映像の収集と解析
- 押収品の分析(スマートフォンやPCの解析など)
- 通信事業者への照会(インターネット上に画像がアップロードされた場合)
- SNSやウェブサイトの監視
- 類似事件との関連性の調査
捜査によって被疑者が特定された場合は、その人物の前歴や生活状況、職業といった背景情報も詳しく調査され、後の逮捕状請求等の判断材料となります。
警察官による逮捕状請求と後日逮捕
捜査によって「被疑者の逮捕が必要」と判断された場合、司法警察員(巡査部長以上の階級を有する警察官)が裁判所に逮捕状発布を請求し、逮捕状に基づいて被疑者を逮捕します。
これが警察官による後日逮捕(通常逮捕)です。

川口晴久
ただし、被疑者が特定された場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれが少ない場合後日逮捕されないこともあります。
検察官への送致または釈放
捜査が完了すると、警察は事件を検察官に送致します。
送致の時点ですでに被疑者が逮捕されている場合は、捜査で得られた証拠等とともに被疑者の身柄も検察官に送致します(身柄送致、身柄送検)。
身柄送致をするかどうかは、必ず逮捕から48時間以内に決定することが必要です。
送致をしない場合、警察官は被疑者をすみやかに釈放しなければなりません。
一方、被疑者が逮捕されていない在宅事件の場合は、検察官に対して事件の資料だけを送致します(書類送致、書類送検)。
書類送致の場合、被疑者の身柄は拘束されていませんから、「48時間以内に送検するかどうか決めなければならない」という時間的制約はありません。
検察官による逮捕・勾留請求または釈放
検察官が送致された事件資料をチェックした結果、「警察が捜査で得た証拠だけでは不足している。被疑者を拘束して話を聞く(取り調べをする)必要がある」と判断した場合、検察官は裁判官に対して被疑者の勾留を請求します。
ただし、書類送致(在宅事件)の被疑者について勾留請求をする場合、まずは被疑者を逮捕しなければなりません。
被疑者が在宅のまま、逮捕を経ないでいきなり勾留することは違法だからです。
✓ このルールを「逮捕前置主義」といいます。
勾留は、逮捕よりも長期間にわたり被疑者の身柄を拘束する点で、被疑者の人権を強く制限します。
そのため、まずは逮捕手続きを先行させて、「本当に身柄拘束が必要なのか」を裁判官に慎重に吟味させるわけです。
裁判官が「被疑者を逮捕すべき理由がある」と判断した場合は、逮捕状を発布します。
検察官はその逮捕状を持って被疑者の自宅や勤務先等に出向き、被疑者に提示して後日逮捕(通常逮捕)を行います。
裁判官が「被疑者を逮捕すべき理由がない」と判断した場合は、被疑者をすぐに釈放しなければなりません。
また、逮捕前置主義にしたがい被疑者を逮捕してから検察官が勾留請求をした場合でも、「被疑者をこれ以上勾留すべき理由はない」と裁判官が判断すれば、勾留請求が却下されるので、やはり被疑者はすぐに釈放されます。
身柄の長期間拘束を阻止するためのタイムリミットは「72時間」
検察官は、警察官から被疑者の身柄を送致されたときから24時間以内に裁判官へ勾留請求をしなければなりません。

赤井耕多
捜査の結果、勾留の必要性がないと判断した場合は、勾留請求せずにすぐ釈放する義務があります。
被疑者の送致から24時間以内に「勾留か、釈放か」を判断するのは少しあわただしく感じるかもしれませんが、これは被疑者の人権保障のために必要なことです。
身柄を長期間拘束されたまま取り調べを受けた被疑者は、精神的に追い込まれ、早く解放されたくて犯していない罪を自白してしまうかもしれません。
被疑者の自由な意志に基づかない自白は、ときに「冤罪」を引き起こします。
そのため刑事訴訟法は、被疑者の拘束時間が必要最小限になるよう制限しているのです。
以上の説明でわかるように、盗撮で警察に逮捕された犯人が長期間身柄を拘束される(勾留される)かどうかの判断は、「逮捕から48時間」+「送致から24時間」=72時間以内に決まります。
✓ 逮捕から72時間経っても捜査が進展せず、「この盗撮事件は証拠が足りないので、これ以上被疑者を拘束する理由がない」と判断されれば、勾留請求されることもなくすぐに釈放されます。
被疑者の身柄拘束期間は最長23日間におよぶ
逮捕から72時間以内に勾留請求が行われ、裁判官によって勾留が認められると、その後は長期間にわたり身柄拘束されるのが通常です。
勾留期間は10日間ですが、追加捜査の必要性から再度の勾留請求が認められると、さらに10日間勾留されます。
つまり、盗撮で警察に逮捕されてしまうと、最長で23日間も身柄を拘束される可能性があるのです。
盗撮犯の後日逮捕に至る3つのきっかけ
2024年に盗撮事件が捜査機関に認知された件数は8436件にもなります。
その内、検挙(事件が捜査対象になること。逮捕されない場合も含む)に至った事例は6867件です。
つまり、盗撮事件の80%以上が検挙されていることになります。
これは、侵入盗(空き巣)の検挙率が60%に満たないことと比べると、かなり高い数字だと言えるでしょう。
では、検挙された盗撮事件の犯人は、どのような捜査がきっかけで後日逮捕されるのでしょうか。
以下の3つを詳しく解説します。
後日逮捕のきっかけ
・被害者による被害届、第三者の目撃証言
・防犯カメラ映像・監視カメラの解析
・パソコン・スマホのデータ解析
被害者の被害届、第三者の目撃証言
盗撮事件で後日逮捕に至る最も多いのは、被害届や目撃証言による犯人の特定です。
被害者からの被害届を受理した警察は、聞き取り調査で犯罪事実の有無を調べ、第三者の目撃証言などもふまえて犯人の特定を図ります。
被害者等の証言と現場状況が整合すれば、逮捕状請求の前提となる「相当な理由」が成立するため、裁判官が発布した逮捕状をもとに、犯人の自宅や勤務先等で後日逮捕が行われます。
防犯カメラ映像・監視カメラの解析
商業施設や駅構内に設置された防犯カメラの映像を解析し、行動履歴や服装から犯人を割り出して後日逮捕に至るパターンもよくあります。
映像記録は強力な客観的証拠となるため、犯行現場付近にカメラがある場合は必ず映像を解析し、逮捕の理由を裏付ける証拠として活用します。
パソコン・スマホのデータ解析
盗撮する方法は様々ですが、よくあるのがスマートフォンや小型カメラなどのデジタル機器を使う方法です。
盗撮をしてしまった人の多くは、デジタル機器に保存された画像等を見るだけで満足できず、鑑賞・販売するために画像を保存しているというケースが多いです。
そのため、家宅捜索により自宅等からパソコンやスマートフォンを押収してデータを解析すると、盗撮画像・動画が大量に発見されることも珍しくありません。
過去の撮影データもすべて一覧できるので、常習性を裏付ける強力な証拠となります。
データに含まれる撮影日時や位置情報を、聞き取り等で明らかになった犯行現場の状況と照合して一致すれば、被疑者として特定されるので後日逮捕に至ります。
盗撮で起訴を回避するための4つの方法
盗撮で後日逮捕された犯人が起訴を回避したい場合、以下の4つの方法が有効です。
盗撮で起訴を回避するために
✓ 刑事事件に強い弁護士に相談する
✓ 早期に示談交渉を行う
✓ 誠実な反省と再犯防止策を示す
✓ 証拠隠滅は絶対にしない
それぞれ詳しく解説します。
1.刑事事件に強い弁護士に相談する
後日逮捕されたときに最初に行うべきことは、刑事事件に強い弁護士への相談です。
もちろん本人は身柄拘束されているので直接弁護士を探したり依頼したりすることはできません。
家族や友人がサポートしてあげましょう。
弁護士の主な仕事は4つあります。
弁護士活動の例
・ 余計な自白を防ぐための黙秘権行使のアドバイス
・ 違法捜査からの保護
・ 示談交渉の代行
・ 不起訴や執行猶予獲得のための活動
逮捕直後に被疑者の言い分を記録する「弁解録取」や、警察等で行われる「取調べ」の段階では、弁護士のアドバイスなしに供述してしまうと、後の弁護方針に悪影響を及ぼす可能性がありますので注意しましょう。
2.早期に示談交渉を行う
傷害事件の場合、示談交渉するためには被害者の治療を待つ必要があります。
これは、治療していない状況では被害の程度が不確定であり、示談を進めることができないからです。
一方、盗撮事件の場合、傷害事件と比べると被害者の心身の負傷は大きくないため、被害者の治療を待たずに示談交渉を始めることができます。
盗撮事件では早期の示談成立が非常に重要です。

川口晴久
示談が成立していれば不起訴処分となる可能性が高まるからです。
ただし、示談が成立しても必ず不起訴になるわけではありません。
たとえば、複数人で集団行動し、常習的に盗撮していたような事件や、盗撮映像を販売して莫大な利益を得ていたような事件の場合、被害者の個人的な権利侵害にとどまらず、社会の秩序を乱した点で重大な犯罪とみなされます。
このようなケースでは、たとえ被害者と示談が成立していても起訴される可能性はかなり高いでしょう。
刑事事件における示談には以下のような効果があり、これは盗撮事件でも同様です。
示談の効果
✓ 被害者感情の緩和による処分軽減が期待できる
✓ 検察官の起訴判断における有利な情状材料となる
✓ 起訴後も量刑判断での減刑要素となる
身柄拘束事件の場合、加害者自ら被害者と連絡をとって示談交渉することは不可能です。
したがって、示談交渉は弁護士を通じて行います。
また、たとえ在宅事件であっても、被害者と直接接触しようとすると無用なトラブルを引き起こします。
適切な示談金額の設定や条件交渉ができなくなるので、必ず弁護士に依頼して示談交渉を進めましょう。
3.誠実な反省と再犯防止策を示す
盗撮の証拠が固まっているのに、取調べにおいて全く罪を認めず黙秘を貫くなど、反省の態度を示さないことは不利に働きます。
起訴処分を避けるためには、取り調べに誠実に対応し、反省の態度を示すことが何よりも重要です。
具体的には以下のような態度を取ると良いでしょう。
反省の態度を示す例
・犯行をすみやかに認め、責任を受け入れる姿勢を示す
・ 深い反省の意を示すため、反省文を作成する
・再犯防止のための具体的な計画(カウンセリング受診など)を自ら申し出る

赤井耕多
このような態度を示すことで、検察官の起訴・不起訴の判断で有利に働く可能性が高まります。
また、もし起訴されてしまった場合でも、裁判において充分な反省の態度を示せば、情状酌量で刑が軽くなることが期待できます。
4.証拠隠滅は絶対にしない
身柄が拘束されない在宅事件の場合、被疑者の心理としては「自由に動ける今のうちに盗撮の証拠を消しておけば、逮捕や勾留、起訴を免れるのでは?」と思いたくなるかもしれません。
しかし、いったん捜査が始まったあとは、「パソコンやスマートフォンのデータ削除」「SNSアカウントの削除」といった証拠隠滅は厳に慎むべきです。
特にデジタルデータの場合、削除したつもりでも、捜査機関は高度な解析技術を有しているので、簡単にデータを復元できます。
データの復元の結果、証拠隠滅を図ったことが発覚すれば、逮捕や勾留の必要性判断において当然不利に扱われますし、起訴される可能性が高くなります。
盗撮に限った話ではありませんが、証拠隠滅を行ってもメリットは一切ありませんので注意しましょう。
逮捕された犯人をサポートできるのは家族や友人
盗撮事件の犯人が、処分軽減に向けて自らできることは自首くらいです。
いざ逮捕されてしまったあとにサポートできるのは、自分以外の家族や友人です。
お一人で悩みを抱え込まず、信頼できる弁護士に相談し、気持ちの整理をしながらこれからの方針を一緒に立てましょう。
裁判開始後に身柄を解放したいなら「保釈金」
盗撮犯人が起訴されて裁判が始まると、被疑者から被告人に変わります。
被告人の身柄は、裁判が確定するまでのあいだ、各都道府県の拘置所・拘置支所に収容されるのが慣例です。
ただし、裁判所に保釈金を納めれば、裁判確定前でも被告人の身柄を解放できる場合があります。
盗撮事件の保釈金額に明確な「相場」はありませんが、150~300万円位になることが多いです。
納めた保釈金は裁判が終わると返還されますが、保釈中に「証拠を隠滅した」「出頭要請に応じず裁判を欠席した」といった事情があると没収されてしまいます。
なお、保釈が認められるためには、しっかりとした身元引受人の存在が重要です。
裁判所に対して、身元引受人が被告人を厳しく監督することを約束すれば、保釈が認められやすくなるからです。
身元引受人になれる条件は特にありませんが、家族や信頼できる上司が良いでしょう。
適切な人物が見つからない場合、弁護士に依頼することも可能です。
盗撮の加害者になった身内をサポートしたい時は西船橋ゴール法律事務所へ
盗撮事件の加害者となってしまった場合、何もしないでいると逮捕・勾留・起訴される可能性が高くなります。
身柄拘束や起訴を回避するためには、刑事事件の経験豊富な弁護士にアドバイスをもらいながら、「捜査機関に対して真摯な反省の態度を示す」「被害者とすみやかに示談交渉する」といったポイントを実行することが肝心です。
「身内や知り合いが出来心で盗撮してしまった。今はまだ逮捕されていないけれど、いつ警察に逮捕されるかわからない……」
そんな不安に悩んでいるご家族や友人の方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。
盗撮事件の示談成功など刑事事件の実績に優れた弁護士が、不当な刑事処分で身柄拘束されないよう適切に対応します。
経済的な事情で弁護士費用を心配している方には、初回無料の法律相談や分割払いを用意していますのでご活用ください。
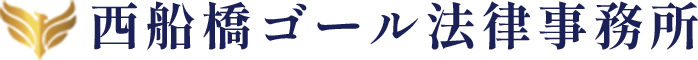


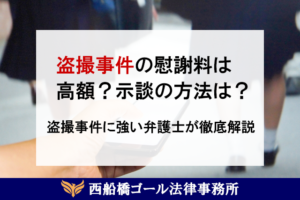
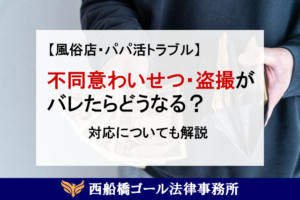
とは?これまでの法律とは何が違うの?逮捕されたり前科がつくの?-300x200.png)