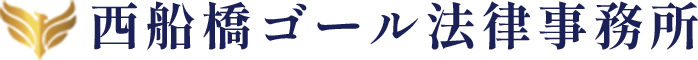逮捕されたらどうなるの?逮捕の必要性や逮捕後の流れについて解説
未分類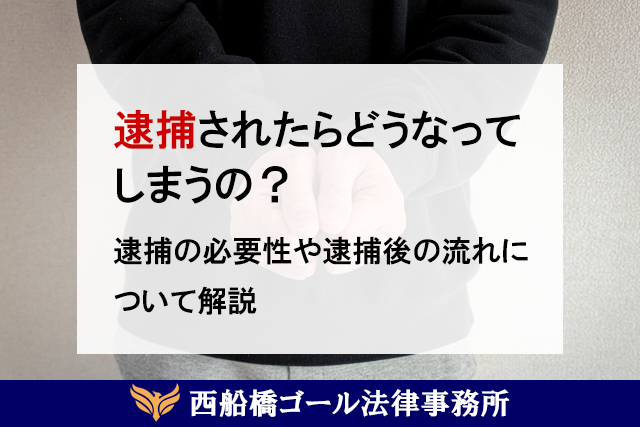
普段テレビやインターネットのニュースで容疑者が逮捕されたなどと報道されることがあります。
逮捕とはどういった手続きなのでしょうか?
また、逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか?以下、弁護士が解説していきたいと思います。
この記事でわかること
・逮捕とは何か
・なぜ逮捕されるのか
・逮捕された後の流れ
目次
逮捕とは何か?
テレビやインターネットのニュースで毎日のように容疑者が逮捕されたと報道されておりますが、この逮捕とはどういった手続きなのでしょうか。
逮捕を犯罪者に対する制裁であると誤解される方がおりますが、逮捕手続きの目的は犯罪者に対する制裁ではないのです。

赤井耕多
また、逮捕されたからといって、逮捕された方は必ずしも犯罪を行っているとは限りません!
それを前提に逮捕という手続きは法律上許されているのです。
逮捕の手続については、刑事訴訟法199条以下に規定されています。
逮捕の要件
捜査機関が逮捕をするには、刑事訴訟法199条で定められた要件が満たされなければなりません。刑事訴訟法199条の規定は以下のとおりです。
刑事訴訟法199条(逮捕状による逮捕)
第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
第2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察職員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本庄において同じ。)の請求により、前条の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項 検察官又は司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
このように刑事訴訟法199条1項には逮捕の要件が、同条2項には逮捕状発付の要件が定められています。
なぜ逮捕されるのか?
逮捕は、逮捕された者が罪を犯したか否かを捜査機関が捜査するために、被疑者の身柄を確保するための制度です。
ですので、逮捕された者が逮捕された時点で罪を犯したか否かは確定ではありませんし、逮捕されたものに対する制裁の意味合いもありません。
まず、刑事訴訟法上の「逮捕」とは、被疑者の身体を拘束して警察署や拘置所へ連れて行き、その効果として比較的短期間の留置を認めるものとされています。
そして、逮捕の要件として規定されている「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とは、特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があることとされています。
逮捕状の発付を求められた裁判官は、明白に逮捕が不要だと認められる場合に限り却下の義務があるとされており、それ以外の場合については、捜査機関の意向を尊重して逮捕状を発付しなければならないとされています。
その場合の逮捕の必要性の有無は、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重・態様その他諸般の事情を総合的に考慮し、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれの有無等によって判断されるとされています。
実務上、警察官が裁判所に対して逮捕状の発付を求めると、裁判所は基本的に逮捕状の発付をほとんどの場合で許可するようです。
なお、逮捕については、刑事訴訟法429条1項各号所定の準抗告(逮捕が決まったことに対する不服申し立てを意味します。)の対象となる裁判に含まれませんので、準抗告は許されません。
同じ犯罪事実について再度逮捕されることはある?
実務上、逮捕された被疑者の方は、逮捕後取調べを受けたものの嫌疑が不十分のため翌日に釈放されることがあります。
それでは、一度釈放された場合、同じ犯罪事実で再度逮捕されることはあり得るのでしょうか。
刑事訴訟法199条第3項の規定は、逮捕の不当な蒸し返しを防止するために通知義務を課したものといえます。
同一犯罪事実について2度以上逮捕状を請求することも、発付することも問題ないということになりますが、1度逮捕された後に釈放された被疑者を同じ犯罪事実で再度逮捕することは、特別な事情がない限り、前の逮捕の蒸し返しとして禁止されなければなりません。

川口晴久
実務上、同じ犯罪事実で逮捕されるケースは非常にまれだといえます。
逮捕されるとどうなる?逮捕後の流れ
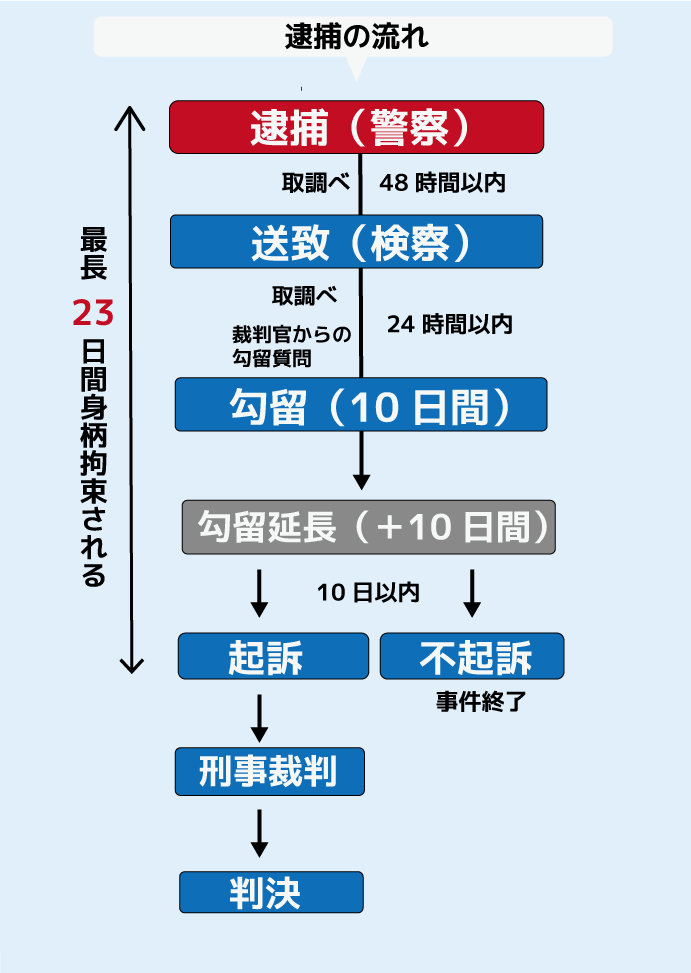
まずは留置場へ入れられる
まず、逮捕されると警察署内に設置されている留置場(又は留置施設)に入れられ、身体拘束をされることになります。
留置部屋については、一人部屋のときもあれば複数人が収容されている部屋の場合もあります。留置係から呼ばれる際は、基本的に定められた番号で呼ばれます。
留置場には、人が少ないときもあれば非常に多いときもあります。留置されている方が多いか否かは時期や留置されている警察署にもよります。
女性で逮捕されてしまった方は、逮捕された管轄の警察署ではなく、女性の収容を取り扱っている留置場に移されることが多いです。
警察による取調べ
警察署に逮捕された直後は、警察署内で取り調べが行われることが一般的です。
被疑者は、逮捕直後、すぐに警察からの取調べを受け、そこで身上経歴に関する話や逮捕の原因となった事実について話を聞かれます。その際に被疑者の弁解についても聞かれます。

赤井耕多
被疑者は、逮捕されると、警察署の留置施設の職員の方から、誰か一人に対して、現状を伝えることができると教えてもらえます。
当番弁護士と会うことが可能
逮捕後、当番弁護士への依頼を希望すると、弁護士会から単発の接見のために派遣された弁護士と会うことができます。
そこで、当番弁護士と接見をすることができれば、当番弁護士から、今後の捜査の流れや逮捕されている件についての見通し等を教えてもらえます。
場合によっては、被疑者は、当番弁護士に対して何らかのかたちで報酬を支払い依頼をすることが可能です。
もし、当番弁護士を依頼することになりましたら、被疑者は、まず初めに当番弁護士に対して、被疑者の身体拘束を解放してもらうための弁護活動を依頼することになります。
また、被疑者は、逮捕された当日に家族や親族、知人の方らと面会することができませんので、当番弁護士に対し、家族や親族らへの伝言などをお願いするとよいでしょう。
実務で多いのは、会社員等として仕事をしている方がお客さんや会社に対して、仕事の引継ぎ等の関係で、当番弁護士を通じ伝えるといったことが多くあります。
なお、被疑者は、持病があったり体調が悪かったりすると、病院へ連れていってもらえたりしますので、持病や体調不良については我慢することなく積極的に伝えるのが良いでしょう。
逮捕された翌日
逮捕された翌日は、そのまま警察署の留置場で過ごしながら取調べを受けるか、一日何もせずに過ごす場合もあります。

川口晴久
千葉県の場合ですと、逮捕された翌日は、基本的に留置場から検察官のいる検察庁まで護送車で移動することが多いです。
被疑者は、逮捕された後、48時間以内に検察官に対して送致(被疑者や捜査書類を送ることを意味します。)がされなければ、釈放されます。
そのため、千葉県の警察官は、基本的に逮捕後48時間以内である翌日に検察庁へ被疑者と捜査資料を送るのです。
検察での取調べ
検察へ移動する際の注意点
検察庁へ移動する場合は、基本的に警察官から前日の夜に、次の日の朝に検察庁へ行くことを伝えられます。
そして、検察庁へは、逮捕された翌日の午前9時前頃には、留置されている警察署を出発して検察庁へ護送車で移動することになります。
なお、被疑者が逮捕された日から報道機関に報道されているようなケースでは、検察庁へ移動する日の朝に被疑者が警察署から出て護送車に乗るタイミングで報道機関により被疑者の顔などを写真で撮られることがあります。
報道機関によるインターネット上のニュースはせいぜい2,3カ月で消えますが、そのインターネットニュースで使用された写真や記事の内容については、他のウェブサイトで転載されることがあり、その記事自体は半永久的に残ってしまいますので、なるべく護送車に乗るタイミングでは顔を上げず、下を向いて報道機関のカメラに写らないように移動するのがよいでしょう。
下を向いて護送車に乗ろうとすると周囲の警察官から顔を上げて歩くよう注意されるかもしれませんが、そのようなことを気にしていたら半永久的に自身の顔写真等ががインターネット上に残ってしまうので、警察の言うことに従わなくても良いでしょう。
取調べの内容や時間
検察庁に着くと、おおよそ午前中のうちに検察官からの取調べを受けることになります。
時間は長くて1時間程度となります。なお、黙秘する場合、検察官は取調べに1時間もかけずに、10分程度で取り調べを終了させることもあります。
取調べの際は、検察官のいる部屋へ入り、検察官と検察事務官の目の前で検察官から聞かれることに対して対応することになります。
検察官からは、警察官と同じような話を聞かれ、最後に話した内容の確認と書面への署名、指印を求められます。
取調べの時間配分としては、最初の30分で事件等に関する話を聞かれ、残りの30分で書類の作成に移ります。
検察官の取調べの結果、検察官より勾留(警察署や拘置所にさらに10日身体拘束されることを意味します。)の必要がないと判断された者は、検察官の終了後にほどなくして釈放されることになります。

赤井耕多
例えば、痴漢や自動車事故については逮捕後に勾留されず、検察官の取調べ後に釈放されるといったことが多くあります。
他方で、大半の被疑者は、検察官から勾留請求をされてしまいます。検察官は、刑事訴訟法上、24時間以内に裁判所に対して勾留請求をしなければ、被疑者を釈放しなければなりませんので、千葉県の検察官は、被疑者の取調べ後すぐその日のうちに裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求された後はどうなるの?
裁判官からの勾留質問を受ける
検察官が裁判所に対して勾留請求をすると、被疑者は、検察官から取調べを受けた後、今度は護送車で裁判所まで移動させられることになります。
裁判所まで移動させられた被疑者は、今後は裁判官から質問を受ける手続きを受けることになります。
裁判官は、検察庁から送られてきた記録を読み込み、被疑者に質問(勾留質問といいます。)した上で、被疑者を10日間の勾留にするか否かを決定します。
勾留されない場合もある
裁判官が被疑者を勾留決定しないと判断した場合は、その後ほどなくして被疑者は釈放されることになります。
なお、検察官の勾留決定にもかかわらず、裁判官が勾留請求を却下した場合、検察官は、場合によっては裁判官の勾留決定に対して不服申し立てをすることがあり、その不服申し立てが認められてた場合、被疑者は10日間の勾留が決まってしまいます。
他方で、勾留決定までの間に弁護士を就けておらず釈放のための活動をしていない場合、被疑者は、裁判所より、勾留決定を下され、10日間の勾留が決まってしまいます。
逮捕されたらすぐに弁護士に相談しよう
逮捕後、刑事手続はどんどん進んでいく
東京では、被疑者は、千葉県と同じように逮捕された次の日に検察庁へ送致されます。もっとも、検察官から勾留請求がされると、裁判官の勾留質問が開かれるのは、検察官の取調べの次の日となります。
他方で、千葉県では、逮捕された次の日に、勾留請求も勾留質問も行われてしまいます。イメージとしては、逮捕された翌日の午前中に検察官の取調べ、午後に裁判官による勾留質問となります。
早く弁護士に相談するメリット
逮捕された当日や逮捕された次の日の午前中のうちに弁護士に依頼をすれば、釈放のための弁護活動に着手してもらえます。
そして、事案によっては弁護士に身柄解放のための依頼をすることで逮捕翌日に釈放してもらえるケースが多くあります。

川口晴久
会社員の方が逮捕された場合も、翌日に釈放されれば、会社に逮捕の事実が発覚しなかったりするなど社会的なダメージを低く抑えることができます。
いったん勾留決定が下されてしまいますと、10日間は警察署等に身体拘束されることになり不利益が大きいです。
そして、勾留決定に対する不服申し立てが通る確率は、勾留を阻止できる可能性よりは低いように思えます。
逮捕されそうな方であれば、あらかじめ弁護士に依頼し逮捕された後の活動を綿密に打ち合わせし身柄解放のための依頼をし、既に逮捕されてしまった方については、勾留決定を阻止するための活動を弁護士に依頼するのがよいでしょう。
刑事事件で不安な方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所までお気軽にご相談ください。

法政大学法学部卒業
学習院大学法科大学院修了
アトム法律事務所
アトム市川船橋法律事務所
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
所属:千葉県弁護士会