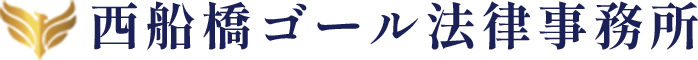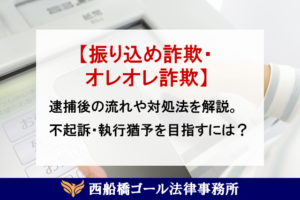【詐欺の受け子とは】初犯でも実刑になる可能性あり!量刑や逮捕事例を紹介します
特殊詐欺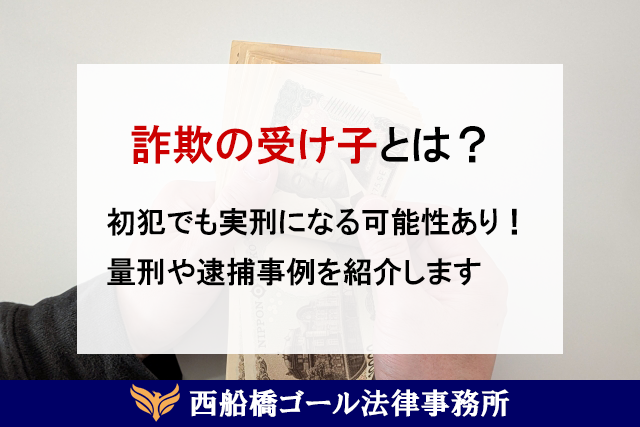
特殊詐欺を行い被害者を騙す手口は巧妙化しています。
その中でも「受け子」と呼ばれる人は、組織の末端でありながら詐欺の実行役であり、そして、実際に被害者宅などに出向いて金品を受け取るため、逮捕されるリスクが非常に高い存在です。
詐欺の受け子は、仮にそれが犯罪だと知らなかったとしても詐欺罪に該当する可能性があります。
そして、特殊詐欺の実行役として、逮捕されれば初犯であっても実刑判決を受ける可能性があります。
この記事でわかること
・詐欺の受け子がどのような犯罪になるのか
・適用される可能性がある法律
・量刑
・実際の逮捕事例
・詐欺犯罪に関与しないための注意点
目次
詐欺の受け子とは?特殊詐欺の受け子について
オレオレ詐欺などの特殊詐欺では「受け子」とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、特殊詐欺の手法について解説します。
受け子とは何か?
「受け子」とは、特殊詐欺グループの指示の元に、被害者から現金やキャッシュカードを実際に受け取る役割をしている人です。
特殊詐欺には「振り込め詐欺」「還付金詐欺」などがあり、主に情報弱者になりやすい高齢者が狙われていると言われています。
特殊詐欺の受け子は組織の末端に位置していたり、場合によってはアルバイトとして雇われていたり、個別に依頼をうけていたりするケースもあります。
ですが、当然、受け子も詐欺という犯罪に加担しているわけであって、法的には重大な犯罪行為となります。

川口晴久
詐欺罪は刑事事件になるため、逮捕される可能性がありますし、その後の裁判では厳しい処罰が科せられることになります。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺)とは?
振り込め詐欺(オレオレ詐欺)は、犯人が家族や警察官、銀行などになりすまして、「お金が必要」と信じ込ませて騙し取るというものです。
受け子は、被害者と接触して現金を直接受け取るケースも珍しくありません。つまり詐欺の実行犯ということです。
還付金詐欺とは?
還付金詐欺は、税務署、市役所、銀行などになりすまして「還付金がある」と嘘をついてあたかもお金が貰えるかのようなやり方で実際に騙してお金をATMで送金させるという詐欺です。
特に、高齢者が狙われることが多く、電話を利用するケースもあります。
受け子は逮捕される!法的責任と実刑判決の可能性
特殊詐欺の受け子は、詐欺グループの中心的な存在ではありません。
組織の末端であったり、アルバイトであったりするケースが多いです。

赤井耕多
場合によっては自分が詐欺の受け子であると認識していないケースもあります。
だからといって、詐欺の受け子の違法性がなくなってしまうわけではありません。
詐欺の受け子は犯罪であり、逮捕される可能性が最も高いとも言えます。
詐欺罪は刑事事件として取り扱われることになりますので、逮捕や勾留の可能性もあります。
詐欺の受け子に適用される可能性がある法律
作業の受け子に対して適用される可能性がある犯罪は以下が考えられます。
受け子に適用される犯罪
・刑法246条第1項 詐欺罪
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)
詐欺罪

川口晴久
詐欺罪と聞くと、刑法の詐欺をイメージする方が多いかと思います。
確かに、受け子が逮捕された場合に適用される犯罪としては、刑法の詐欺罪の適用がある可能性が高くなります。
刑法第246条第1項の詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」ときに成立します。
つまり、受け子が、被害者から現金やキャッシュカードを受け取った時点で詐欺罪が成立します。被害者から振り込まれた現金をATMで引き出した場合も同様です。
また、詐欺は未遂であっても処罰の対象となるため、実際に金銭を受け取る前であっても、逮捕・起訴される可能性があります。
組織犯罪処罰法
組織犯罪処罰法は、「組織的な犯罪」に対して適用される法律です。
受け子を有するような詐欺は単独犯ではなく2人以上で行われる組織的な犯罪であるケースが多く、場合によっては組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が適用される可能性があります。
第3条に規定される「組織的詐欺罪」が適用された場合、受け子も厳罰に処されることになります。
いずれにしても、詐欺の受け子が刑事事件に該当する犯罪行為であることは間違いありません。

赤井耕多
詐欺は親告罪ではないため、被害者が被害届けを出していなくても逮捕されることになります。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第3条|e-Gov法令検索
詐欺罪の量刑と時効
詐欺罪に関する刑罰は、刑法で規定されています。
受け子が逮捕される特殊詐欺の場合、計画性や組織性が問題視されて初犯であっても厳しい刑が科されるケースがあります。
また、詐欺罪には未遂罪の適用があるため、途中で行為を中断しても罪に問われることがあります。
ここからは、詐欺罪の具体的な量刑や未遂罪の適用、時効の詳細について解説します。
詐欺罪は「10年以下の懲役」
詐欺罪の量刑は10年以下の懲役です。
量刑は裁判所による判決で確定します。
その際には、被害額、詐欺の手口、共犯関係の有無、被害者の人数、反省の態度があるかなどが考慮されます。
特に、特殊詐欺のように計画性があり、被害額が大きい場合や、社会に与えた衝撃や影響、被害が大きい場合は実刑判決が下る可能性が高くなります。
また、刑期に関しては、被害の程度や金額、常習性などで異なります。
詐欺は未遂でも刑事事件として処罰される
詐欺罪には「未遂罪」が適用されます。
未遂罪とは刑法第43条のルールです。受け子をしていた人が犯行の途中で怖くなって「やっぱり辞めておこう」と行為を中断しても、未遂罪に問われる可能性があるということです。

川口晴久
「被害者から現金を受け取る前に怖くなって逃げた」場合でも、詐欺の未遂罪が成立するかもしれないということです。
実際に、受け子が未遂罪に問われたケースがあります。
2022年に「金融庁職員になりすまして高齢者宅に向かっていた最中に警察の尾行に気づいて現金を受け取りを中止した」というケースがありました。
この事件では、容疑者は被害者の自宅まであと140メートルというところまで来ていました。
この事例では、途中で断念したためお金は受け取っていませんが、窃盗の未遂罪が成立しています。
参考:読売オンライン
詐欺罪の時効
詐欺罪の公訴時効は7年です。
つまり7年を過ぎて時効が成立すれば刑事事件として起訴ではなくなるため捜査も行われず、逮捕されなくなるということです。
ただし、時効には停止する条件があります。成立する前に逮捕・起訴された場合は、時効が中断しますし、外国に滞在していた期間は時効期間に換算されません。
複数の人間が関わっていることが多い特殊詐欺の場合、共犯者が逮捕されて供述するなどして、時効完成前に逮捕されるケースもあります。
詐欺の受け子は初犯でも実刑になる可能性がある
ここまで紹介してきたとおり、詐欺の受け子をして逮捕・起訴された場合には、初犯であっても実刑になる可能性があります。
特に特殊詐欺は、高齢者をターゲットにして組織的に行われる犯罪であり、反社会勢力との繋がりも問題視されていることから、犯行が悪質であると判断される可能性が高くなります。
また、詐欺グループからの指示で、実際に金銭を受け取りに行く受け子は詐欺の実行役とされます。
組織内では末端やアルバイト的な立ち位置であることが多いのですが、受け子がいなければ犯罪が完成しないという重要なポジションでもあるのです。
そのため、初犯であっても、実刑判決が下されるケースが多く、執行猶予がつかない事例も決して珍しくありません。
実際の逮捕事例は?実刑になっている人が多いのか
逮捕事例
受け子の逮捕事例としては、「オレオレ詐欺で500万円をだまし取った受け子が逮捕された事例」や「警察になりすまして通帳をだまし取った事例」など多くの逮捕事例事例があります。

赤井耕多
受け子は現場に直接足を運ぶ役割であるため、遠隔で指示を出す人よりも逮捕されやすいのも事実です。
詐欺は重大な犯罪であり、アルバイト感覚の受け子であっても関わると必ず逮捕される日がきますので、絶対に犯罪に手を染めないようにしましょう。
詐欺の起訴率
法務局が公表している2023年検察統計年報によると、詐欺罪の起訴率は49.1%となっています。
日本では、起訴された場合は99%が有罪判決を受けると言われています。不起訴になるケースがないわけではありませんが、詐欺で逮捕された人の約半数が起訴されているのが事実です。
そして、同調査の2022年版では詐欺罪で起訴された人の約半数が初犯でした。
つまり初犯だから「不起訴になる」というわけではないのです。
加えて、令和3年版 犯罪白書 第5章 第3節 科刑状況では、受け子や出し子の54.9%が実刑であったことがわかっています。つまり、受け子や出し子の半数以上が、刑事裁判で執行猶予がつかない実刑判決を受けて刑務所に入っているのです。
このように詐欺の受け子は、初犯であっても起訴されて刑事裁判で裁かれる確率が高く、執行猶予がつかない実刑を受ける可能性も決して低くないことがわかります。
参考:令和3年版 犯罪白書 第5章 第3節 科刑状況|法務省
2023年検察統計年報|法務省
2022年検察統計年報|法務省
実刑と執行猶予は大きな違いがある
実刑判決であっても、執行猶予付きであっても有罪であるという事実は同じです。
ですが、実際には大きな違いがあります。
起訴されると被疑者から被告人となって刑事裁判で実刑判決を受けるわけですが、実刑判決を受けると、刑務所に決められた期間収容され、刑務所内で自由がない厳しい生活を送ります。
一方で、執行猶予がついた場合は、すぐに収監されることはなく、執行猶予の期間を問題なく過ごせば刑務所に入れられることはありません。
実刑判決ではないということは、本人や家族にとって極めて重要なのです。
また、実刑判決を受けた後、刑期を終了して社会復帰しても「前科がある」という過去を一生背負うことになります。

川口晴久
もちろん、受け子をして逮捕された場合でも弁護士をつける権利は保証されています。
うっかり特殊詐欺の受け子をしないように
詐欺の受け子の中には「アルバイト感覚でうっかり」というケースもあります。
実際に、どのような犯罪なのかを本人が解っていないということもあるようです。
ですが、受け子をするということは、知らなかったでは済まされない大きな犯罪に加担しているのです。
「知らなかった」では済まされない
特殊詐欺の受け子をしてしまった場合、「私は何も知らなかった」は理由にならず、当然それでは済まされません。
仮に、本当に犯罪であることを知らなかったとしても、罪に問われる可能性があります。
そして、アルバイトだと思っていたとしても、詐欺という重大な犯罪に関与して実行したという事実が消えるわけではありません。
警察の取り調べでは、「知らなかった」や「指示されたからその通りにやっただけ」と言ったとしても、それで許されるということはないでしょう。
特殊詐欺の受け子をして逮捕されたというだけでも社会的な影響は小さくありませんが、仮に実刑となって刑務所に行くことになれば、家族や職場にも大きな影響を与えます。
また、被害者の財産を奪ってその後の人生を大きく狂わせてしまうことになります。
特殊詐欺グループや闇バイトなどには絶対に関わらないようにしましょう。
SNSでの甘い誘い文句に注意
SNSなどで「誰でもできる」「すぐに現金が手に入る」「短時間で大金を稼げる」といった甘い文句で受け子を募集しているというケースがあります。
いわゆる「闇バイト」というものですが、これはアルバイトなどではなく犯罪行為です。
当然、関わっても何のメリットもありません。
そして、違法だと解っていなくても共犯と見なされるケースがありますし、前述したとおり「犯行の途中でやめても未遂罪になる」ことがあります。
詐欺の受け子をするということは、人からお金や財産をだまし取って相手の人生を大きく狂わせるその片棒を担ぐということです。ですので、どんなに高額報酬で依頼されても絶対に関わってはいけません。
万が一、闇バイトの勧誘にあって脅迫されたり強要されていたりする場合は、警察や弁護士に相談しましょう。
受け子をして逮捕されてしまったらどうする?
万が一、受け子をしてしまって逮捕・勾留された場合はどのように対応すれば良いのでしょうか。
まず、逮捕された場合は捜査に協力しましょう。
そして、弁護士に連絡をして接見をするなど、自分に認められている権利を行使しましょう。

赤井耕多
家族との面会はできないケースがほとんどですが、弁護士との接見は権利として保障されています。
逮捕後の流れ
逮捕後の流れとしては、事情聴取等のあとに送検されるかどうかが決まります。
そして、検察官が起訴もしくは不起訴かを決定します。起訴されれば、刑事裁判で裁かれることになります。
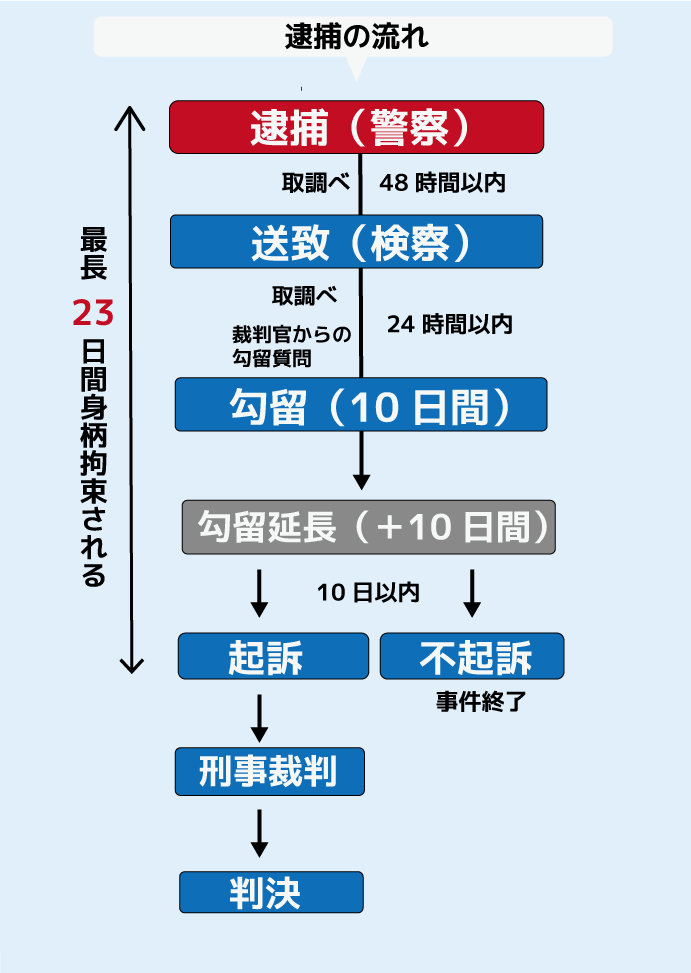
弁護士に依頼する費用がない場合は、当番弁護士という制度を1回限りで無料で利用できます。
まとめ
特殊詐欺の受け子は詐欺グループの末端であり、組織の実態を知らないケースも少なくありません。
ですが、詐欺という犯罪行為に直接関わって実行する役割であり、犯罪です。
また、受け子は実際に被害者の自宅に出向くなどして接触するため、逮捕される可能性が非常に高いポジションです。「私は何も知りませんでした」と言っても、犯罪に加担した事実はなくならないのです。
詐欺は重大な犯罪であり、受け子が初犯であっても実刑判決が下されることがあります。特に組織的な詐欺に関わっていると判断された場合は、執行猶予がつかず実刑になる可能性が高くなります。
受け子の逮捕事例や量刑の実態を知ることで、この犯罪の重大さを理解し、決して関与しないよう注意が必要です。
詐欺の受け子は、闇バイトのようにSNSで募集しているケースがあります。
「簡単な仕事」「高収入」といった言葉でお金に困っている人や情報弱者を受け子にして犯罪が行われています。このような犯罪グループと関わると抜け出すのが難しくなり、実際に詐欺に加担すると逮捕されるリスクも高まります。
もし怪しい勧誘を受けた場合は、すぐに警察に相談し、犯罪に巻き込まれないよう十分に注意しましょう。
詐欺関連でお困りの方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所までご相談ください。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業 平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 学習院大学法科大学院修了 平成27年9月 司法試験合格 アトム市川船橋法律事務所 令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業 所属:千葉県弁護士会