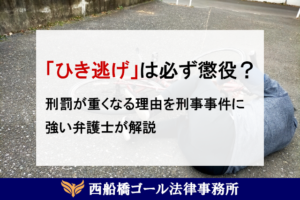【危険運転の罰則は?】危険運転致死傷罪やあおり運転が適用される行為を解説
過失運転致傷・ひき逃げ・当て逃げ
危険運転には8種類もの行為があり、罰則は厳しいものです。なぜなら、危険運転は他の道路利用者の生命を脅かす重大な違法行為だからです。
この記事では、危険運転致死傷罪やあおり運転が適用される具体的な行為と罰則、通報された場合の対応、危険運転に遭遇した際の適切な対処法を解説します。

赤井耕多
危険運転は絶対に行ってはいけません。罰則は非常に厳しく、最悪の場合、懲役刑に処される可能性もあります。
目次
危険運転とは、あおり運転を含む人を死傷させる運転
危険運転とは、酒や薬物の影響下での運転、著しい速度超過、あおり運転など、他の道路利用者の安全を著しく脅かす悪質な運転行為を指します。
これらの行為は、重大な事故につながる可能性が高いため、法律で厳しく規制されています。
危険運転の特徴は、その行為自体が罰則の対象となる場合があること、人身事故を起こした際に「危険運転致死傷罪」が適用される点です。
危険運転によって人を
①負傷させた場合→「危険運転致傷罪」
②死亡させた場合→「危険運転致死罪」に該当します。
また、近年社会問題となっているあおり運転も危険運転の一種として扱われます。

川口晴久
あおり運転は、人身事故の有無に関わらず「妨害運転罪」として罰則の対象です。
危険運転は、他者の生命を脅かす重大な違法行為であり、その罰則も非常に厳しいものとなっています。
危険運転致死傷罪:悪質な危険運転による人身事故に適用
2014年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)が施行され、危険運転致死傷罪が規定されました。
この罪は、アルコールや薬物の影響下での運転、著しい速度超過、赤信号無視などの悪質な運転行為によって人を死傷させた場合に適用されます。
危険運転致死傷罪の適用は、運転者の行為が他者の生命を著しく危険にさらしたことを重く見た結果であり、交通安全への警鐘となっています。
危険運転に該当する行為は8種類
危険運転に該当する行為は、自動車運転死傷行為処罰法第2条で明確に規定されています。
人命を脅かす可能性が高い8種類の危険な運転行為が該当します。
アルコールや薬物の影響下の運転(酩酊危険運転)
アルコールや薬物の影響下での運転は、危険運転の中でも特に重大な違反行為です。
「酩酊危険運転」とも呼ばれます。
アルコール類の摂取による酩酊状態や、覚せい剤などの薬物使用による幻覚状態など、正常な運転が困難な状態での自動車運転が該当します。
ただし、飲酒運転が全て危険運転に該当するわけではありません。
判断基準は、摂取したアルコールや薬物の種類と量、酩酊や幻覚の程度、摂取からの経過時間などを総合的に考慮します。
例えば、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上の場合、酒気帯び運転として免許が取り消されますが、これだけでは必ずしも危険運転には該当しません。
ですが、この状態で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用される可能性が高く、罰則も厳しくなります。
安全運転の観点からも、飲酒や薬物使用後の運転は絶対に避けるべきです。
参考:警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」
制御困難な高速の運転(速度超過)
自動車を制御できないほどの高速度で走行する行為は、危険運転の典型例として自動車運転処罰法で規定されています。
この場合、単に速度違反をしただけではなく、その車両や道路状況において「制御困難」と判断される速度での運転が該当します。
特徴的なのは、「時速何キロ以上」という一律の基準が存在せず、道路形状や交通状況、天候条件などを総合的に考慮して判断される点です。
直線道路では安全に走行できる速度でも、急カーブや交差点、混雑した市街地では「制御困難」とみなされることがあるため、状況に応じた適切な速度での運転が求められます。
制御する技能がない運転(運転技量不足)
自動車の基本操作や交通ルールを理解せず、車両を制御する技能を持たないまま運転する行為は、自動車運転処罰法で危険運転として規定されています。

赤井耕多
一般的には無免許運転がこれに該当する可能性が高いとされています。
しかし、法的判断においては単に免許を持っていないことだけでなく、実際の運転技能の有無が重視される点に注意が必要です。
免許は失効していても長年の運転経験がある場合、「技能を有しない」とは認められにくいことがあります。
逆に、免許を取得したばかりでも、技能不足で制御できない状態での運転は危険運転に該当する可能性があるでしょう。
悪質な接近・急進入による通行妨害行為
他者の通行を妨げる意図で、人や車に極端に近づいたり前方に突然入り込んだりする行為は、危険運転の代表的な形態です。
このような運転は深刻な事故を引き起こす可能性があるため、厳格に規制されています。
歩行者への異常な接近や、走行車両の目前への意図的な割り込みなどがこれに該当し、特に速度が速いケースでは危険度が格段に上昇します。
昨今問題視されている「あおり運転」もこのカテゴリーに分類され、その深刻さから2020年6月の道路交通法改正で「妨害運転」という違反として罰則化されました。
この種の運転行為は単なる交通違反を超え、道路利用者全体の生命の安全に直接的な脅威をもたらす行動です。
前方での危険な妨害行動と急接近行為
走行車両の通行を意図的に妨げる目的で前方に位置を取り、急停止やつきまとう行為は、危険運転行為に分類されています。
他車が速度を出している状況下で、意図的に進路を遮る急ブレーキや極端な車間距離の縮小が該当します。
全停止に至らなくとも、安全運転を脅かす状況を意図的に作り出す行動は危険運転とみなされる可能性が高いです。
こうした行為は「あおり運転」の一類型として社会に認識されており、法改正によって「妨害運転」として罰せられるようになりました。
追突事故は高いリスクを伴い、深刻な人的被害につながる恐れがあるため、事故発生の有無を問わず法的措置の対象となります。
高速道路における悪質な強制停止行為
高速道路を走行する車の前方で突然停車したり極端に接近して停止を強いる行為は、危険運転行為の中でも特に悪質なケースです。
高速道路や自動車専用道路など高速走行が前提の道路環境では、急な速度低下や停止行動が極めて危険な状況を生み出します。
他車の走行妨害を意図して前方車両に対し強制的な停止を促したり、異常な接近で減速を余儀なくさせたりする行動は、その速度に関係なく危険運転行為として認定されます。
高速道路上での妨害行為は連鎖的な事故を誘発しやすく、複数車両を巻き込む大事故へと発展する可能性が高いため、実際に衝突事故が発生していなくても処罰対象となりやすいでしょう。
意図的な信号無視と高速走行の危険性
故意の赤信号無視と高速走行を組み合わせた運転行為は、代表的な危険運転行為です。
法律上、赤色信号を「わざわざ」無視する意図と「交通安全に深刻な脅威を与える速度」での走行という2つの要素がそろった場合に、この違反が成立します。
単純な見落としによる信号無視や、低速での通過は該当しない点が重要です。

川口晴久
この違反の適用には故意性と速度という両面の要件が必須となります。
赤信号を明確に認識しながら高速で交差点に突入するような行動が、この規定が想定する典型的な違反行為といえます。
このような運転は交差点における致命的な衝突リスクを著しく高め、周囲の道路利用者の命を危険にさらす極めて悪質な行為です。
通行禁止道路を進行し高速度の運転(通行禁止無視)
通行禁止道路を進行し高速度で運転する行為は、危険運転として厳しく規制されている行為です。
道路標識や道路標示によって明確に通行禁止が示されている道路、または法令によって通行が禁止されている道路や区間を、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為が該当します。
車両進入禁止の標識がある道路や、歩行者専用道路を高速で走行するケースが挙げられます。
この種の危険運転は、予期せぬ場所に車両が進入することで、歩行者や他の道路利用者に重大な危険をもたらす可能性が高いです。
特に高速度での走行は、突発的な状況への対応が困難になり、事故の危険性を著しく高めます。
危険運転による罰則
危険運転による罰則は以下の3つが挙げられます。
危険運転による罰則
①危険運転致死傷罪
②準危険運転致死傷罪
③妨害運転(あおり運転)
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法第2条に規定される犯罪です。
危険運転致死傷罪は、危険な状態で自動車を運転し、結果として人を死傷させた場合に適用されます。
具体的には、アルコールや薬物の影響下での運転、著しい速度超過、運転技能不足、あおり運転などの危険行為により人身事故を起こした場合です。
罰則の厳しさは、事故の結果によって異なります。
| 被害者が死亡した場合 | 1年以上20年以下の有期懲役 |
| 被害者が負傷した場合 | 15年以下の懲役 |
| 無免許運転の場合 | 刑が重くなり、負傷事故でも6カ月以上20年以下の有期懲役 |

赤井耕多
危険運転致死傷罪の特徴は、罰金刑がなく懲役刑のみが定められていることです。
準危険運転致死傷罪
準危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法第3条に規定される犯罪です。
この罪は、正常な運転に支障が生じる「おそれがある」状態で人身事故を起こした場合に適用されます。
アルコールや薬物の影響、または特定の病気により、正常な運転能力が低下している可能性がある状態での運転が該当します。

川口晴久
危険運転致死傷罪との違いは、運転者の状態が「正常な運転ができない」ではなく「おそれがある」という点です。
罰則の内容は事故の結果によって異なります。
| 被害者が死亡した場合 | 15年以下の懲役 |
| 被害者が負傷した場合 | 12年以下の懲 |
| 無免許運転の場合 | ・死亡事故では6カ月以上20年以下の有期懲役 ・負傷事故では15年以下の懲役 |
準危険運転致死傷罪の特徴は、危険運転致死傷罪よりも若干軽い刑罰が定められていることです。運転者の状態が「おそれがある」という不確実性を考慮したものといえます。
妨害運転(あおり運転)
妨害運転(あおり運転)は、2020年6月の改正道路交通法施行により、新たに厳しい罰則が設けられた危険運転の一形態です。
妨害運転の罰則は、その行為の危険性によって2段階に分けられています。
まず、交通の危険の「おそれがある」行為には、急ブレーキや著しい接近などが含まれます。
一方、実際に交通の危険を生じさせた場合、例えば高速道路上で他車を停止させたり事故を引き起こしたりした場合は、より重い罰則が適用されます。
刑罰は下表の通りです。
| 交通の危険の「おそれがある」行為 | ・違反点数25点の加算(免許取消2年) ・累積点数によっては、欠格期間が最長5年に延長される可能性あり | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 実際に交通の危険を生じさせた場合 | ・違反点数35点の加算(免許取消3年) ・前歴や累積点数によっては、欠格期間が最長10年まで延長される可能性あり | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
危険運転を受けた際の対処法
危険運転を受けた際の対処法は次の3つです。
危険運転の対処法
①相手から離れ安全な場所へ避難
②ドアや窓を開けず車内で退避
③警察に通報し相手の車や被害状況を動画撮影

赤井耕多
自分の身の安全を守るため確認しましょう。
相手から離れ安全な場所へ避難
危険運転、特にあおり運転を受けた際の最優先事項は、自分自身の安全確保です。
まず、冷静さを保ちながら以下の対応を心がけましょう。
| 速度を落とし車間距離を広げる | 相手の挑発に乗らず、むしろゆっくりと減速し、安全な車間距離を確保します。 |
| 安全な場所へ移動 | 一般道なら人通りの多い場所や交番付近、高速道路ではサービスエリアやパーキングエリアに避難します。 |
| 無理な逃走は避ける | スピードを上げて逃げようとすると、かえって危険な状況を招く可能性があります。 |
| 周囲の状況を確認 | 安全に車線変更や退避ができるか、常に周囲の交通状況に注意を払います。 |
冷静な判断と適切な行動で、危険な状況から速やかに脱することが重要です。
ドアや窓を開けず車内で退避
相手が車外に出てきても、決してドアや窓を開けてはいけません。
以下の対応を心がけましょう。
| 車内にとどまる | 車外に出ることで直接的な暴力を受ける危険性が高まります。 |
| ドアと窓を確実にロック | 外部からの侵入を防ぎます。 |
| 相手の挑発に応じない | 話しかけられたり怒鳴られたりしても、無視して冷静さを保ちます。 |
| 周囲に注意を喚起 | 必要に応じてクラクションを鳴らすなどして、周囲の人々の注意を引きます。 |
身の安全が保てないと感じたら、以下のように警察に連絡します。
警察に通報し相手の車や被害状況を動画撮影
危険運転する車から安全な距離を確保できたら、速やかに警察へ通報しましょう。
通報の際は、危険運転の状況、相手車両の特徴(車種、色、ナンバー)などを可能な範囲で伝えます。
指示された場所で警察の到着を待ちましょう。
通報先は110番のほか、警察本部の相談窓口「#9110」も利用できます。相談窓口は、危険運転の判断が難しい事例や緊急性の低い相談にも対応しています。

川口晴久
証拠確保のため、スマートフォンやカメラで相手車両や威嚇行為の様子を撮影することも有効です。
ただし、必ず安全な場所に停車してから撮影しましょう。
全方位撮影が可能なドライブレコーダーがあれば、運転中の状況も記録でき、自身の無実も証明しやすくなります。
【2023年】危険運転致死傷罪の適用件数
2023年における交通事故の罪種別検挙件数・人数は下表の通りです。危険運転致死は減少傾向ですが、危険運転致傷は検挙件数・人数とともに年々増加しています。
| 法2条・3条の別※ | 罪種 | 件数 | 人数 |
| 法2条 | 危険運転致死 | 26件 | 26人 |
| 法2条 | 危険運転致傷 | 425件 | 421人 |
| 法3条 | 危険運転致死 | 7件 | 7人 |
| 法3条 | 危険運転致傷 | 279件 | 278人 |
(※自動車運転死傷処罰法)
参考:警察庁「年次別 交通事故事件 罪種別 検挙件数及び検挙人員」
【まとめ】危険運転の罰則は厳しい!なるべく早く弁護士に相談しよう
危険運転による罰則の種類は3つあります。
危険運転致死傷罪と準危険運転致死傷罪では、いずれも無免許運転の場合には、刑が重くなります。
妨害運転(あおり運転)は、2020年6月の改正道路交通法施行により、新たに厳しい罰則が設けられました。前歴や累積点数によって、欠格期間が延長される可能性があります。
危険運転を引き起こしてしまったら、弁護士への相談が必要です。
適切な相談の時期を逃すことがないよう、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所まですぐにお問い合わせください。

法政大学法学部卒業
学習院大学法科大学院修了
アトム法律事務所
アトム市川船橋法律事務所
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
所属:千葉県弁護士会
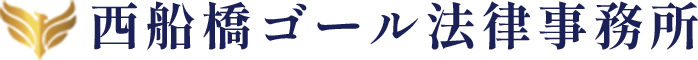
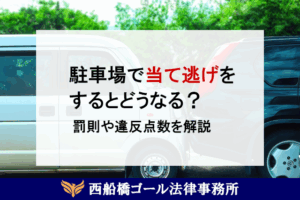
をしたら逮捕される?刑罰の重さは?-300x200.png)