「ひき逃げ」は必ず懲役?刑罰が重くなる理由を刑事事件に強い弁護士が解説
過失運転致傷・ひき逃げ・当て逃げ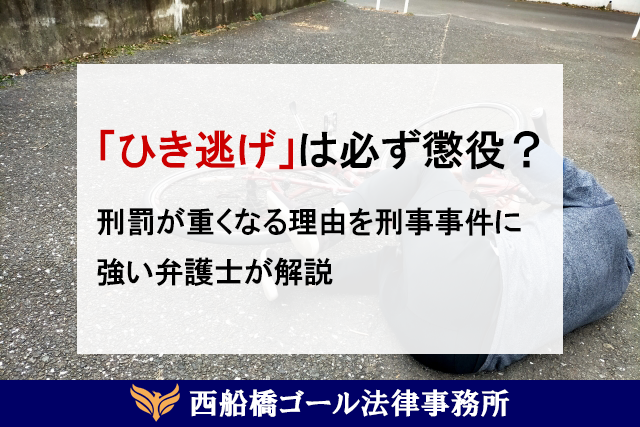
車を運転してひき逃げ事故を起こし逮捕されるとどんな罪になるか?
成立する犯罪名と刑罰は?
運転者の救護・報告義務、危険運転の具体例、ひき逃げが懲役刑になりやすい理由を刑事事件に詳しい専門弁護士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・ひき逃げとはどんな犯罪か
・ひき逃げ事件の刑罰はなぜ重いのか
・ひき逃げで捕まった場合、刑を軽くする方法はあるか
目次
「ひき逃げ」は2つの法律に違反する犯罪
ひき逃げとは
交通事故で他人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合に、被害者を助ける行動を取らずに現場から離れてしまうことを、「ひき逃げ」と言います。
・自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)
・道交法(道路交通法)
この2つの法律に違反する複合的な犯罪であることが、ひき逃げの大きな特徴です。
(自動車運転処罰法違反の犯罪)
・過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)
・危険運転致死傷罪(同法第2条・第3条)
(道交法違反の犯罪)
・救護義務違反(道路交通法第72条1項前段)
ひき逃げは、人身事故(上記1または2)を起こした加害者が、事故で負傷した被害者を助けるために救急車を呼ぶなどの救護活動を行わずに現場から立ち去った(上記3)場合に成立します。

川口晴久
したがって、過失運転致死傷や危険運転致死傷だけでは、ひき逃げは成立しません。
ここからは、ひき逃げを構成する各犯罪の内容と法定刑について説明していきます。
ひき逃げと当逃げの違い
ひき逃げとよく似た言葉に「当て逃げ」があります。
「ひき逃げ=人身」「当て逃げ=物損」
当て逃げとは、事故を起こした当事者が、道路上の危険を防止する措置(飛散した物を除去する、後続車に事故発生を知らせる等)を取ることなく現場から立ち去ったケースをさします。
ひき逃げと同様に、当て逃げも道交法第72条1項で規制されていますが、ひき逃げは人身事故であるのに対し、当て逃げは物損事故である点に違いがあります。
ひき逃げをすると懲役になる可能性が高い
ひき逃げの加害者になると懲役になる可能性が高いです。
懲役になりやすい理由
・ひき逃げをすると複数の犯罪が成立する
・法定刑が厳しく定められている
・危険運転致死傷罪が原因となりうる
・逮捕や有罪判決を免れる手段がほぼない
ひき逃げを構成する犯罪の内容・法定刑
過失運転致死傷罪
運転中の過失(うっかり、不注意)が原因で事故を起こし、人を死傷させる行為は、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)に該当します。
過失運転致死傷罪の法定刑は以下のとおりです。
- 7年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金(被害者が軽傷のときは情状により刑の免除も可)
特徴は、懲役ではなく禁錮とされる場合があることと、情状酌量で刑が免除される場合があることです。
危険運転致死傷罪
危険な運転が原因で事故を起こし、人を死傷させる行為は、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条・第3条)に該当します。
危険運転致死傷罪の法定刑は以下のとおりです。
・危険運転致死罪:1年以上20年以下(または15年以下)の懲役
・危険運転致傷罪:15年以下(または12年以下)の懲役
法定刑が1つのパターンしかない過失運転致死傷とは異なり、行為や結果の悪質性により法定刑の上限下限が変わることが特徴です。
また、禁錮や罰金がなく懲役のみであり、情状酌量による刑の免除もないため、懲役刑で処断されるのが原則ですが、執行猶予がつく可能性はあります。
危険運転の具体例
危険運転でひき逃げを起こすと、過失運転の場合よりもはるかに罪が重くなるため、懲役の可能性が高まります。
危険運転の具体例
・アルコールや薬物のせいで正常な判断ができない状態で運転した
・自動車の進行を制御するのが難しいほどの高速度で運転した
・自動車をコントロールできるだけの技能がないのに運転した
・人や車の通行を妨害する目的で、進入・停止・接近などのあおり運転をした
・信号無視をしながら危険な速度で運転した
・車両通行禁止の道路に進入し、危険な速度で運転した
・病気のために正常な運転が難しいにもかかわらずあえて運転し、人を死傷させた
救護義務違反
過失運転または危険運転で人身事故を起こした当事者は、直ちに運転を停止して救急車を呼ぶなど、事故で負傷した人を救護することが義務づけられています。(道交法第72条1項前段)
救護義務違反だけを犯した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。(道交法第117条1項)
しかし、ひき逃げは人身事故であり、被害者が負傷・死亡しているため、法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(道交法第117条2項)
ひき逃げが成立するためには、「過失運転致死傷または危険運転致死傷」と「救護義務違反」を別々に犯すのではなく、同一人物が同じ現場で同時に犯す必要があることに注意してください。
事故に気づかなかった場合は救護義務違反にならない
ひき逃げを構成する救護義務違反は、故意犯(わざと罪を犯すこと)です。
故意犯であるためには、事故の発生を認識している必要があります。
自分が人身事故の加害者であるとわかっているのに、あえて被害者を救護せず逃げたからこそ、ひき逃げという重い犯罪となるわけです。
たとえば、次のような事例を想像してみてください。
「夜間、交差点を照らす街灯が全くない農道。信号も横断歩道もない交差点を走行していた大型ダンプが、死角から突然走ってきた小さな子供の足をひいてしまった。しかし、子供の存在に全く気づかなかったため、回避することも停止することもなくそのまま走り去った」
このようなケースでは、死角から急に飛び込んでくる子供の存在をはっきり視認することは、きわめて困難です。
また、大型ダンプが小さな子供の足をひいてしまったような場合、事故発生時の衝撃や違和感が小さいために、運転者が事故に気づかないことも少なくありません。

赤井耕多
運転者に事故を起こした認識がない場合は救護義務が否定されるため、ひき逃げが成立しない(過失運転致死傷だけが成立する)可能性があります。
ひき逃げすると重い懲役刑になりやすい3つの理由
ひき逃げをしてしまうと、次の3つの理由から、重い懲役刑となる可能性が高くなります。
重い懲役刑になる理由
・重傷・死亡事故になりやすいから
・併合罪で刑が加重されるから
・危険運転が成立すると量刑が重くなるから
重傷・死亡事故になりやすい
ひき逃げは、被害者がすぐに救護されたケースと比べると重傷・死亡事故になりやすいため、重い懲役刑になる可能性があります。
たとえば、夜間で人通りのない時間帯にひき逃げ事件が起きた後、重傷の被害者が長時間放置されたとしましょう。
被害者の出血がひどい場合、すぐに救急搬送して輸血治療しないと命の危険があります。
もし頭部を強打して脳内出血を起こしていたら、すぐに救護しなければ確実に死亡するでしょう。
このようにひき逃げ事故では、被害者の救護が遅れることがしばしばあり、重傷・死亡にいたる確率が高くなるため、重い懲役刑で処断されるのです。
併合罪で刑が加重される
ひき逃げは併合罪で処理されるため、刑が重くなる可能性があります。

川口晴久
併合罪とは、一人の被告人が、裁判でまだ確定していない複数の犯罪を犯した場合です。
たとえば、「過失運転でひき逃げした」というケースでは、過失運転致傷罪と救護義務違反という複数の犯罪が成立するため、裁判で併合罪として処理されます。
このケースで最も重い罪は、過失運転致傷罪(7年以下の懲役)ではなく、救護義務違反(10年以下の懲役)です。
併合罪の法定刑は、最も重い罪の刑期の上限を1.5倍にするので、「懲役15年」が法定刑の上限となります。
このように、併合罪処理によって刑期の上限が延びることから、ひき逃げは重い懲役刑となりやすいのです。
危険運転が成立して量刑が重くなる
危険運転が原因でひき逃げを起こすと、過失運転のケースよりも量刑が重くなります。
これは危険運転によるひき逃げの方が重大な結果につながりやすいからです。
たとえば、大量に飲酒して正常な運転が全くできない状態で事故を起こすと(自動車運転処罰法第2条1号)、軽度の飲酒運転よりも重大な事故となるおそれがあります。
大幅な速度違反(同2号)や危険なあおり運転(同4〜6号)、信号無視(同7号)で事故を起こしたケースなども同様です。
また、危険運転に無免許運転が加わると、さらに法定刑が重くなります(自動車運転処罰法第6条)。
平然と無免許運転するような人は、そもそも正常な判断能力にとぼしく、重大な事故を起こす危険性が高いので法定刑が加重されているわけです。
このように、危険運転によるひき逃げでは、過失運転の場合よりも被害が大きくなる傾向があります。
そのため、重い懲役刑で処断されてしまうのです。
ひき逃げでも逮捕を免れたり刑を軽くする方法はある?
ひき逃げ事件を起こした人は、勤め先や家族のことが心配になり、こんなふうに考えてしまうかもしれません。
「警察に身柄を拘束(逮捕・勾留)されると、会社にすごい迷惑がかかるなあ……」
「実刑判決だと何年も刑務所暮らし。相手から損害賠償や慰謝料を請求されたら、きっと家族が肩代わりしてくれるのだろう。もう、あわせる顔がない……」
犯罪の加害者になってしまったとき、誰もが心配するのが「逮捕されてしまうのか?」「裁判で実刑になるのか?」ということでしょう。
では、ひき逃げ事件を起こした場合に、逮捕を免れたり刑を軽くしたりする方法はあるのでしょうか?
逮捕を免れる方法はない
ひき逃げ事件を起こした者が逮捕を免れる方法は「ない」と理解してください。
負傷者の救護や警察への報告をせず現場から逃走することは、きわめて自分勝手で悪質な犯罪です。
したがって、警察も犯人逮捕に向けて必死に捜査します。
ひき逃げ事件の検挙率(事故の加害者を特定し、ひき逃げの被疑者として扱った割合)をみると、重傷事故が79.4%、死亡事故で100%、重傷に至らないケースも含めた全検挙率でも69.3%です。
これだけ高い検挙率を維持できているのは、捜査機関がひき逃げ事件を重大視し、厳しい態度でのぞんでいるからです。
また近年、街頭防犯カメラや、ドライブレコーダーを搭載する車の数が急速に増えています。
そのため、ひき逃げ犯が現場から逃げても、捜査機関が記録映像を緻密に解析すれば、犯人の逃走経路や所在地を特定することは比較的容易でしょう。
以上をふまえると、ひき逃げ事件の犯人が逮捕を免れる方法は「ない」と断言できます。
刑を軽くしたいなら「自首」か「示談」
ひき逃げ事件の犯人が逮捕されないとしたら、「被害者の怪我の程度が軽く、逮捕前に示談が成立したため処罰感情がない」といった限られたケースだけです。
人身事故を起こしてしまうと、気持ちがあせってしまい、事故現場から逃げたくなるのは理解できます。
しかし、逃げなければ人身事故だけにとどまったものを、逃げてしまったために「ひき逃げ」という悪質な犯罪となり、重い懲役となるのはなんとも馬鹿馬鹿しいことです。
・人身事故を起こしてしまったら、すぐに被害者の救護と警察への報告を行う
・もし逃げてしまった場合でも、事件が捜査機関に発覚する前に、家族や信頼できる人に連絡し、自発的に自首する
・逮捕されてしまったら、一刻も早く刑事事件に詳しい弁護士に相談し、被害者に反省の気持ちを伝えて示談の交渉をする
このように正しい選択をすることが、人身事故の刑罰を軽くする唯一の方法です。
「ひき逃げで懲役刑」でも執行猶予がつけば刑務所行きはなし
ひき逃げ事件の被疑者として逮捕・起訴されたからといって、必ず懲役の実刑判決を受けるわけではありません。
執行猶予の可能性があるからです。
執行猶予の期間が満了すれば刑罰は「ゼロ」
執行猶予とは、裁判で3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に、1年〜5年の範囲で刑の執行を行わないことです(刑法第25条)。
たとえば、「被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の全部の執行を猶予する」という有罪判決を受けた場合、3年間おとなしく生活していれば刑務所に入ることはありません。
反対に、執行猶予期間中に新たな罪を犯し、禁錮以上の有罪判決を受けてしまうと、より重い実刑が科されることになります。
前回の執行猶予が取り消されるだけでなく、今回の有罪判決も合算されてしまうからです。

赤井耕多
ひき逃げ事件の裁判で執行猶予をもらったからといって、ハメを外してまた罪を犯すようなことは絶対に避けましょう。
執行猶予でも「前科」は避けられない
ひき逃げの裁判で懲役刑の判決を受けた場合、たとえ執行猶予がついていても、有罪であることに変わりありません。
したがって「前科」はついてしまいます。
前科持ちになることをどうしても避けたいなら、「不起訴」か「無罪判決」のどちらかが必要です。
しかしながら、ひき逃げ事件の被疑者として逮捕勾留されている状況では、「人違いで拘束された」などよほどのことがない限り、不起訴は期待できません。
また、いったん起訴されて刑事裁判となれば有罪率は99%にもなるため、無罪判決の可能性はほぼないでしょう。
このように、ひき逃げ事件を起こしてしまうとほぼ確実に有罪判決となるため、前科がつくことは避けられないと理解してください。
示談交渉で刑を軽くしたいなら、西船橋ゴール法律事務所へ
ひき逃げ事件の加害者になった場合、ほぼ確実に逮捕勾留されます。
また、「ひき逃げ」という行動自体に逃亡や罪証隠滅のリスクがつきまとうため、保釈請求のハードルも高くなります。
そして、刑事裁判となれば無罪となることはほぼありません。
このような状況では、裁判官に情状酌量を求めることで、量刑を少しでも軽くしてもらうことや執行猶予をつけてもらうことが最善の対策となります。

川口晴久
情状酌量を求める上で必要不可欠なのが「示談」です。
適切なタイミングと内容で示談を進めたい方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。
逮捕された方のご家族による法律相談は初回30分無料、メールでのお問い合わせは年中無休で受け付けています。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業 平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 学習院大学法科大学院修了 平成27年9月 司法試験合格 アトム市川船橋法律事務所 令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業 所属:千葉県弁護士会
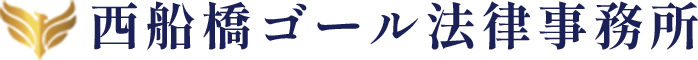
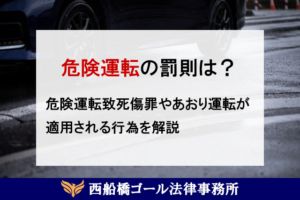

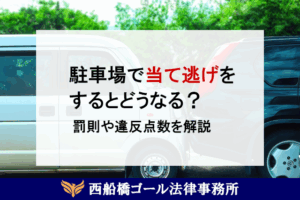
をしたら逮捕される?刑罰の重さは?-300x200.png)