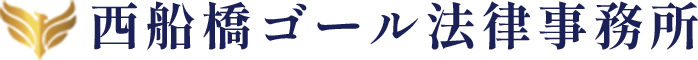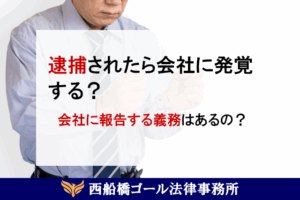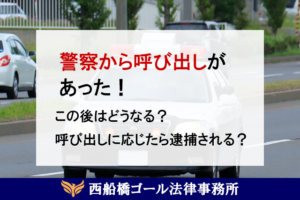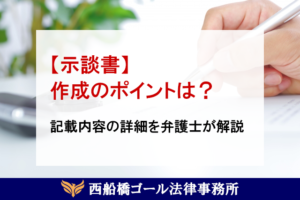取り調べに弁護士は同席できる?刑事事件の取り調べの立ち会いに関する権利とは
未分類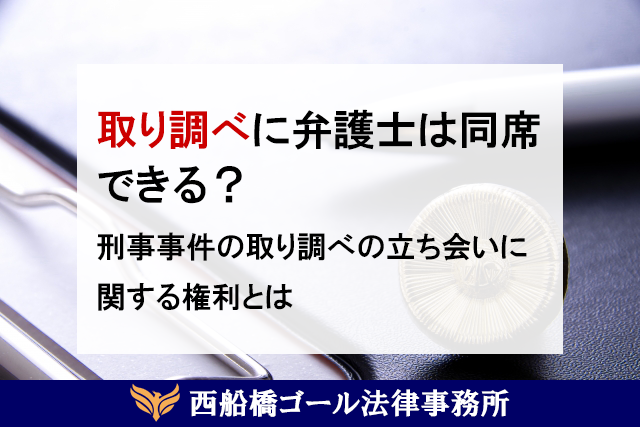
日本では、取り調べに弁護士が同席する権利は認められていませんが、例外的に許可されることがあります。
本記事では、弁護士の同席が認められるケース、同席できない場合の対応策、そして弁護士の重要な役割について解説します。
取り調べを受ける際に自分の権利を守るための知識を身につけましょう。
この記事でわかること
・弁護士の取り調べ同席の可否
・同席のメリット
・同席できない場合の対応策
目次
はじめに
突然、警察に逮捕されたら…多くの人が冷静でいられないでしょう。警察では捜査の一環として取り調べが行われますが、当然ながら捜査官は被疑者の味方ではありません。
逮捕や起訴された場合、誰でも弁護士を選任する権利があり、拘留中でも弁護士との面会が法律で認められています。
しかし、「取り調べに弁護士が同席できるのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
日本の法律では、取り調べに弁護士が同席する権利は明文化されていません。ただし、禁止されているわけではないため、捜査機関が許可すれば同席は可能です。しかし、実際にはほとんどのケースで同席は拒否されるのが現状です。
それでも、弁護士が取り調べに同席できない場合でも、被疑者が活用できる法的手段はあります。
取り調べに弁護士が同席できるという法律はない
捜査機関の取り調べに弁護士の同席を権利として認めている法律は今の日本にはありません。
面会や弁護士を選任する権利などはありますが、取り調べに同席する権利はないのが現状です。
弁護士が取り調べに同席できる状況は?
弁護士の同席は法的な権利として保障されているわけではありませんが、例外的に認められるケースもあります。それは、捜査機関が弁護士の同席を許可した場合です。
弁護士の同席は明文化された権利ではないものの、法律で禁止されているわけではありません。そのため、捜査機関が「同席を認める」と判断すれば、弁護士が立ち会った上での取り調べが可能になります。
しかし、実際には捜査機関が弁護士の同席を認めるケースは極めて少なく、ほとんどの場合で拒否されるのが現状です。
弁護士の取り調べ同席はなぜ認められにくいのか?
弁護士の同席は、認められにくいものの絶対にないというわけでもありません。
過去に、取り調べに弁護士の同席が認められたケースもあります。ただし、ほとんどの場合で、取り調べに弁護士が同席することは断られてしまうというのが今の現状です。
ですが、素人が同席するわけでもないのに、どうして捜査機関は弁護士の同席を避けたがるのでしょうか。
まず第一に、捜査機関は「真実を明らかにする」という目的で取り調べをしています。
取り調べでは、逮捕した人を時間内に送検するかどうかを判断しなければなりません。そのような中で、弁護士が同席するとスムーズな取り調べができなくなってしまうという懸念があるのかもしれません。
また、逮捕後の取り調べに弁護士が同席するケースは珍しく、まだ一般的ではないというのも、同席を断られる理由として考えられます。捜査官側も慣れていないということですね。
日本弁護士連合会が取り調べの際の弁護士の同席を支援している
日本弁護士連合会は、取り調べに弁護士が同席することを求めています。
これは、逮捕段階で侵害されやすい権利を守る目的や、不当な取り調べを未然に防ぐためとしています。
2024年4月から、日本弁護士連合会は捜査機関での取り調べに同席した弁護士に支援金を支払うという取り組みを始めています。
諸外国では取り調べに弁護士の同席が認められている?
日本では、法律に明記されていない取り調べに弁護士が同席する権利ですが、外国では権利として認められている国が多くあります。
アメリカやフランス、イギリス、台湾などは弁護士の同席を権利として認めています。中には、同席だけでなく取り調べに弁護士が介入できる国という国もあります。

川口晴久
日本では、禁止はされてないものの権利として認められてもいないため、グローバルな視点でみると遅れをとっているのが現状です。
参考資料:諸外国の刑事司法制度(概要)
判例:名古屋高判令和4年1月19日令和3年(ネ)第167号
取り調べに弁護士が同席しないデメリットはある?
弁護士が取り調べに同席できない場合に、どのようなデメリットが発生するのでしょうか。
精神的に追い詰められて不利な証言をしてしまう
逮捕直後の混乱した状況で、長時間にわたる取り調べを受けることは、精神的に大きな負担となります。
多くの人が恐怖を感じたり、萎縮したりすることで、冷静な判断が難しくなるでしょう。精神的な動揺により、思わぬ供述をしてしまう可能性もあります。
こうした状況の中で、取り調べを行う捜査官はあくまで真相を追求する立場であり、被疑者の味方ではありません。
そのため、弁護士が同席できることには大きな意義があり、不当な取り調べを防ぎ、被疑者の権利を守る役割を果たします。
慣れない環境の中で、家族や友人との会話もできずに毎日取り調べを受ける中で、ついつい精神的に追い詰められて自分に不利な表現をしてしまったり、誤解を生みやすい言葉を発してしまう可能性があります。
弁護士が同席した場合、不当な取り調べが行われる可能性を排除できる
日本では、逮捕後の取り調べは1日8時間以内と法律で定められており、それを超える取り調べは認められていません。
また、逮捕・拘留中であっても、食事やトイレを制限することは許されず、暴力や脅迫を伴う取り調べも違法とされています。
多くの捜査官は適正な手続きを守っていますが、それでも過去には不当な取り調べが問題となった事例があります。
弁護士が同席しない場合、取り調べは密室で行われ、被疑者と捜査官のやり取りが外部から確認しにくくなります。
不当な取り調べを防ぐためにも、弁護士が取り調べに同席することは重要であり、被疑者の権利を守る有効な手段となります。
弁護士が取り調べに同席する価値とは
取り調べは、被疑者にとって精神的にも肉体的にも負担が大きく、適切に対応しなければ自らに不利益な供述をしてしまう可能性があります。
特に、日本では弁護士が原則として取り調べに同席できないため、不当な取り調べや誘導尋問のリスクが指摘されています。弁護士が同席できる場合の価値は計り知れません。
では、弁護士が取り調べに同席することでどのような価値があるのでしょうか。
取り調べの段階での権利を保護してくれる
弁護士が取り調べに同席する最大の価値は、被疑者の権利を守ることにあります。
取り調べは、捜査機関が事件の真相を解明するために行われるものですが、精神的に追い詰められた状況で冷静な判断を失い、不本意な供述をしてしまうことがあります。
弁護士が同席している場合、不当な取り調べを抑制する効果が期待できます。
弁護士は被疑者の権利を熟知していて、捜査機関も慎重にならざるを得ません。捜査官が強引な手法を取ろうとした場合でも、弁護士の存在は牽制となり、適正な手続きを求めることが可能です。
さらに、取り調べにおける録音・録画の実施が義務化されたとはいえ、すべてのケースに適用されるわけではなく、録音が行われていてもその内容が問題視されることは少なくありません。

赤井耕多
取り調べの現場に弁護士が立ち会い、現場で被疑者の権利を保護することが極めて重要です。
法的なアドバイスを受けられる
取り調べを受ける際、多くの人が「どう答えればいいのか分からない」「何を話せば不利にならないか」と悩みます。
警察官や検察官の質問は巧妙であり、安易に返答してしまうと、後々不利な証拠として扱われる可能性があります。
また正当な権利であっても、それを本人が認識していないケースもあります。
弁護士が取り調べに同席することで、被疑者が不利になるような供述を誘導したり、威圧的な取り調べをしないように牽制できます。また、どのような取り調べが行われたかを現場で知っておくことで、今後の弁護方針を作る際に弁護士にとって有利になります。
さらに、弁護士が同席していると、被疑者は精神的にも安定しやすくなります。
取り調べは長時間に及ぶことが多く、孤独な環境の中で精神的に追い詰められることも少なくありません。弁護士がそばにいることで心理的な安心感を得ることができ、冷静に取り調べに対応しやすくなります。
取り調べに弁護士が同席できない場合はどうする?
弁護士が依頼者の取り調べに同席して立ち会うためには、捜査機関からの許可がなければなりません。
ですが、弁護士の同席ができなくても、合法的に認められている権利があるため、権利を行使して自分を守ることができます。
黙秘権の行使
まず、弁護士が同席できない場合に有効な手段の一つが黙秘権の行使です。
黙秘権は、憲法38条1項および刑事訴訟法311条1項で認められており、捜査機関や裁判所もこれを否定することはできません。簡単に言えば、取り調べで何を聞かれても答えない権利を持っているということです。
取り調べの際、捜査官に「黙秘権を行使します」と伝えれば、それ以降は一切発言しなくても問題ありません。

川口晴久
不用意な発言が不利な証拠となるリスクを避けるため、黙秘権を活用することは重要です。
また、「黙秘する=犯罪の証拠になる」と推測されることはなく、黙秘権の行使が直接的に有罪の決定要因となることもありません。
弁護士と連携しながら、適切に権利を行使することが、取り調べにおける防衛手段となります。
参考:憲法第三十八条
署名指印拒否
次に、取り調べにおける修正申立権と署名押印拒否権について知っておくことが重要です。
取り調べの最後には、供述調書への署名を求められますが、これは必ずしも応じる必要はありません。署名をするということは、「この取り調べの内容が正しい」と認めることになるため、内容に誤りや不服がある場合は署名を拒否する権利があります。
具体的な対応策としては、以下の2つが挙げられます。
・供述調書の訂正を要求する
・供述調書に署名しない
これらは、取り調べを受けた人に認められた正当な権利であり、捜査機関が強制的に署名させることは違法です。暴力や脅迫による強要、または本人の意思に反して勝手に署名をすることも禁止されています。
弁護士が同席できない場合でも、供述調書の内容に納得がいかない場合は署名を拒否し、後から弁護士と相談しながら対応を決めることが大切です。

赤井耕多
取り調べにおいて不当だと感じる点があれば、権利を正しく行使し、自身の立場を守ることができます。公権力である警察官に対し「一人で拒否する勇気がない」という方も多いので、弁護士が同行し、あらかじめ、警察に”弁護士監督のもと、署名押印しない”との予告をしておくこともあります。
弁護士と接見してアドバイスを受ける
弁護士と接見する権利は法律で認められています。
弁護士との面会は捜査官の立ち会いなしで行われるため、外部と連絡を取る貴重な機会となります。
取り調べを受ける際は、弁護士とできるだけ頻繁に接見し、適切なアドバイスを受けることが重要です。接見の際には、以下の点を確認しておきましょう。
接見で確認するポイント
・取り調べで聞かれたことや待遇について
・取り調べで何を話したのか
・不安や要望
・家族や職場への連絡の代行
・取り調べの受け答えのポイント
・これからの方針
弁護士は被疑者の権利を守る立場にあり、接見の内容が捜査官に漏れることはありません。
弁護士と密に連携することで精神的な支えとなり、取り調べにおいて適切な対応ができるようになります。
まとめ
日本では、取り調べに弁護士が同席する権利は法律で保障されていません。
しかし、捜査機関が許可すれば弁護士の同席は可能となり、その場合、被疑者の権利保護や法的アドバイスを受けられる大きな利点があります。ただし、実際にはほとんどのケースで弁護士の同席は拒否されるのが現状です。
取り調べに弁護士が同席できない場合でも、黙秘権の行使や供述調書の署名拒否、弁護士との接見など、認められた権利を正しく理解し行使することで、不当な取り調べに備えることができます。
逮捕後の取り調べに冷静に対応するためにも、弁護士と密に連携し、適切な法的サポートを受けることが重要です。
刑事事件でお困りの方は、千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所までご相談ください。

法政大学法学部卒業
学習院大学法科大学院修了
アトム法律事務所
アトム市川船橋法律事務所
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
所属:千葉県弁護士会